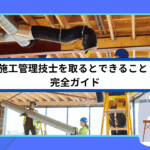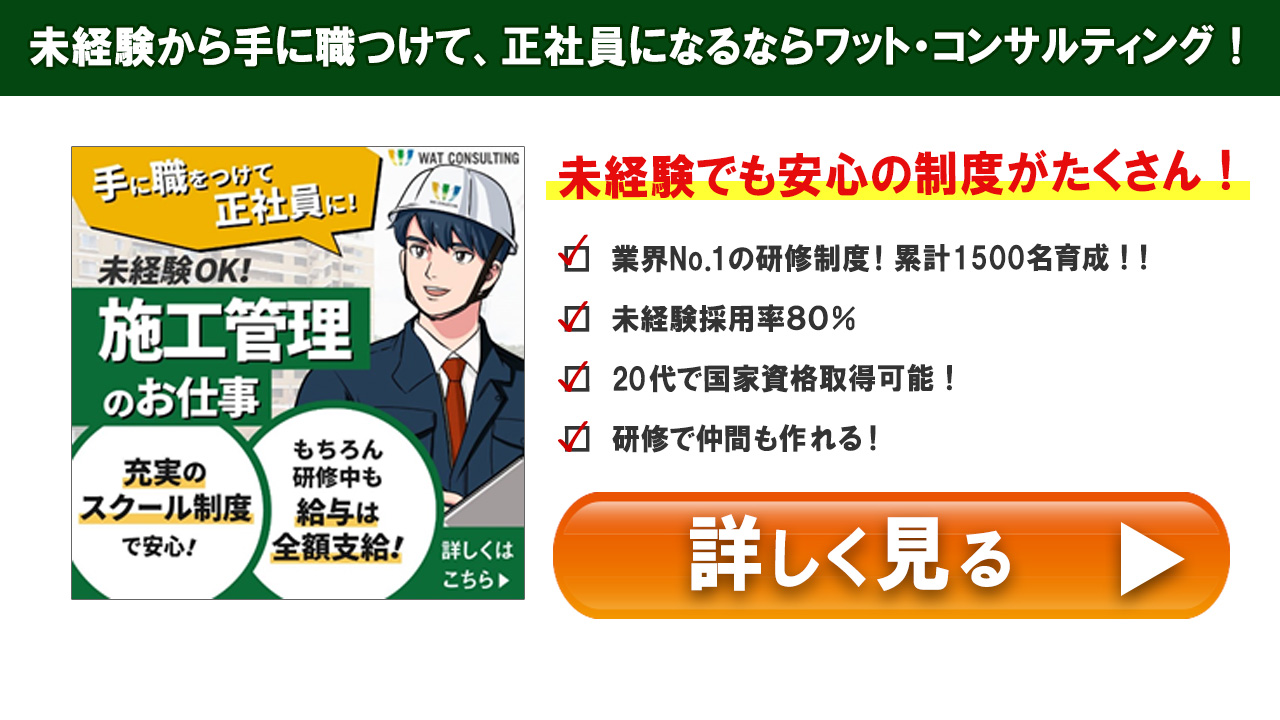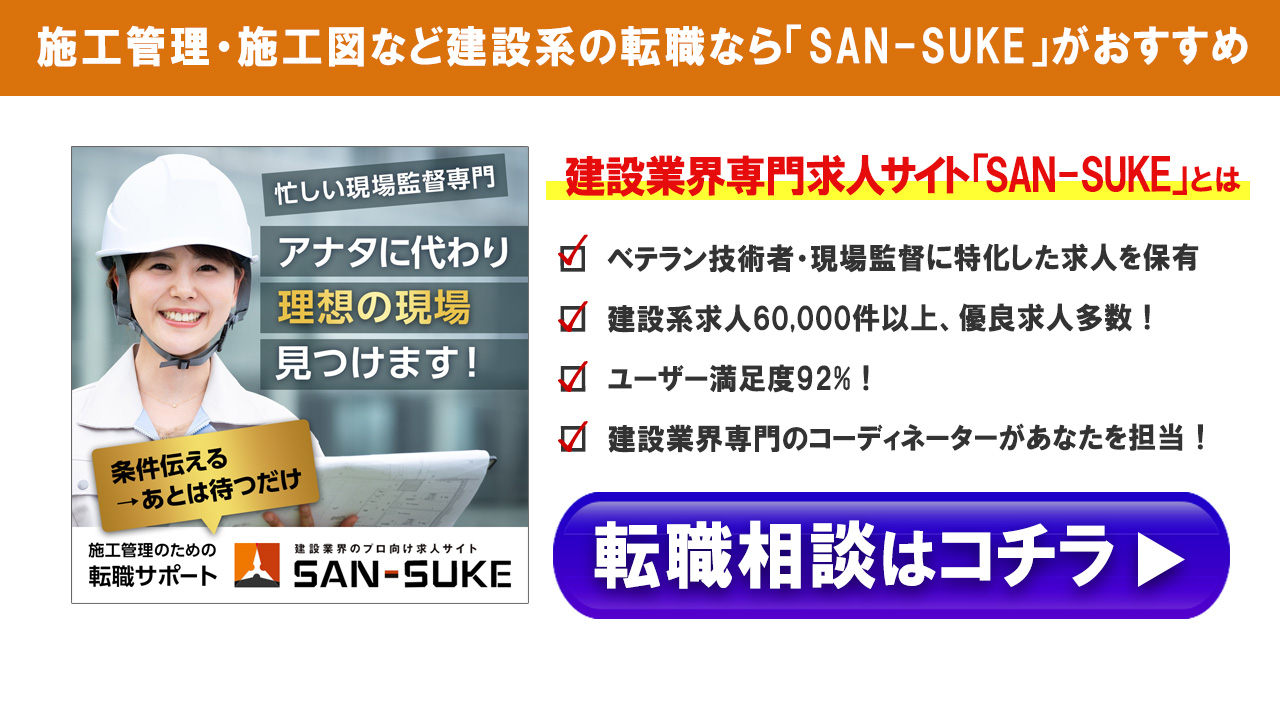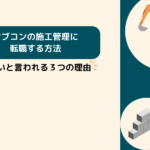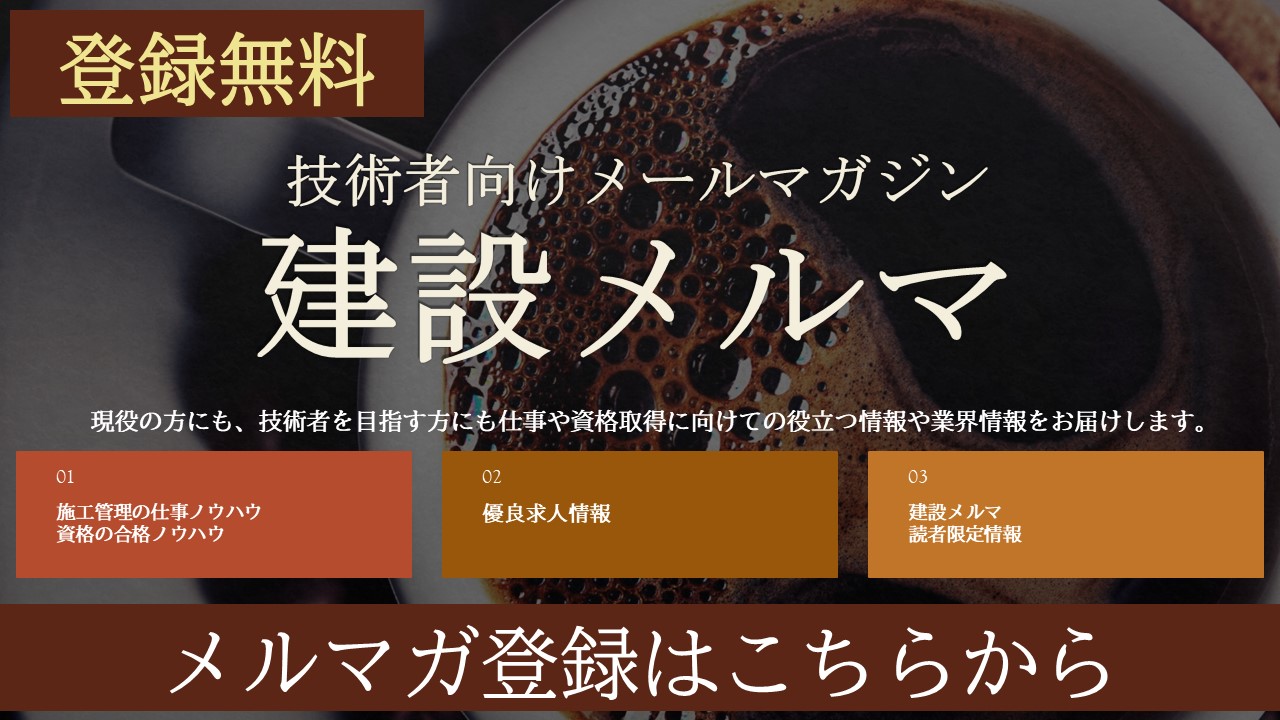「会社でRebroの講習や研修を導入したい」
「どうやって講習を運用すればいい?」
こういった疑問をお持ちの経営者様や研修担当者様向けの記事です。
この記事でわかること
- Rebroを導入するメリット
- レベル別|Rebro講習の学習プラン
- Rebro講習のスタイルと費用相場
Rebroは建築設備(空調・電気・配管)の3D設計に特化したBIMソフトです。
直感的な操作で3Dモデルを作成し、干渉チェックや施工図の作成が可能です。
設備設計の効率化と精度向上に役立ちます。
この記事では、企業でRebroの講習を導入する方法がわかります。
チーム全体のRebroの操作スキルを底上げしたい方は、最後まで読んでみてください。
Rebroの講習は、株式会社ワット・コンサルティングが提供する「Construction Boarding」がおすすめです。
いつでもどこでも学べるeラーニングなので、忙しい担当者でもスキマ時間でRebroを学べます。
Construction Boardingが合う企業様の特徴
- Rebroの人材育成に割く資金が足りない
- 残業を減らしながら人材育成する時間を捻出できない
- 社内でRebro講習制度を作るノウハウがない
無料で2週間のトライアルができて、さらに助成金の対象となるeラーニングです。
「まずはお試しで始めたい」「低コストでRebro講習を実施したい」という場合は、お気軽に資料請求してみてください。
※前置きはいいから、早く「Rebro講習の選び方を教えて!」という方は、Rebro講習のスタイルと費用相場にジャンプしてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣と研修を行う会社です。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
Rebro導入の背景と課題
国土交通省によるBIM/CIMや建設DXの推進で、三次元での設備設計が必要とされています。Rebroは空調や配管などの各種設備を立体的にまとめ、干渉を未然に見極めるためのBIMソフトとして注目されています。
しかし、2D CAD中心の業務フローを続ける現場にとっては、以下のような課題があるでしょう。
Rebro導入を成功させるには、従来の作図手順を見直したうえで三次元特有の運用を受け入れる姿勢が必要です。ネットワーク環境やハード面の検討に加え、現場が混乱しないよう初期段階から研修計画を設定しましょう。
2Dからスムーズに切り替えられるよう、管理職と担当者で協力して教育を進める取り組みが欠かせません。
ポイント
この記事ではRebroを導入するコツがわかるので、最後まで読んでみてください。
Rebroを導入するメリット
Rebroを導入するメリットを紹介していきます。
Rebroを導入するメリット
- 空調・配管・電気設備にフォーカスした機能
- 日本国内でのサポート体制・操作言語の優位性
- 他ソフトや各種データと連携性しやすい
設備設計で役立つため、まだ導入していない場合は検討してみましょう。
空調・配管・電気設備にフォーカスした機能
Rebroは空調や配管、電気関連のパーツを標準で備えており、三次元モデルで全体をスムーズにチェックできます。ダクトやケーブルの寸法を詳細に入力でき、干渉箇所を見落としにくい点も特長です。
立体的なレイアウトを確認すれば、施主や施工担当者との打ち合わせがスムーズになるでしょう。以下に主な機能をまとめます。
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| 機器パーツの標準ライブラリ | エアハンドラや照明器具などを選んで素早く配置できる |
| ケーブル配線機能 | 電気系統の長さや負荷を考慮しながらケーブル経路を設定できる |
これらの機能を活用すれば、配管や電気設備の複雑な接続を1つのモデルで整理できます。二次元の図面では把握が難しい相互干渉も短時間で発見でき、エラー削減につながるでしょう。
日本国内でのサポート体制・操作言語の優位性
Rebroは株式会社NYKシステムズが提供しているソフトで、日本語に対応しており、操作画面やマニュアルが国内向けに整備されています。海外製ソフトと比べると、バージョンアップの説明や導入事例を日本語で入手できる点が利点です。
ポイント
開発元のサポートデスクも国内企業向けの問い合わせに慣れており、疑問に素早く対応してくれます。
さらに、研修講座やオンラインセミナーが定期的に開催されているため、学習を続けるうえで便利でしょう。
他ソフトや各種データと連携性しやすい
Rebroは他のBIMソフトやCADデータとの連携が可能で、設備だけでなく建築や構造の情報を1つのモデルに統合できます。
例
IFC形式に出力すれば、別のソフトを使う協力会社とも干渉チェックや数量算出を共有できます。さらにExcelやCSVを介して資材リストやスケジュールを取り込めば、図面と連動したコスト管理がスムーズになるでしょう。
外部の積算システムと結合すれば、プロジェクト全体を見渡しながら効率的に進められます。さまざまなフォーマットに対応しているため、設計や施工段階のやり取りを一元化し、変更や修正を素早く反映できるところもメリットです。
レベル別|Rebro講習の学習プラン
Rebro講習は、担当者の習熟段階に応じて学習内容が変わります。以下はRebro講習の学習プランの例です。
レベル別|Rebro講習の学習プラン
- 初級レベル|Rebroの基本の使い方を学ぶ
- 中級レベル|作図スピードを上げていく
- 上級レベル|複雑な設備設計スキルを身につける
1つずつ解説していくので、講習設計の参考にしてみてください。
初級レベル|Rebroの基本の使い方を学ぶ
Rebroの初心者は、画面構成や主要コマンドを理解する段階です。インターフェース内のボタン配置を覚えれば、操作に迷いにくいでしょう。
例
配管を新規作成する際はプロパティパネルで管径や高さを入力し、2Dと3Dを切り替えてつながりを確かめる方法を知ると安心です。
ダクトや継手を入れるときに向きが逆転する場合があるので、ビューの回転やスナップ位置を早い段階で身につけるとトラブルを減らせます。最初は小規模のモデルで練習し、基本操作を着実に定着させましょう。
中級レベル|作図スピードを上げていく
中級者は3Dモデルの編集効率やレイアウト調整を意識して、作図時間の短縮を狙う時期です。
例
配管のルートを一括で再配置したり、ダクト径をまとめて変更したりするテクニックを学ぶと、手戻りを防げます。プラグインや連携ソフトの導入も検討し、Excelから部材リストを読み込んで属性を付加すれば入力の手間を減らせます。
ビューごとにテンプレートを設定すると、階層別の図面管理が容易になるでしょう。複数部署とやり取りする段階なので、ファイル命名規則やバージョン管理のルールを決めておくとスムーズです。
実務での修正頻度が増える時期であるため、ショートカットの活用を学ぶ講習もおすすめです。
上級レベル|複雑な設備設計スキルを身につける
上級レベルでは、カスタム設定や独自テンプレートの作成を学ぶと良いでしょう。
例
配管材やダクト部材のカタログ情報を登録し、大規模物件に合わせて寸法や圧力損失をあらかじめ入力しておくと効率が上がります。企業独自のライブラリを整備すれば、プロジェクトごとの重複作業を回避できるでしょう。
大工場や高層ビルのように階層が多い案件では、モデルの分割や干渉チェックが増えるため、担当者同士の連携が不可欠です。最終的な品質を高めるため、進捗管理や関連ソフトとのデータ交換の流れまで見直してみましょう。
Rebro講習のスタイルと費用相場
Rebro講習の主な3つのスタイルを紹介します。
Rebro講習のスタイル
- eラーニング
- 集合研修
- オンライン研修
各講習スタイルのメリット・デメリット・費用相場・どんな企業に向いているかもまとめたので、社内体制や予算、学習の目的に合わせて選んでみてください。
eラーニング
eラーニングは、オンライン教材や録画コンテンツを視聴して学ぶ方式です。受講者が空き時間を見つけて進められるため、全員の予定を合わせなくても学習できます。
学習の進捗を管理できるシステムがあれば、社内でフォローアップしながら習熟度を高められます。
無料で試せるRebroのeラーニング
冒頭でもお伝えしましたが、Rebroの講習は「Construction Boarding」がおすすめです。
Construction BoardingはRebroを学べるeラーニングで、担当者がスキマ時間で学べます。
進捗管理機能もあるため、メンバーのモチベーションも維持しやすいです。
ポイント
「Construction Boarding」は、低コストでRebro講習を導入できます。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
集合研修
集合研修は、同じ場所に集まり講師の指導を直接受ける方法です。操作を確認しながら質問しやすく、他の受講者から得る学びも多いでしょう。
社内全員が同時に参加すると、習得度合いを比較しながら進められますが、会場費や交通費がかかる点に留意してください。
オンライン研修
オンライン研修は、Web会議ツールを活用し、講師と画面を共有しながら学ぶ形式です。遠隔地のメンバーが同時に受講できるため、出張経費を抑えやすい特徴があります。
リアルタイムで質問する際は、マイクやチャット機能を駆使し、講師とのタイミングを合わせる工夫が必要です。
Rebro講習の導入に活かせる補助金や助成金
Rebro講習に活かせる補助金や助成金を知っておくと、費用の負担を抑えながら講習を導入できます。以下はRebro講習に活かせる補助金や助成金の例です。
Rebro講習の導入に活かせる補助金や助成金
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
申請期限が限られる制度もあるため、必ず公式ホームページで最新情報を確認してください。1つずつ解説していきます。
ポイント
私たちが提供する「Construction Boarding」も、人材開発支援助成金の対象です。
コストカットしながらRebro講習を導入したい場合は、お気軽に資料請求してみてください。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
社員向けのスキルアップ研修全般を支える仕組みです。例えばRebro講習の費用やテキスト代が一部戻り、訓練時間帯の賃金も支給対象となります。
研修開始前に訓練計画を提出し、終了後に支給申請するため、事前準備とスケジュール管理が重要です。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
Rebro講習を通じた設備設計のDX推進も対象になりやすいです。研修計画の認定を受けたうえで実施し、後日申請により助成金を受け取ります。
2026年度までの時限措置なので、早めに申請しましょう。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設分野に向けた助成策で、Rebroの設備設計研修を技能向上訓練とみなし費用を補助できます。講習開始前に計画届を管轄労働局へ提出し、終了後に領収書などを添えて支給申請する流れです。
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
Rebro導入に必要なライセンス費用やシステム構築費の一部を国が負担します。公募期間が複数回あり、IT導入支援事業者との連携が必須です。
gBizID取得など事前準備もあるため、事務局の公式サイトをチェックしてスケジュールを立てましょう。
Rebro講習の効果を測定する方法
講習を導入したら、必ず効果測定しましょう。効果を高めるために講習を改善していくと、Rebroの作業効率が上がります。
以下はRebro講習の効果を測定する具体的な方法です。
Rebro講習の効果を測定する方法
- 事前・事後テスト
- アンケートで自己評価
- 作業時間の計測
- エラー・手戻り工数の測定
こちらも1つずつ解説していくので、効果測定の参考にしてみてください。
事前・事後テスト
以下のようにテスト結果を表にまとめ、講習前後の理解度を比較するのがおすすめです。もし伸び悩んでいる箇所がある場合は、別途フォローアップが必要かもしれません。
| テスト項目 | 受講前の点数 | 受講後の点数 |
|---|---|---|
| Rebroの基本操作 | 60点 | 80点 |
| 三次元モデルでの干渉検出 | 50点 | 80点 |
| 配管ルートの入力精度 | 65点 | 65点 |
| ダクトや電気設備の設定方法 | 40点 | 75点 |
数値が上がっていれば、講習内容がうまくいっている可能性が高いです。結果をチーム内で共有し、訓練計画を調整してみてください。
アンケートで自己評価
アンケートを活用すると、本人の実感を拾い上げられます。例えば次のような項目を尋ねると、スキルアップを把握しやすいです。
アンケートの項目例
- 講習前後でRebro操作に対する不安が減ったか
- 配管やダクトを三次元で管理するメリットを認識できたか
- ショートカットやテンプレートの活用方法を把握できたか
回答の集計だけでなく、自由記述欄で掴んだポイントや戸惑いを詳しく書いてもらうのもおすすめです。アンケートの内容を、今後の研修企画に活かしていきましょう。
作業時間の計測
講習後、実際の業務にかかる時間を計測してみてください。講習前と講習後で作業時間を定期的に計測すれば、Rebro講習が効率向上に繋がっているか判断できます。
例
1週間単位で集計し「修正工数が何分短縮したか」などを比較するのもおすすめです。
上司や同僚と結果を共有し、追加のテクニックを身につける必要性を検討する材料にもなるでしょう。
エラー・手戻り工数の測定
エラーや手戻りの回数・修正時間を把握することで、Rebro講習の成果を確認できます。例えば、干渉チェック不足に起因する配管の修正件数を数えたり、ダクト方向の誤りを直すのに費やした時間を記録したりすると良いでしょう。
ポイント
少しでも誤りが減っていれば、Rebroのメリットを活かせていると言えます。修正履歴を管理し、何が原因で手戻りが起きているかも解析するのがおすすめです。
エラー・手戻りの原因が操作ミスなら、講習内容の調整が必要です。
Rebroについてよくある質問
最後に、Rebroについてよくある質問に答えていきます。
Rebroの参考書で独学できる?
参考書を使った独学も不可能ではありません。実際にRebro解説書や操作マニュアルを入手し、サンプルデータを読み込みながら学ぶ方法もあります。
ポイント
しかし、企業として学習する環境を作る場合は、講習を通じてチーム全員の操作スキルを底上げするのがおすすめです。独学だとメンバーの知識に差がでたり、実際の業務に応用できなかったりするデメリットがあります。
チーム全体で学びたい場合は、講習を検討してみてください。
RevitやARCHICADとの違いは?
Rebro・Revit・ARCHICADの比較表は以下のとおりです。
どのソフトを導入するかは、自社の業務範囲との相性で判断すると良いでしょう。
参考:【無料あり】Revit講習の種類と選び方|企業導入のメリット徹底解説
Rebroを使うためのPC環境は?
Rebroを扱う際に必要なPCスペックは以下のとおりです。三次元モデルの描画負荷が高いので、CPUやメモリに余裕があると良いでしょう。
| 項目 | 推奨スペック |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7以上または同等クラス |
| メモリ | 16GB以上(複雑なモデルを扱う場合は32GB以上が望ましい) |
| グラフィック | NVIDIA GeForce GTXシリーズまたはQuadroシリーズなど専用GPU搭載 |
| ストレージ | SSD(Cドライブ)で512GB以上 |
| ディスプレイ | フルHD(1920×1080)以上の解像度 |
モデル規模が大きくなるほど処理負荷は上がるため、メモリとグラフィック性能が安定性に直結します。ネットワーク接続環境も検討課題です。社内サーバーに複数人が同時アクセスする運用では、有線LANを中心とした高速ネットワークを整備することが望ましいです。
まとめ|Rebro講習や研修でレベルアップしていきましょう
最後に、Rebro講習のスタイルの比較表をまとめておきます。
社内体制や予算、学習の目的に合わせて選んでみてください。
おすすめの講習
くりかえしですが、Rebroの講習は「Construction Boarding」がおすすめです。
Rebroを学べるeラーニングで、担当者がスキマ時間で学べます。
さらに「Construction Boarding」は、低コストでRebro講習を導入できます。
無料で2週間のトライアルもあるため、お気軽に資料請求してみてください。
貴社のRebro講習の参考になれば幸いです。