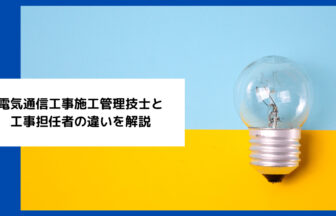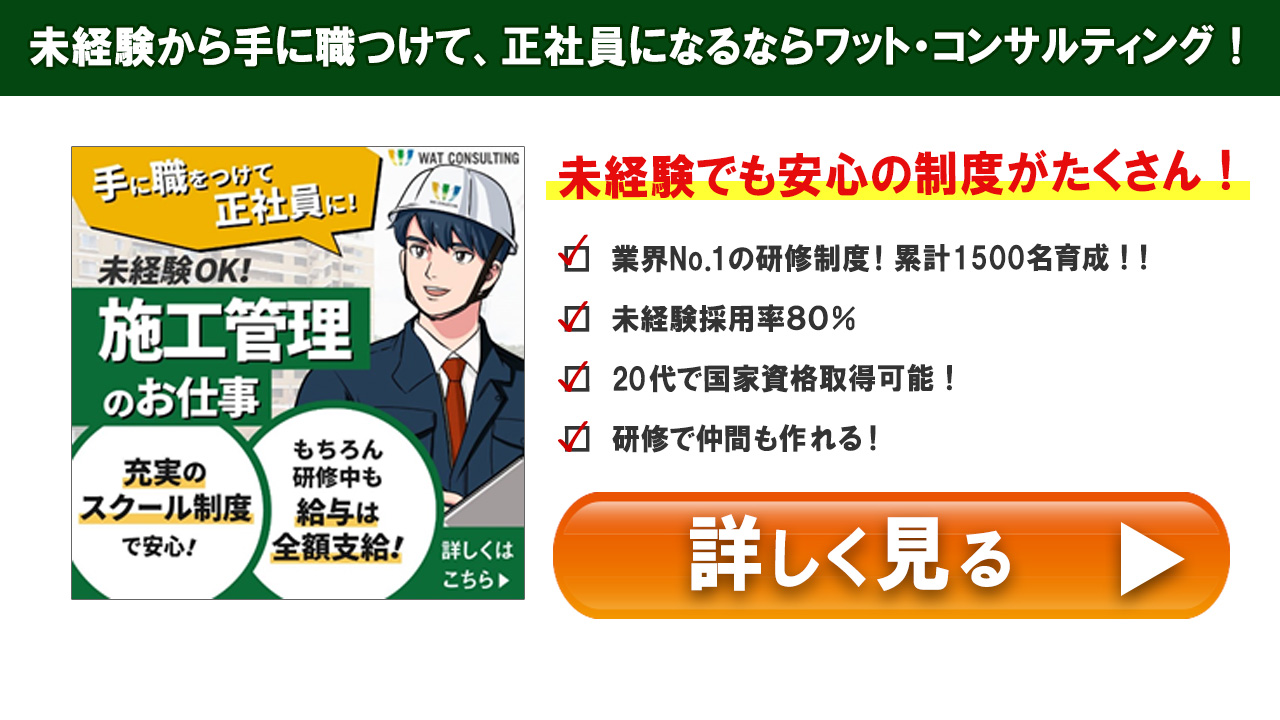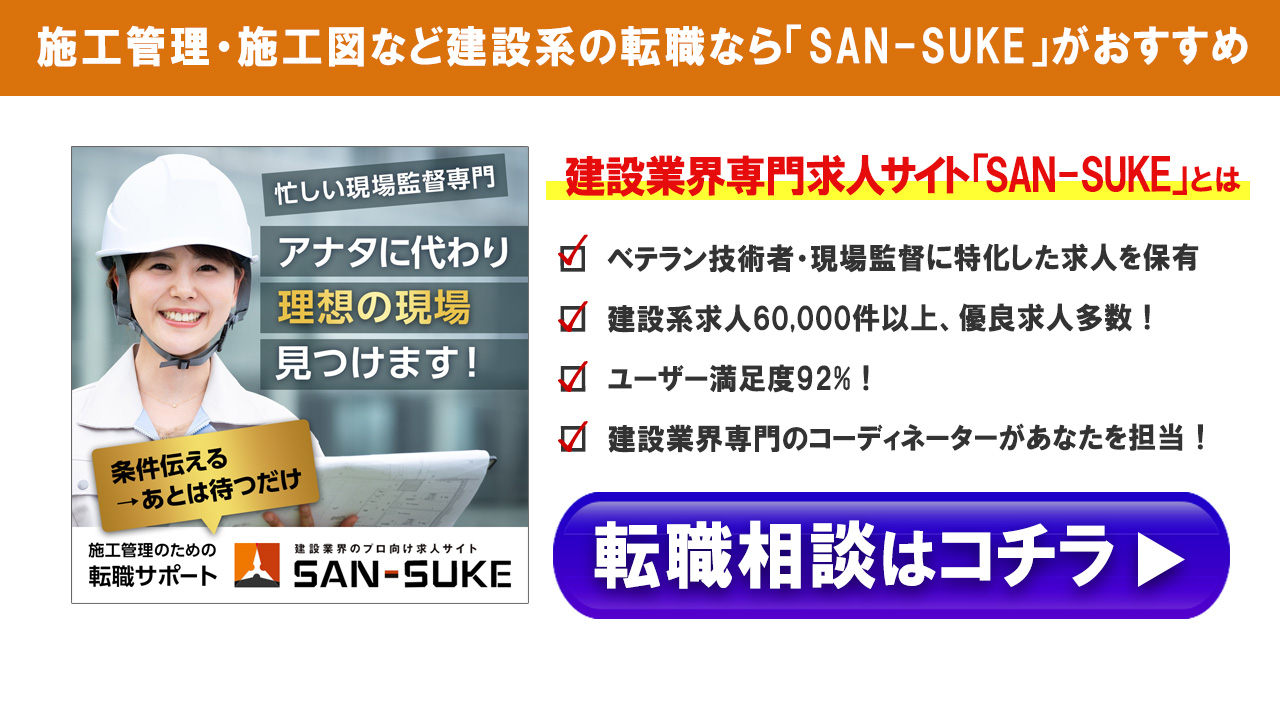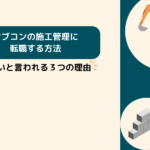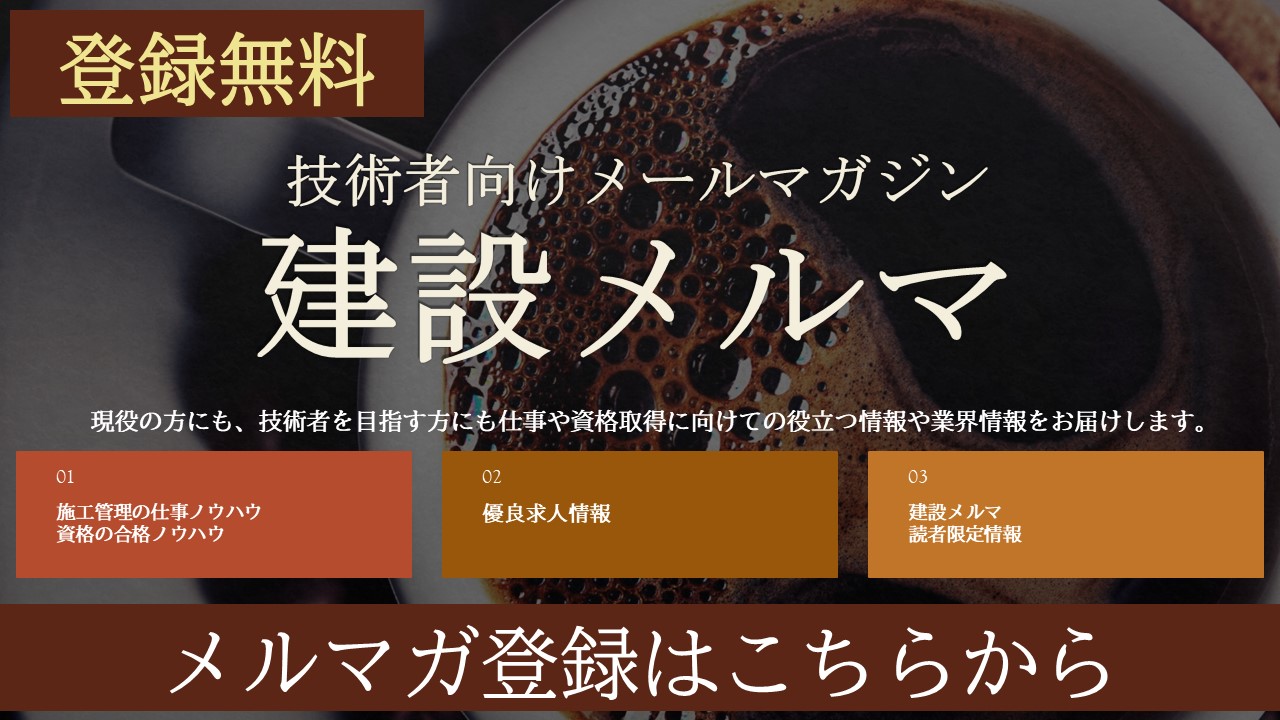2級がなくても、1級電気工事施工管理技士はいきなり受験できる?
キャリアアップを急ぎたい。
こういった疑問に応える記事です。
この記事でわかること
- 1級電気工事施工管理技士をいきなり受験してもOK
- 電気工事施工管理技士1級と2級の合格率の違い
- 1級電気工事施工管理技士の勉強方法
結論、受験資格を満たしていれば、いきなり1級電気工事施工管理技士から受験して大丈夫です。
1級電気工事施工管理技士を目指している人は、2級から受験すると1級取得までの年数が増えてしまうので、あまりおすすめしません。
ポイント
この記事では、令和6年度に変更した資格制度の情報に触れながら、1級電気工事施工管理技士の受験資格や勉強方法を解説します。
1級電気工事施工管理技士に合格すると得られる4つのメリットもまとめたので、参考にしてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣を行う会社で、施工管理の転職サポートも実施しています。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
1級電気工事施工管理技士をいきなり受験してもOK
くりかえしですが、1級電気工事施工管理技士をいきなり受験しても大丈夫です。
令和6年度に新たにスタートした制度では、19歳以上であれば誰でも第一次検定を受験できるようになりました。
1級電気工事施工管理技士の受験資格は以下のとおりです。
出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります
1級電気工事施工管理技士の新受験資格をまとめると以下のとおりです。
1級電気工事施工管理技士の新受験資格の特徴
- 19歳以上であれば第一次検定を受験できる
- 未経験者でも第一次検定を受験できる
- 第二次検定は第一次検定合格後に5年以上の実務経験が必要
旧受験資格は、第一次検定・第二次検定の両方とも実務経験が最低3年以上ないと受けられませんでした。
施工管理技士の新受験資格については、令和6年度から施工管理技士試験の受験資格が改正される|3つの注意点も解説で詳しくまとめています。
【注意】2級→1級の順序で受験するメリットはあまりない
1級電気工事施工管理技士の試験は、2級→1級の順に受験するメリットはあまりありません。
2級→1級の順に受験すると、1級を取得するまで時間がかかってしまうからです。
もし、2級から1級の順に受験した場合、1級を取得するまでに最短8年かかります。
一方、いきなり1級を受験すれば最短5年での取得が可能です。
1級から受験した場合
- 第一次検定:19歳以上ならすぐ受験できる
- 第二次検定:第一次検定に合格後、実務経験5年以上で受験できる
- 最短約5年で1級を取得
続いて、2級から受験した場合を見てみましょう。
2級→1級の順で受験した場合
【2級】
- 第一次検定:17歳以上ならすぐ受験できる
- 第二次検定:実務経験3年以上で受験できる
【1級】
- 第一次検定:19歳以上であればすぐ受験できる
- 第二次検定:2級合格後、実務経験5年以上で受験できる
- 最短約8年で1級を取得
1級を目指しているなら、2級を経由せず、1級から受験するのがおすすめです。
旧受験資格を満たしている方は早急に1級を受験しよう
旧制度の受験資格を満たしている方は、すぐに1級電気工事施工管理技士を受験しましょう。
令和11年以降は受験資格がすべて新受験資格に移行してしまい、旧受験資格では受験できなくなります。
新受験資格に移行してしまうと、第一次検定に合格後、新たに実務経験を5年以上積まないと第二次検定を受験できません。
つまり、資格取得までに5年間のタイムロスが発生してしまいます。
出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります
第二次検定の受験資格は「1級第一次検定合格後、実務経験5年以上」となっています。
令和10年度までであれば、第一次検定も第二次検定も旧受験資格のまま受験できます。
早めに受験して1級を取得しましょう。
電気工事施工管理技士における1級と2級の合格率の違い

でも、いきなり1級を受験するのは難しそう…
難易度はどれくらい違うか知りたい。
電気工事施工管理技士における1級と2級の合格率の違いは以下のとおりです。
近年の1級の合格率は以下のとおりです。
| 年度 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|
| 平成30年 | 56.1% | 73.7% |
| 令和元年 | 40.7% | 66.3% |
| 令和2年 | 38.1% | 72.7% |
| 令和3年 | 53.3% | 58.8% |
| 令和4年 | 38.3% | 59.0% |
| 平均合格率 | 45% | 66% |
参考:国土交通省
- 1級建築・電気工事施工管理技術検定「学科試験」合格者の発表
- 電気工事施工管理技術検定「実地試験」(1級・2級)の合格者の発表
- 令和元年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「学科試験」合格者の発表
- 令和元年度電気工事施工管理技術検定「実地試験」(1級・2級)合格者の発表
- 令和2年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「学科試験」合格者の発表
- 令和2年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「実地試験」の合格者の発表
- 令和3年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表
- 令和3年度建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
- 令和4年度1級建築・電気工事施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表
- 令和4年度建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
過去5年分の平均合格率は、第一次検定が約45%、第二次検定は約66%です。
次に2級の合格率を、過去5年分で見てみましょう。
| 年度 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|
| 平成30年 | 65.3% | 57.6% |
| 令和元年 | 56.3%(前期)50.0%(後期) | 61.3% |
| 令和2年 | 58.5% | 64.1% |
| 令和3年 | 60.3%(前期)57.1%(後期) | 68.7% |
| 令和4年 | 59.3%(前期)55.6%(後期) | 61.8% |
| 平均合格率 | 57% | 62% |
参考:国土交通省
- 2級建築・電気工事施工管理技術検定「学科試験(前期)」合格者の発表
- 2級電気工事施工管理技術検定の合格者を発表
- 令和元年度2級建築・電気工事施工管理技術検定「学科のみ試験(後期)」合格者の発表
- 令和元年度電気工事施工管理技術検定「実地試験」(1級・2級)合格者の発表
- 令和2年度2級建築・電気工事施工管理技術検定「学科のみ試験(後期)」合格者の発表
- 令和2年度2級建築・電気工事施工管理技術検定「実地試験」の合格者の発表
- 令和3年度2級技術検定「第一次検定(前期)」※合格者の発表
- 令和3年度建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
- 令和4年度2級技術検定「第一次検定(前期)」合格者の発表
- 令和4年度建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
第一次検定の平均合格率は約57%、第二次検定は約62%です。
1級と2級の合格率に大きな差はありません。
もちろん1級の方が試験は難しいですが、合格率が極端に低いことはないため積極的に挑戦してみましょう。
1級電気工事施工管理技士の試験は、計画的に勉強すれば合格できる試験です。
勉強方法はこのあと解説するので、このまま読み進めてください。
1級と2級における試験問題の難易度の違い
1級電気工事施工管理技能士試験は、大規模で複雑な電気工事を想定しているため、試験範囲の広さ、応用力が求められます。
試験内容は以下のとおりです。
※スマホを横にすると見やすいです。
| 1級 | 2級 | |
|---|---|---|
| 想定する工事の規模 | 大規模で複雑な工事現場 | 小規模から中規模の工事 |
| 第一次検定試験範囲 | ・電気工学などの一般的な知識 ・施工管理法の知識と応用力 ・法規の一般的な知識 | ・電気工学などの概略の知識 ・施工管理法の基礎的な知識 ・法規の一般的な知識 |
| 第一次検定解答形式 | 全てマークシート方式 | 全てマークシート方式 |
| 第二次検定試験範囲 | 監理技術者に必要な施工管理法の知識 | 主任技術者に必要な施工管理法の知識 |
| 第二次検定解答形式 | 記述式マークシート | 記述式マークシート |
1級では電気設備全般にわたる幅広い知識が必要で、特別高圧設備や大規模な施設での設計・施工の知識が問われます。
施工計画や原価管理、工期や法令の実務的な判断力が重要です。
「設計段階での施工性の検討」や「最適な工法との検討」といった、単純な知識ではなく総合的な判断力をためす問題が頻繁に出ます。
ポイント
電線の太さや導体の無制限電流などのコード計算、必要率や力率計算など、具体的な電気工学の計算問題も出題されます。
一方で、2級は高圧・低圧設備の施工に関する基本的な知識が求められますが、特別高圧設備や高度な管理スキルは問われません。
工事内容も限定的で、例えば「一般住宅の配線計画」や「電線管の種類の選択」など具体的なものが多いです。
安全管理や施工計画についても、基礎的な内容が中心です。
もちろん1級の試験の方が難しいですが、先ほどもお伝えしたとおり1級と2級で合格率はそこまで変わりません。
せっかく時間を割いて学習するなら、1級から合格を目指すと良いでしょう。
1級電気工事施工管理技士の第一次検定の勉強方法

いきなり1級を受験してみようと思うけど、勉強のコツがあれば知りたい。
1級電気工事施工管理技士の第一次検定の勉強は、4月頃からスタートしましょう。
試験日が7月なので、3ヶ月前の4月からコツコツと勉強をすれば間に合う可能性があります。
勉強のポイント
勉強する際は、参考書と過去問題集を購入し、過去5年分を3〜5周解くと良いでしょう。
1級電気工事施工管理技士は過去問と似た問題が多く出題されるので、過去問を中心とした学習がおすすめです。
おすすめの参考書と過去問題集は以下のとおりです。
| 著書名 | おすすめのポイント |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士第一次検定テキスト | 豊富な図や挿絵がある |
| 1級電気工事施工管理技士第一次検定基本テキスト2025年版 | 合格に必要な学習項目を網羅 |
| 1回で受かる!1級電気工事施工管理技術検定合格テキスト | 暗記に便利な赤シート付き |
| 1級電気工事施工管理技士第一次検定 分野別過去問題集2025年度版 | 過去6年分の試験問題を収録 |
| 1級電気工事施工管理技士第一次検定対策問解説集2025年版 | 全920問の解答・解説を完全掲載 |
| 1級電気工事施工管理第一次検定問題解説集2025年版 | 過去8年分の試験問題を収録 |
| 令和7年度 分野別問題解説集1級電気工事施工管理技術検定試験 第一次検定 | 無料の動画講習サービスがある |
| 詳解1級電気工事施工管理技術検定過去問題集’25年版 (2025年版) | 暗記に便利な赤シート付き |
特に、電気工事施工管理の経験が浅い方は、重点的に勉強しましょう。
アプリも使って隙間時間も勉強するのがコツです。
1級電気工事施工管理技士の勉強でおすすめのアプリは、1級電気工事施工管理技士の試験勉強におすすめのアプリ8選を紹介で紹介しています。
1級電気工事施工管理技士の第二次検定の勉強方法
1級電気工事施工管理技士の第二次検定の勉強方法は以下のとおりです。
第二次検定の勉強方法
- 第二次検定用のテキストと過去問題集で勉強する
- 経験記述の文章を書く
- 経験記述の文章を添削してもらう
こちらも1つずつ詳しく解説します。
第二次検定用のテキストと過去問題集で勉強する
第一次検定に合格したら、第二次検定の勉強を始めましょう。
第一次検定の合格発表が8月で、第二次検定の試験日は10月なので、2ヶ月間コツコツ勉強すれば間に合う可能性があります。
第二次検定の勉強でおすすめのテキストと過去問題集は以下のとおりです。
| 著書名 | おすすめのポイント |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士第二次検定試験対策集 2025年版 | 必要項目が網羅されている |
| 1級電気工事施工管理第二次検定問題解説集2024年版 | 記述問題の豊富な事例を解説 |
第一次検定と同様に、第二次検定も過去問からの出題が多いため、過去問題集で重点的に勉強しましょう。
経験記述の文章を書く
第二次検定では経験記述の問題が出題されます。
今までに経験した電気工事について、対策したことや技術的なことを具体的に記述する問題です。
ポイント
品質管理・工程管理・安全管理から出題される傾向があるので、それぞれの文章をあらかじめ考えておきましょう。
過去問を見ながら傾向をつかみ、文章を練習しておくのがおすすめです。
経験記述の文章を添削してもらう
練習として記述した文章は、事前に添削してもらいましょう。
経験記述の文章は独特の書き方があり、第三者から見て読みにくい部分がないかなど、添削してもらうと精度が上がるからです。
ポイント
通信講座で添削を受けると、経験記述のプロに具体的なアドバイスをもらえます。
また、1級電気工事施工管理技士を取得している会社の先輩がいたら、添削をお願いするのも良いでしょう。
1級電気工事施工管理技士を取得する4つのメリット
1級電気工事施工管理技士を取得するメリットは、以下の4つあります。
1級電気工事施工管理技士を取得するメリット
- 監理技術者になれる
- 公共工事を受注しやすくなる
- 昇進・昇格しやすくなる
- サブコンに転職しや少なる
キャリアアップにはメリットが大きい資格なので、しっかり勉強して取得しましょう。
1つずつ解説します。
監理技術者になれる
1級電気工事施工管理技士を取得するメリットは、監理技術者になれることです。
監理技術者は、大規模な工事現場の責任者として現場を監督します。
つまり、企業に1級電気工事施工管理技士がいることで、大規模な工事が受注できるため、1級を取得することで企業の売上に貢献できます。
また、監理技術者として大きな現場を担当すれば経験値が増え、市場価値の高い人材になれるでしょう。
参考:国土交通省|技術者制度の概要
公共工事を受注しやすくなる
1級電気工事施工管理技士の取得により、企業は公共工事を受注しやすくなります。
公共工事を受注する際に指標となる、経営事項審査の点数を高くできるためです。
経営事項審査とは
経営事項審査とは、工事を請け負う業者の健全性を測るもので、点数が高いほど工事を受注しやすくなります。
2級電気工事施工管理技士の経営事項審査の加点は2点ですが、1級は5点です。
1級電気工事施工管理技士を取得することで、公共工事を受注しやすくなり、会社の売上アップに役立ちます。
昇進・昇給しやすくなる
1級電気工事施工管理技士を取得すると、監理技術者として大規模な工事を担当できたり、企業が公共工事を受注しやすくなったりするため、会社の売上に貢献できます。
それにともなって、社内で昇進・昇給する会社が多いです。
年収アップしたい方は、1級電気工事施工管理技士を取得しましょう。
サブコンに転職しやすくなる
サブコンへの転職が有利になることも、1級電気工事施工管理技士を取得するメリットです。
サブコンは「サブコントラクター」の略称で、大手ゼネコン(ゼネラルコントラクター)から委託された工事の一部を手がける専門施工会社です。
ポイント
具体的には、大規模な施設の電気や空調・消防・衛生などの設備系の工事を担当します。
サブコンは設備工事の大手企業であり、大規模な工事を請け負っていることから、給料も高い傾向があります。
サブコンは大規模な工事を受注するため、1級電気工事施工管理技士の資格がある方を積極的に採用したいと考えています。
いずれサブコンで活躍したいと考えているなら、1級電気工事施工管理技士の資格を取得しましょう。
サブコンについては、サブコンの施工管理に転職する方法|きついと言われる3つの理由に詳しくまとめています。
まとめ|いきなり1級電気工事施工管理技士に挑戦しよう
1級電気工事施工管理技士の試験にいきなり挑戦しても大丈夫です。
2級から順番に受験した場合、1級を取得するまでに最短で8年かかってしまいますが、1級から受験すれば最短5年で取得できます。
現在は19歳以上であれば、実務経験を問わず誰でも第一次検定の受験が可能です。
ポイント
また、1級と2級では合格率に大きな差はなく、テキストや過去問で計画的に勉強すれば合格できる可能性があります。
まずはテキストや過去問題集を購入し、くりかえし問題を解きながら勉強しましょう。
あなたのキャリアアップの参考になると嬉しいです。