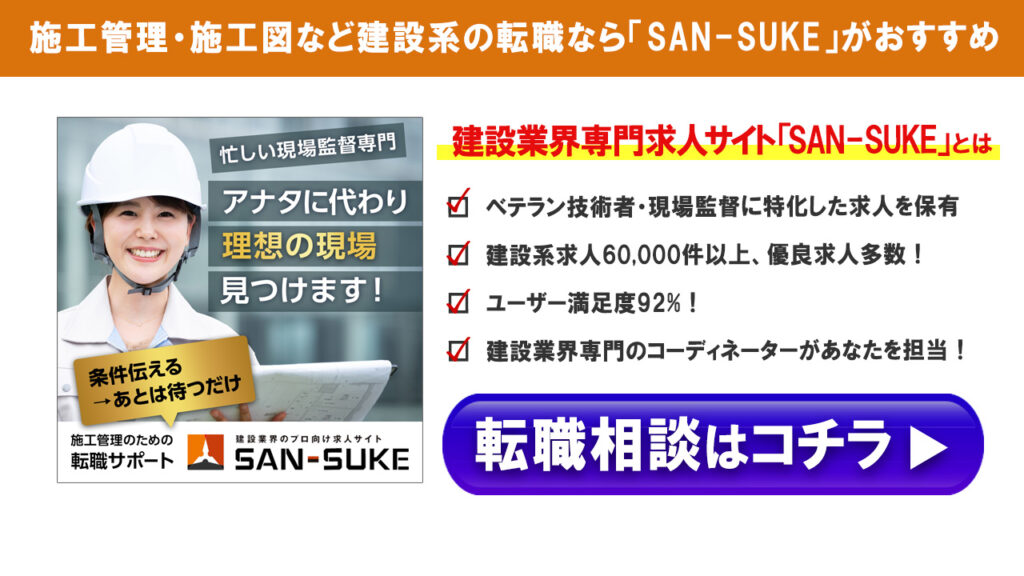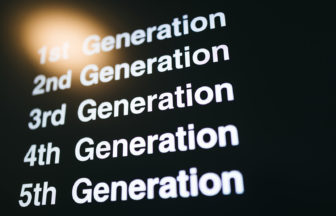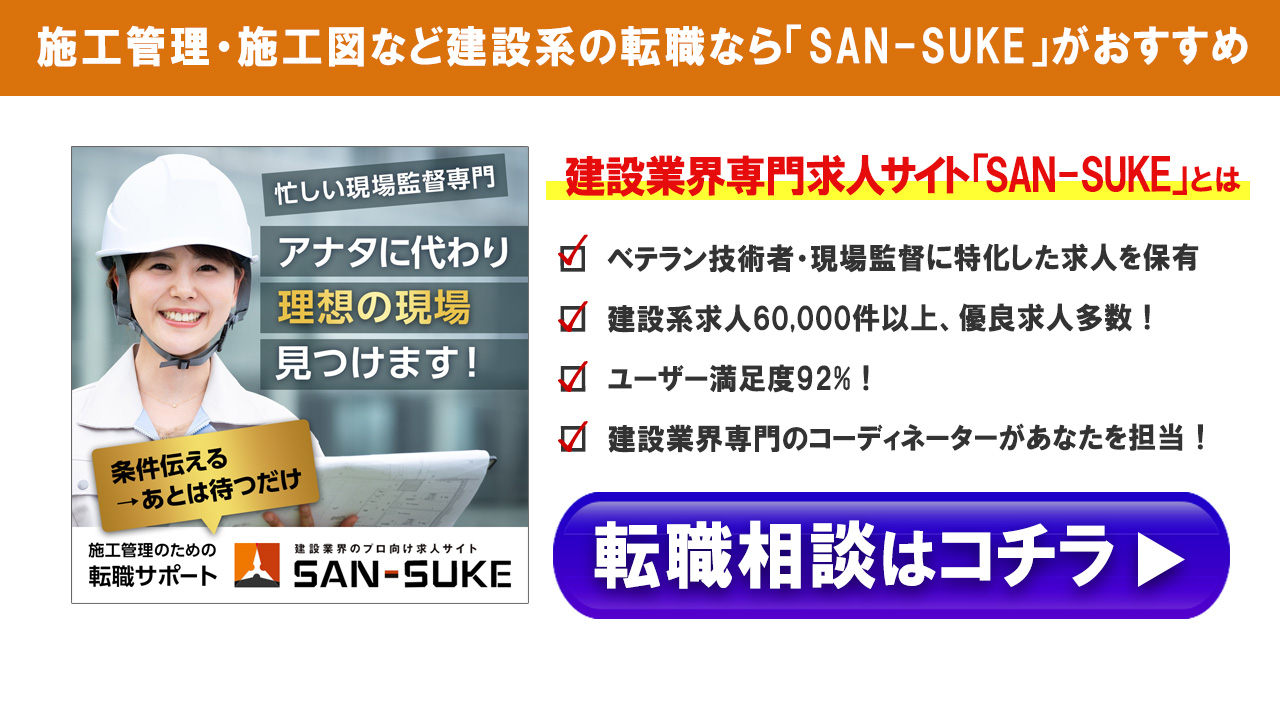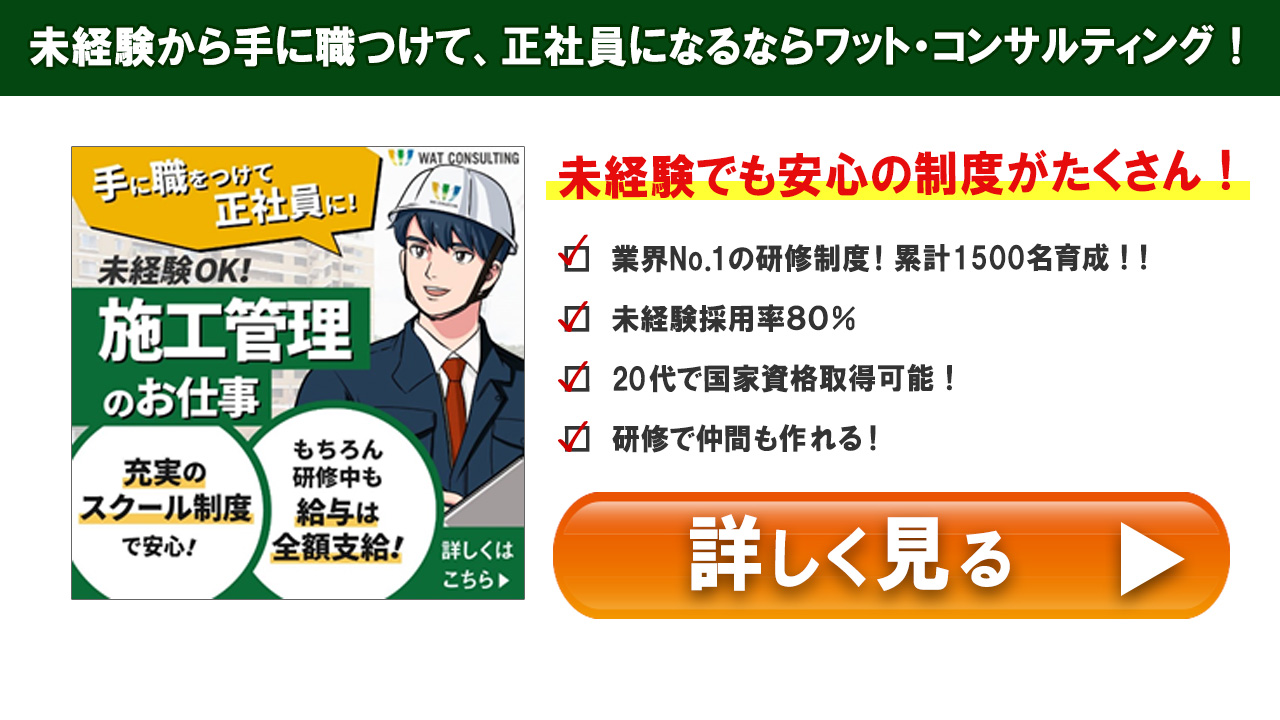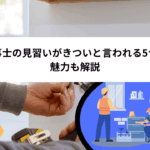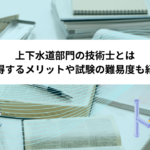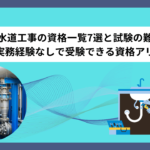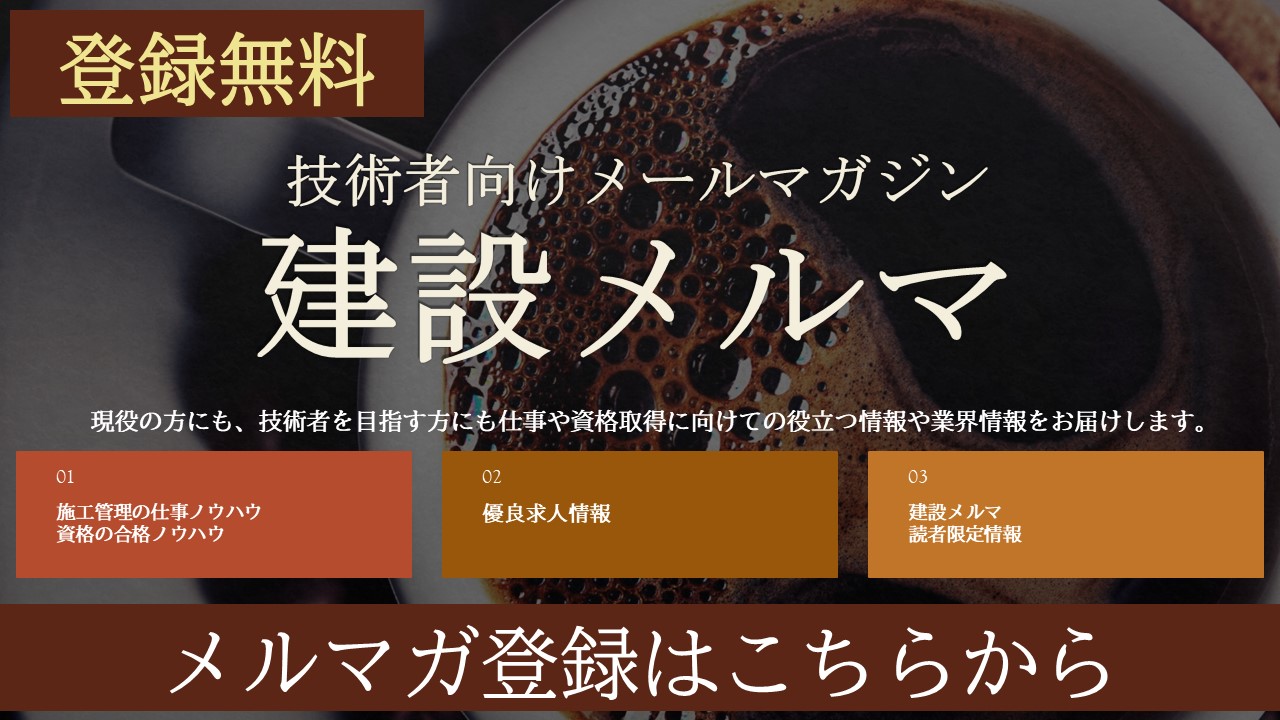消防設備士の合格率からみる難易度を紹介します。
受験資格がなく誰でも受験できて、消火器を扱える乙6などがとても人気の資格です。
また、自動火災報知やガス漏れ火災警報などを扱う甲4や、漏電火災警報器を扱う乙7も人気です。
就職や転職にも有利な資格なので、ぜひとも取得したいところですよね。
この記事では下記などを紹介します。
- 消防設備士の合格率からみる難易度
- 合格するための勉強方法や勉強時間
- おすすめのテキストや参考書
- 他の資格との難易度の比較
あなたの消防設備士合格の参考になればうれしいです。
目次
【まず】消防設備士の種類

消防設備士には大きく分けて甲種と乙種があります。
- 甲種:消防設備の点検・整備・工事が可能
- 乙種:消防設備の点検・整備だけが可能
となっており、甲種の方が業務可能な範囲が広いです。
さらに甲種と乙種には細かい分類があり、下記にように分かれています。
- 甲種:特類・1類・2類・3類・4類・5類
- 乙種:1類・2類・3類・4類・5類・6類・7類
消防設備士の合格率からみる難易度

消防設備士の合格率からみる難易度を解説します。
- 甲種全体:30%前後
- 甲種1類:25%前後
- 甲種2類:35%前後
- 甲種3類:35%前後
- 甲種4類:30%前後
- 甲種5類:35%前後
- 甲種特類:20%前後
- 乙種全体:35%前後
- 乙種1類:30%前後
- 乙種2類:35%前後
- 乙種3類:30%前後
- 乙種4類:33%前後
- 乙種5類:40%前後
- 乙種6類:40%前後
- 乙種7類:60%前後
※くわしい合格率については、一般財団法人消防試験研究センターのサイトを確認してください。
全体的に、甲種の合格率の方が低くなっています。
最難関は甲種特類ですね。
ただし、多くの試験が合格率30%台なので、きちんと勉強しないと難易度が高いと言えるでしょう。
消防設備士の試験内容からみる難易度
消防設備士の試験内容は下記のとおりです。
- 甲種:筆記試験(4択マークシート)、実技試験(選択・記述・製図)
- 乙種:筆記試験(4択マークシート)、実技試験(選択・記述)
乙種は製図試験がない分、甲種より難易度が低くなっています。
ちなみに、甲種特類は筆記試験のみですが、試験問題の難易度が一番高いです。
試験内容の難易度は下記のとおり。
- 甲種特類
- 甲種1~5類
- 乙種
乙種1~7類を難しい順に並べると下記のイメージです。※もちろん個人差はあります。
- 5類
- 2類
- 3類
- 1類
- 4類
- 7類
- 6類
消防設備士の乙種6類はおすすめ!受験資格は「誰でも受験できる」
消防設備士の中でもおすすめなのは乙種6類です。
乙種6類は消火器を取り扱う資格です。
消火器は1つの建物にたくさん設置されるため乙種6類の仕事は多いです。
乙種は受験資格がなく誰でも受験できるため、とても人気の資格です。
乙種試験の受験者の約3割は乙種6類の受験です。
甲種4類も人気
甲種4類もおすすめです。
甲種4類は火災報知器に関する資格ですが、1つの建物に火災報知器も多く設置されているため甲種4類の需要は高いです。
甲種4類はビルメン4点セットの資格に付加価値をつける資格ともいわれてます。
ちなみに「ビルメン4点セット」の資格は、下記の4つ。
- 第二種電気工事士
- 2級ボイラー技士
- 第三種冷凍機械責任者
- 危険物取扱者乙種4類
甲種の受験者の半分近くは甲種4類の受験です。
消防設備士の勉強時間や勉強方法

消防設備士に合格するための勉強時間や勉強方法をご紹介します。
仕事をしながら受験する人も多いでしょうから、効率よく勉強して合格をつかみとりましょう。
勉強時間や勉強期間
消防設備士に合格するための勉強時間の目安は甲種と乙種で違います。
- 乙種:40時間~70時間
- 甲種:60時間~200時間
勉強時間にだいぶ幅がある理由は下記のとおり。
- 人によって知識量や得意分野が違うから
- 人によって1日に勉強できる時間が違うから
- 受験する試験によって難易度が違うから
勉強期間の目安は下記のとおりです。
- 乙種:2ヶ月前から勉強スタート
- 甲種:3ヶ月前から勉強スタート
甲種の勉強期間を長めにとるのは、乙種よりも問題が難しいのと、実技試験の製図問題の勉強時間が必要だからです。
また、半年~1年と長い勉強期間をとってしまうと、前に覚えたことを忘れることがあります。
甲種の製図問題以外はほとんど暗記なので、2~3ヶ月の短期間で覚えてしまった方が良いでしょう。
甲種の勉強時間のイメージは下記のとおり。
- 仕事がある日1時間・休日3時間で3ヶ月勉強:総勉強時間は約140時間
- 仕事がある日30分・休日4時間で3ヶ月勉強:総勉強時間は約130時間
一方、乙種の勉強時間のイメージは下記です。
- 仕事がある日1時間・休日3時間で2ヶ月勉強:総勉強時間は約90時間
- 仕事がある日30分・休日4時間で2ヶ月勉強:総勉強時間は約85時間
独学におすすめのテキスト・参考書・問題集
消防設備士の勉強では、工藤政孝さんの本などがおすすめです。
amazonで「工藤政孝」と検索するとわかりやすいですよ。
初めて消防設備士を受験する人にもおすすめの本です。
ただし、テキスト・参考書・問題集はいくつも買いすぎないようにしてください。
たくさん買っていくつもの本に手を出すよりも、自分が勉強しやすそうな本をくりかえし勉強する方が合格できます。
本の感じは実際に手に取って見てみるのが一番なので、じっくり選びたい人は書店にいってペラペラとページをめくって自分に合いそうなものを選びましょう。
消防設備士試験の勉強で少々やっかいなのが、過去問題集が少ないことです。
消防設備士は過去問を一部しか公開していないため、上記のような問題集で対策しましょう。
消防設備士に合格するための勉強のコツ

合格するためのコツは下記のとおりです。
- まずはテキストを読んで基礎を勉強してから問題集を繰り返し解く
- 移動時間に勉強する
- 勉強したことを人に教える
- どんなに疲れていても短時間でいいので勉強する
- 15分睡眠がおすすめ
- 疲れ切る前に休憩を入れる
1つずつ解説します。
まずはテキストを読んで基礎を勉強してから問題集を繰り返し解く
資格の勉強の王道は「過去問集をくりかえし解く」ですが、消防設備士は過去問の情報が少ないです。
問題集だけを勉強すると応用が効かなくなるので、まずはテキストで基礎を勉強しましょう。
おおまかな勉強の流れは下記のとおり。
- まずテキストをざっと読む
- 問題集を解く
- 問題の解説を読んでもわからないときは、テキストを確認する
- また問題集を解く
という感じで、あとは②~④のくりかえしです。
問題集の問題と答えを覚えるまで勉強して、9割解けるようになれば安心です。
問題集は最低5回は解きましょう。
移動時間に勉強する
通勤や通学に電車やバスを使う人は移動中に勉強しましょう。
例えば、片道1時間の通勤時間であれば往復2時間です。
移動中に2時間勉強することができて効率的です。
勉強したことを人に教える
勉強したことを人に教えてみましょう。
人に教えることで自分が覚えます。
また、人に教えられるということは意味を理解しているということなので、理解を深めるためにもおすすめです。
仲の良い人に協力してもらいましょう。
どんなに疲れていても短時間でいいので勉強する
仕事しながら勉強するのは本当に大変ですよね。
「今日は本当に疲れたから勉強ムリだ…」ということもあると思います。
でも、1日サボってしまうとサボり癖がついてしまい勉強しなくなってしまいます。
疲れていて辛いときでも短時間でもいいので勉強しましょう。
5分だけでもかまいません。
消防設備士の試験は暗記問題が多いので、勉強のブランクを空けてしまうと前に覚えたものも忘れてしまいます。
短時間でもいいので毎日勉強するクセをつけましょう。
15分睡眠がおすすめ
勉強にどうしても集中できないときってありますよね?
集中できないときは15分睡眠がおすすめです。
個人差はありますが、15分睡眠はかなり頭がスッキリします。
記憶は寝ているときに頭に焼きつくので、こまめに15分睡眠をとるのは良いことなのです。
反対に1時間以上寝てしまうとかえって疲れてしまいますし、寝ぼけた状態が長く続き非効率。
勉強は根性ではありません。
効率的に覚えるために、体のコンディションを整えましょう。
疲れ切る前に休憩を入れる
疲れ切る前に休憩すると回復が早いです。
「あとちょっとがんばれるかな」という手前で休憩しましょう。
疲れ切ってから休憩すると回復まで時間がかかり、勉強時間が減ってしまいます。
休憩のとり方が上手な人は「30分勉強したら10分休む」「1時間勉強したら15分休む」というように時間割を組んで勉強します。
アラームをかけておいて、時間がきたら強制的に休憩をとると、集中力を長時間持続できます。
ちなみに、この手法はメンタリストのDaiGoさんが言っていた方法です。
効率よく勉強する方法などはDaiGoさんのYoutube動画「脳覚醒!集中しまくっても疲れない脳の作り方」が参考になりますよ。
消防設備士は就職・転職も有利になる

消防設備士の資格を取得すると就職・転職に有利です。
消防設備士は、下記などの人が集まる場所の消防設備や防災設備の点検・整備・工事を行う国家資格です。
- オフィスビル
- 商業施設
- ホテル
- 学校
- 病院
- 公共施設
- 劇場
- マンション
消防設備・防災設備の設置は義務なので、国家資格をもつ消防設備士が必要なのです。
主な就職先は下記のとおり。
- ビル管理会社
- ホテル
- 商業施設
- 防災保守点検会社
- 消防設備メーカー
- 警備会社
都市圏を中心にビルやマンションなど大型の建物が増えており、消防設備士の需要が高くなっています。
求人が多いことから仕事には困らないでしょう。
建物の消防設備を設置するときは消防設備士の立ち合いが必要です。
消防に届け出る書類には、下記などを届出に記載する必要があります。
- 消防設備士の免状の種類・番号
- 住所と名前
- 講習履歴
また、消防設備は定期点検が必要なので、消防設備士の仕事は継続性があり安定して稼げます。
もちろん、消防設備士として長く働くなら勉強を続けることは必要です。
消防設備士に向いている人はまじめな人です。
消防設備に異常があると有事の際に人命にかかわります。
1つ1つの業務を正確にこなすことが求められます。
消防設備士と他の資格の難易度の比較

消防設備士の取得を検討している人は、他の資格との難易度の比較も気になりますよね。
資格を取得する順番の参考にもしてみてください。
消防設備士とボイラー技士の難易度の比較
消防設備士とボイラー技士の難易度の比較は、条件によって変わります。
- 消防設備士乙種と二級ボイラー技士の難易度はほとんど同じ
- 消防設備士乙種と一級ボイラー技士なら、一級ボイラー技士の方が難易度が高い
- 消防設備士甲種と二級ボイラー技士なら、消防設備士甲種の方が難易度が高い
- 消防設備士甲種と一級ボイラー技士なら、製図問題があるため消防設備士甲種の方が難易度が高い
- 消防設備士甲種特類と特級ボイラー技士なら、記述問題が多いため特級ボイラー技士の方が難易度が高い
※人によって難易度が変わる可能性はありますが。
ボイラー技士については、ボイラー技士二級・一級・特級試験の難易度や合格率を参考にどうぞ。
消防設備士と電気工事士の難易度の比較
消防設備士と電気工事士の難易度の比較は、条件によって変わります。
- 消防設備士乙種と二級電気工事士なら、技能試験があるため二級電気工事士の方が難易度が高い
- 消防設備士甲種と一級電気工事士の難易度は同じくらい
- 消防設備士甲種特類と一級電気工事士なら、消防設備士甲種特類の方が難易度が高い
※人によって難易度が変わる可能性はありますが。
電気工事士については、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツを参考にどうぞ。
消防設備士と電気主任技術者の難易度の比較
消防設備士と電気主任技術者なら、圧倒的に電気主任技術者の方が難易度が高いです。
電気主任技術者は設備系の資格の中でもトップクラスの難関資格です。
電気主任技術者については、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツを参考にどうぞ。
まとめ【消防設備士は少し難易度が高いけど、きちんと勉強すれば合格できる】

消防設備士は乙種は難易度低めですが、甲種は製図問題があるので難易度が高いです。
過去問の情報が少ないのも特徴なので、テキストや参考書で基礎を勉強するのもお忘れなく。
受験の順番は乙種→甲種がおすすめです。
乙種は6類や7類、甲種は4類が良いでしょう。
合格率はおおよそ30%台が多く、勉強しないと絶対合格できませんが、きちんと勉強すれば合格できる資格です。
特に乙種はほとんど暗記でいけます。
試験の2~3ヶ月前から勉強をはじめましょう。
過去問が少ないので、問題集選びは重要です。
勉強方法のコツも参考にしてみてください!
あなたの消防設備士合格の参考になればうれしいです。