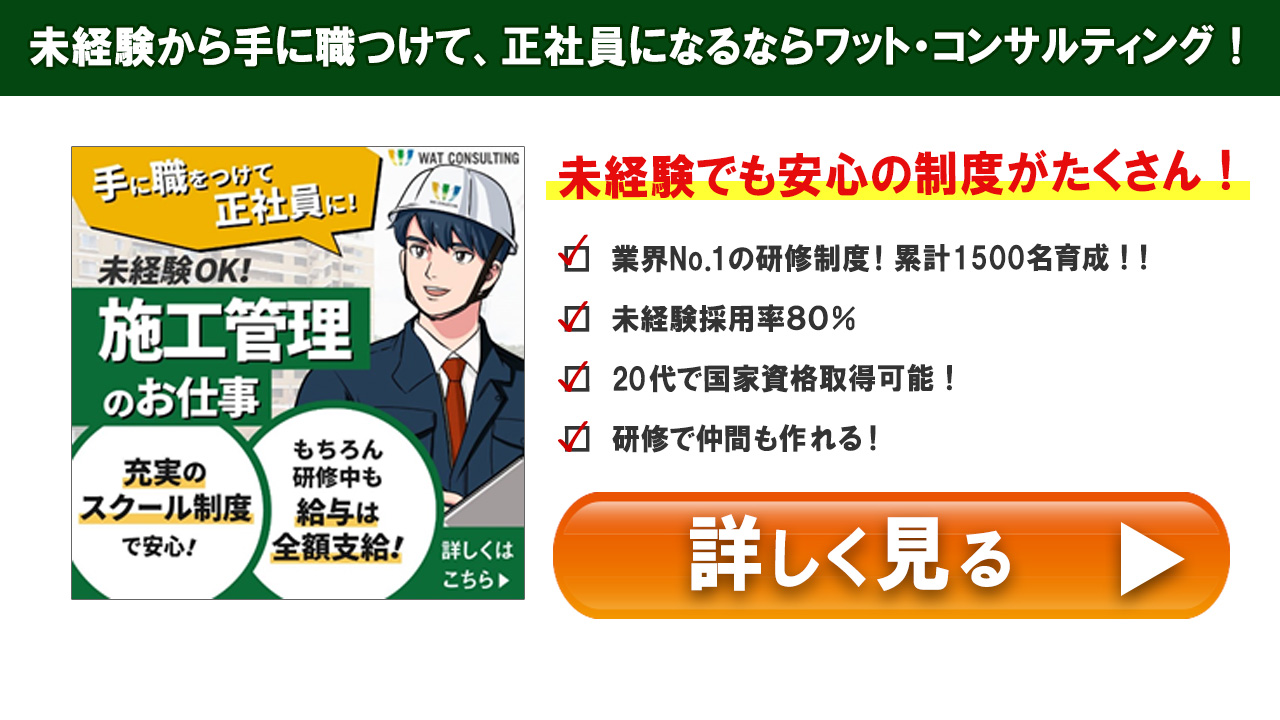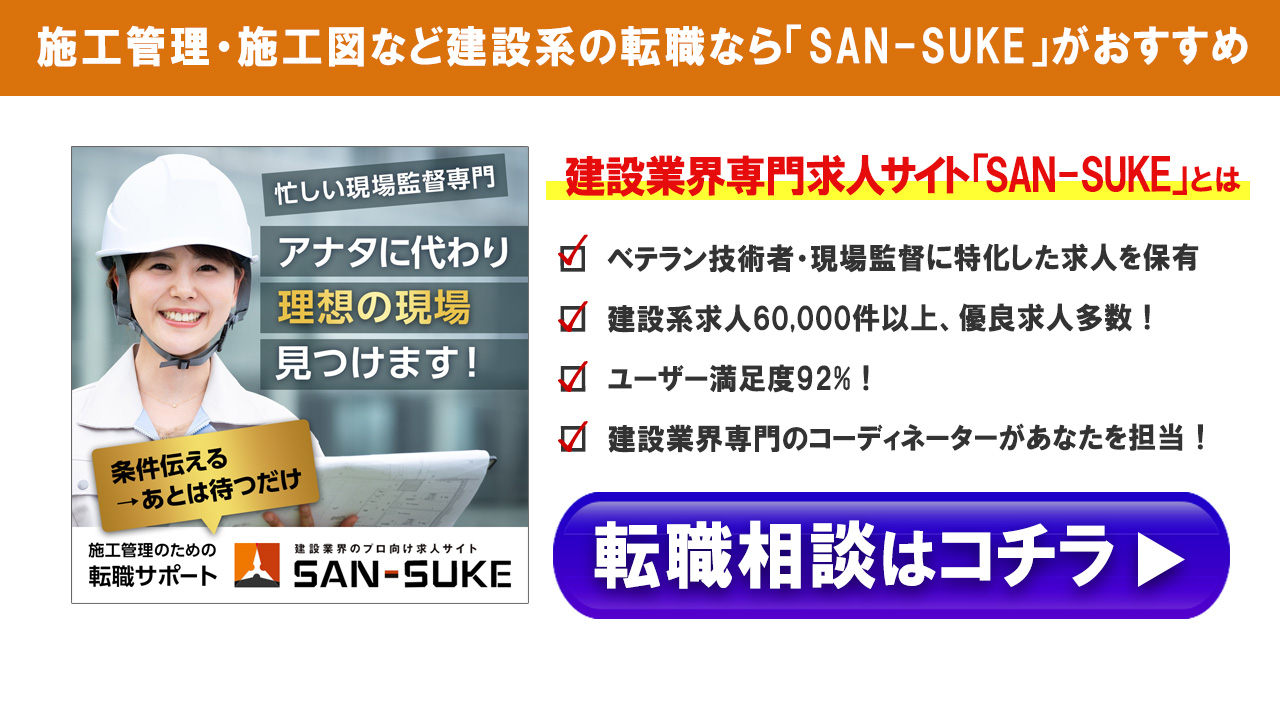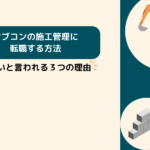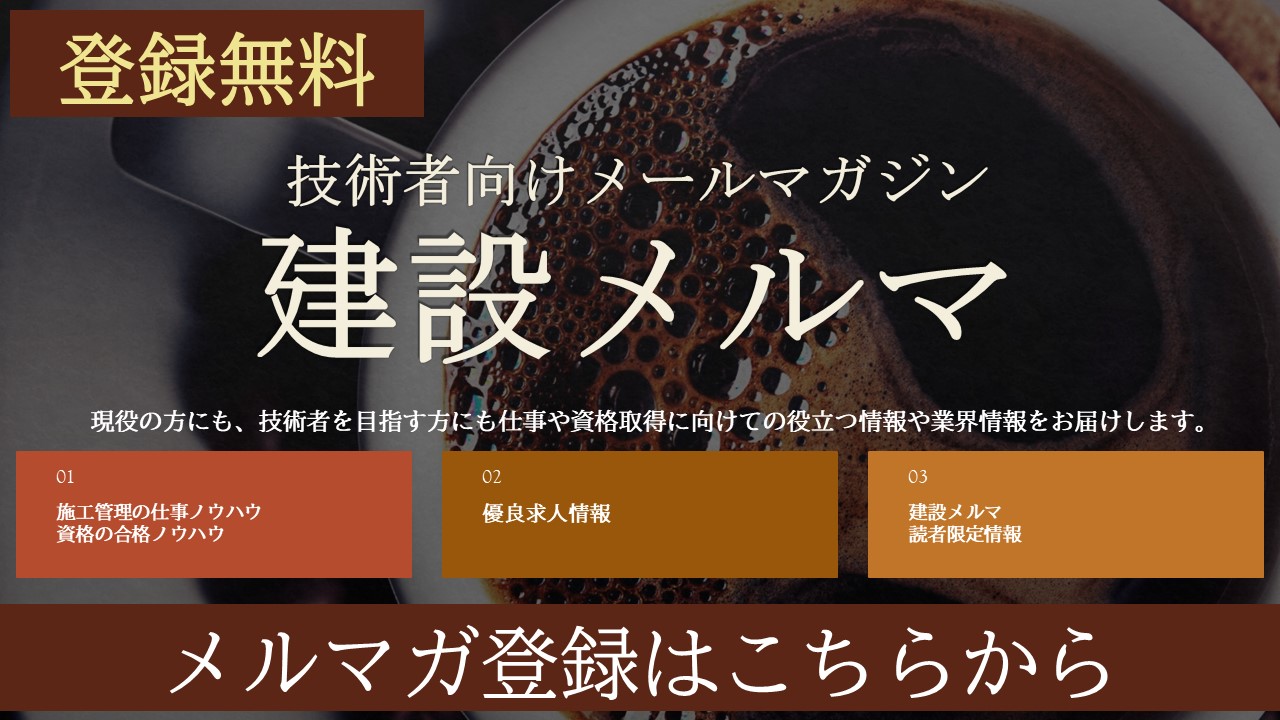「1級管工事施工管理技士の受験資格が緩和されたって本当?」
「自分も受験できるようになったのか、変更点を知りたい」
こういった疑問や悩みに答える記事です。
この記事でわかること
- 1級管工事施工管理技士の新しい受験資格の詳細・変更点
- 受験資格が緩和された背景
- 1級管工事施工管理技士を取得するメリット
私たちワット・コンサルティングは、管工事施工管理の技術者派遣を行っている会社です。未経験から管工事施工管理に就職・転職したい方を募集しています。
2024年度から1級管工事施工管理技士の受験資格が大幅に緩和され、多くの方に資格取得のチャンスが広がりました。
「でも、具体的に何がどう変わったの?」と思いますよね?
この記事では、1級管工事施工管理技士の新しい受験資格の詳細や変更点などを解説します。
記事を読めば、あなたが受験資格を満たしているかが明確になり、資格取得に向けて具体的な一歩を踏み出せるでしょう。
実務経験を積みながら1級管工事施工管理技士を目指せる企業
私たちワット・コンサルティングでは、管工事施工管理の未経験者を募集しています。
60日間の充実した研修で基礎からしっかり学べるため、実務経験がない方でも安心してキャリアをスタートできます。
研修後の定着率は83.2%と業界平均よりも高く、安心して長く働ける環境です。
「未経験から実務経験を積んで、1級管工事施工管理技士を目指したい」という方は、転職先の候補に入れてみてください。
目次
1級管工事施工管理技士の受験資格の緩和内容
2024年から、1級管工事施工管理技士の受験資格が大幅に緩和されました。詳細な変更内容は以下のとおりです。
出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受験資格が変わります
これまでは学歴や実務経験によって複雑に分かれていた要件がシンプルになり、受験しやすくなっています。
次で、新しくなった受験資格の具体的な内容を「第一次検定」「第二次検定」に分けて解説します。
これから1級管工事施工管理技士を目指す方は、受験資格を満たしているか確認してみてください。
第一次検定(学科)の受検要件
第一次検定は、受験する年度の末日時点で年齢が19歳以上であれば、学歴や実務経験を問わず誰でも受験可能になりました。
旧制度では大学の指定学科を卒業した場合でも3年以上の実務経験が必要でしたが、その要件が撤廃されています。
第一次検定の主な変更点
- 学科の要件が撤廃
- 19歳以上であれば誰でも受験可能
この変更により、例えば「大学在学中に第一次検定に合格し、卒業後すぐに第二次検定の準備を始める」といったキャリアプランも立てられます。
施工管理でのキャリアをすぐにスタートさせたい若手技術者にとって、大きなチャンスが訪れたと言えます。
第二次検定(実地)の受検要件
第二次検定の受験資格を得るには、第一次検定の合格が必要です。第一次検定の合格に加えて、以下の実務経験も必要となります。
| 第二次検定の受験資格 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 1級第一次検定合格後 | ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・監理技術者補佐の実務経験1年以上 ・上記以外の実務経験5年以上 |
| 2級管工事施工管理技士合格後 | ・特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上 ・実務経験5年以上 ※それぞれ1級第一次検定合格者に限る |
第二次検定の受験に必要な実務経験年数は、第一次検定に合格後、または2級管工事施工管理技士の合格後からの期間で算出されます。
特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事で、監理技術者や主任技術者の指導のもと、施工管理した実務経験を指します。
この経験を1年以上積むことで、第二次検定受験までの期間を最短3年に短縮可能です。
学歴を問わず実務経験を積むことで、受験資格を得られるようになったことが大きな変更点です。
1級管工事施工管理技士の受験資格が緩和された背景
1級管工事施工管理技士の受験資格が緩和された背景には、建設業界が抱える課題が関係しています。
受験資格が緩和された背景
- 深刻な技術者不足
- 技術者の高齢化対策
- DXに対応できる若手人材の不足
これらの課題は相互に関連しており、将来にわたって社会インフラを維持するために、技術検定制度の見直しが急務となりました。
それぞれの背景について、国の調査データを交えて解説します。
深刻な技術者不足
建設業界は慢性的に技術者が不足しています。
国土交通省の調査によると、就業者数のピークであった1992年の619万人に対し、2021年には485万人まで減少しています。
工事の品質や安全を管理できる技術者の確保は、建設業界の未来を左右する重要な課題です。
技術者不足の状況を改善し、1人でも多くの技術者を現場に迎えるために、実務経験がなくても第一次検定を受験できるようになりました。
技術者の高齢化対策
技術者の高齢化も、受験資格緩和の背景にある大きな要因です。
建設業界は高齢化が著しく、将来の担い手不足が懸念されています。
ご覧のように建設業は若年層の割合が低く、高齢層の割合が高いことがわかります。
10年後には現在60歳以上の技術者の多くが退職時期を迎えるため、技術やノウハウの継承が途絶えてしまう恐れがあります。
そこで、若いうちから資格取得を目指せるように、次世代の技術者を早期に育成できるよう制度を変更しました。
DXに対応できる若手人材の不足
建設業界では生産性向上のためにDXが積極的に推進されています。
しかし、最新技術やデジタルツールを使いこなせる若手人材が不足しているのが現状です。
ポイント
若手人材が不足する原因として、長時間労働の問題や「きつい・汚い・危険」の3Kのイメージが根強く残っていることが考えられます。
国は働き方改革や処遇改善を進めていますが、魅力ある産業へと転換するために、デジタル技術に明るい若者の力が必要です。
1級管工事施工管理技士の受験資格の緩和は、若者が建設業界へ入職しやすくするための働きかけです。
資格取得という明確な目標を提示することで、キャリアパスを描きやすくし、DX時代を担う人材の確保・定着を目指しています。
受験資格が緩和された1級管工事施工管理技士の情報
ここでは、1級管工事施工管理技士を受験するための基本情報を解説します。
1級管工事施工管理技士の基本情報
- 受験料
- 認められる工事種別・工事内容
- 指導監督的実務経験の定義
- 実務経験に該当しない作業例
1級管工事施工管理技士の受験を検討している方は、参考にしてみてください。
受験料
1級管工事施工管理技士の受験料は、第一次検定・第二次検定ともに12,700円(非課税)です。
参考:一般財団法人 全国建設研修センター|1級管工事施工管理技術検定
認められる工事種別・工事内容
実務経験として認められるのは、建設業法で定められた管工事に該当するものです。例えば、以下の施工管理経験が対象となります。
実務経験となる管工事の例
- 冷暖房設備工事
- 空気調和設備工事
- 給湯設備工事
- 衛生器具設備工事
- ガス管配管工事
これらの工事において、施工計画の作成や安全管理などに従事した経験が実務経験としてカウントされます。
自身の経歴がどの工事に該当するか、事前に確認しておきましょう。
指導監督的実務経験の定義
指導監督的実務経験とは、工事現場において部下や下請業者に技術的な指導・監督した経験を指します。
旧受験資格で第二次検定を受験する場合、この経験が1年以上必要です。
具体的には、以下いずれかの立場で工事の技術面を総合的に指導した経験が該当します。
必要な指導経験の例
- 現場代理人
- 主任技術者
- 工事主任
- 施工監督
- 設計監理者
この経験は、ただ現場にいるだけで認められるものではありません。
施工計画に基づいて品質や安全、工程などを管理して指導的な役割を果たした実績が求められます。
実務経験に該当しない作業例
管工事に関連する業務でも、施工管理に直接関与しない作業は実務経験として認められません。
実務経験に該当しない作業の例
- 保守や点検修理などの業務
- 事務や総務などの管理部門での業務
- 単純な労務作業や作業員としての経験
これらの業務は施工管理とは異なる専門性が求められるため、実務経験の対象外です。
あくまで建設工事現場での「施工管理」に関する経験が評価の対象です。
受験資格が緩和された1級管工事施工管理技士の合格率・難易度
受験資格は緩和されましたが、試験の難易度が大幅に下がったわけではありません。
合格するためには試験形式を理解し、適切な対策を立てることが大切です。
1級管工事施工管理技士の合格率と難易度
- 試験形式と出題範囲
- 合格基準と合格率の推移
第一次検定は幅広い知識が問われ、第二次検定は実践的な応用力が試されます。
過去の合格率の推移から、試験の傾向を見ていきましょう。
試験形式と出題範囲
1級管工事施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定で構成されています。
それぞれの形式と主な出題範囲は、以下のとおりです。
| 試験の種類 | 形式 | 出題範囲 |
|---|---|---|
| 第一次検定 | 四肢択一のマークシート方式 | 機械工学等・施工管理法・法規から出題 |
| 第二次検定 | 記述式 | 施工管理の経験記述・ネットワーク工程表の作成など |
第一次検定は知識のインプット、第二次検定は知識を応用して文章で伝えるアウトプットの対策が中心となります。
特に、第二次検定の経験記述は合否を分けるポイントです。
合格基準と合格率の推移
合格基準は第一次・第二次検定ともに「得点60%以上」です。
ただし、第一次検定は全体の得点に加えて「施工管理法」の科目で50%以上の得点が必要になる場合があります。
近年の合格率の推移は、以下のとおりです。
| 年度 | 第一次検定 | 第二次検定 |
|---|---|---|
| 令和2年度 | 35% | 61% |
| 令和3年度 | 24% | 73.3% |
| 令和4年度 | 42.9% | 57.0% |
| 令和5年度 | 37.5% | 62.1% |
| 令和6年度 | 52.3% | 76.2% |
参考:KGKC 建設技術教育センター|1級管工事施工管理技士:受験者数・合格率動向
受験資格が緩和された令和6年度は受験者が大幅に増加し、合格率も52.3%と上昇しました。
第二次検定は実務経験を積んだ技術者が受験するため、第一次検定と比べて高い合格率で安定しています。
1級管工事施工管理技士を取得するメリット
1級管工事施工管理技士を取得すると、以下のメリットがあります。
資格取得の主なメリット
- 監理技術者・主任技術者へのキャリアアップ
- 報奨金・資格手当が付与される可能性がある
- 年収アップ・転職市場での評価が上がる
1級管工事施工管理技士は技術者としての市場価値を大きく高め、キャリアアップにつながります。
それぞれのメリットを1つずつ見ていきましょう。
監理技術者・主任技術者へのキャリアアップ
1級管工事施工管理技士を取得すると、建設業法で定められた「主任技術者」および「監理技術者」として認められます。
これにより、担当できる工事の規模が格段に大きくなります。
| 役職 | 役割と配置が必要な工事 |
|---|---|
| 主任技術者 | すべての建設工事現場に必要な技術者 |
| 監理技術者 | 元請として総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を結ぶ大規模工事で必要な技術者 |
大規模なインフラ工事や大型施設の建設プロジェクトで、全体の技術指導を担う重要なポジションに就けます。
報奨金・資格手当が付与される可能性がある
多くの企業では、従業員のスキルアップを支援するために資格手当制度を設けています。
1級管工事施工管理技士のような難関資格は、より高く評価される傾向にあります。
手当の目安
- 資格手当: 8,000~30,000円程度(毎月)
- 合格報奨金: 50,000~150,000円程度(一時金)
毎月の給与に手当が上乗せされるため、着実な収入アップにつながります。
年収アップ・転職市場での評価が上がる
1級管工事施工管理技士の資格は、年収アップとキャリアの選択肢拡大に直結します。
資格をもつ技術者の平均年収は、無資格者や2級資格保持者に比べて、高い水準にあります。
ポイント
特に、大手企業や大規模プロジェクトを扱う企業の場合、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
資格があることで、企業は経営事項審査で加点されたり大規模な公共工事を受注できたりするため、有資格者を好条件で迎え入れようとします。
そのため、より待遇の良い企業への転職や有利な条件でキャリア交渉ができます。
ワット・コンサルティングは無資格×未経験でも応募できる
私たちワット・コンサルティングでは、資格や経験がない方でも管工事施工管理に挑戦できる体制を整えています。
業界トップクラスの「60日間の新人研修」を実施しており、施工管理の基礎を一から学べます。
これまでに累計1,500名以上の未経験者を育成してきた実績とノウハウがあるため、安心してキャリアをスタートできるのが強みです。
ワット・コンサルティングの強み
- 未経験採用率80%以上
- 定着率83.2%(業界平均は約70%)
- 資格取得支援制度が充実
- 年間休日125日&平均残業31.7時間/月
資格取得を全面的にバックアップする制度も整っているので、働きながら1級管工事施工管理技士を目指せます。
1級管工事施工管理技士の効率的な勉強法
1級管工事施工管理技士の合格を目指すには、効率的に勉強できるかが重要です。
あなたに合う学習スタイルを見つけ、計画的に勉強を進めていきましょう。
1級管工事施工管理技士の効率的な勉強法
- 公式テキスト+過去問題集で勉強する
- eラーニングを活用して勉強する
- 隙間時間にアプリを活用して勉強する
それぞれの勉強法を1つずつ解説します。
公式テキスト+過去問題集で勉強する
王道かつ基本的な勉強法は、市販のテキストと過去問題集をくりかえし学習することです。
試験の全体像を把握し、出題傾向をつかむ上で欠かせないプロセスと言えます。
基本的な学習の流れ
- テキストを通読して試験範囲の全体像を把握する
- 過去問題集を最低でも5年分、3回以上くりかえし解く
- 間違えた問題はテキストに戻り、周辺知識も含めて復習する
このステップで学習を進めることで、効率的に知識が定着して解答のスピードと正確性が向上します。
特に、類似問題がくりかえし出題される第一次検定において、過去問演習は有効な対策です。
eラーニングを活用して勉強する
独学での学習に不安がある方や要点を効率的に学びたい方には、eラーニングの活用が適しています。
専門講師によるわかりやすい解説で、複雑な内容もスムーズに理解できます。
eラーニングのメリット
- 体系的なカリキュラムで学べる
- 図や映像を使った講義で理解が深まる
- 進捗管理機能でモチベーションを維持しやすい
- スマートフォンやPCでいつでもどこでも学習できる
専門学校への通学に比べて費用を抑えられ、時間や場所の制約を受けないのがeラーニングの強みです。
隙間時間にアプリを活用して勉強する
通勤時間や昼休みなどの隙間時間を有効活用するには、アプリでの学習がおすすめです。
机に向かうまとまった時間が取れなくても、コツコツと学習を積み重ねられます。
ポイント
多くの試験対策アプリは、一問一答形式で過去問題を手軽に演習できて便利です。
間違えた問題だけを自動で出題してくれる機能もあり、苦手分野の克服に役立ちます。
テキストやeラーニングでの学習をメインとしながら、補助的なツールとしてアプリを併用すると、より学習効果を高めることが可能です。
おすすめのアプリは、1級2級管工事施工管理技士の試験勉強におすすめのアプリ16選で確認できます。
1級管工事施工管理技士についてよくある質問
最後に、1級管工事施工管理技士についてよくある質問にお答えします。
未経験でも1級管工事施工管理技士を受験できるの?
制度改正により、第一次検定に限り実務経験がなくても受験できるようになりました。
受験する年度の末日時点で19歳以上であれば、誰でも第一次検定を受験できます。
ポイント
ただし、1級管工事施工管理技士の資格を取得するには、第二次検定の合格も必要です。
第二次検定を受験するには、第一次検定合格後に3〜5年の実務経験を積まなくてはなりません。
未経験から資格取得を目指す場合、まずは第一次検定に合格し「技士補」の資格を得て、実務経験を積むのが一般的なルートです。
指定学科以外の卒業でも受験できるの?
指定学科以外の卒業生でも問題なく受験できます。
旧制度では、指定学科卒かそれ以外かで必要な実務経験年数に大きな差がありました。
ポイント
しかし、新制度では学歴による区分が緩和され、第一次検定合格後の実務経験年数で評価されるようになっています。
文系学部や普通科高校の卒業生であっても、管工事の現場で定められた期間の実務経験を積めば、第二次検定の受験資格を得られます。
実務経験が不足している場合はどうすればいい?
実務経験が不足している方は、まず第一次検定に合格することを目指しましょう。
前述のとおり、第一次検定は実務経験なしで受験できます。
| 実務経験が不足している場合のステップ | 概要 |
|---|---|
| 1.第一次検定に合格する | 第一次検定に合格して技士補の資格を取得する |
| 2.就職・転職する | 技士補の資格をアピールして管工事を行う建設会社に就職し、実務経験をスタートする |
| 3.実務経験を積む | 現場で3年~5年の経験を積み、第二次検定の受験資格を満たす |
| 4.第二次検定を受験する | 実務経験を武器に第二次検定に挑戦する |
この手順を踏むことで、未経験からでも計画的に1級管工事施工管理技士の資格取得を目指せます。
資格取得支援制度が整っている企業を選ぶと、働きながらスムーズに学習を進められるでしょう。
参考記事:実務経験なしで2級管工事施工管理技士を目指せる|受験資格から合格のコツまで解説
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
この記事のまとめ
- 受験資格の緩和により第一次検定は19歳以上なら誰でも受験可能
- 第二次検定は第一次検定合格後の実務経験次第で受験可能
- 1級管工事施工管理技士を取得すると大幅な年収アップが可能
受験資格の緩和は、施工管理としてのキャリアを考えている方にとって大きなチャンスです。
あなたに合う勉強法を見つけ、計画的に資格取得を目指しましょう。
くりかえしですが、私たちワット・コンサルティングでは未経験から管工事施工管理に挑戦したい方を募集しています。
Web資格講座やeラーニングを完備しており、働きながら効率的に学習を進めることが可能です。
資格取得奨励金制度もあるため、費用面の心配なくキャリアアップに集中できます。
ワット・コンサルティングの強み
- 定着率83.2%(業界平均は約70%)
- 60日間の充実した研修制度で未経験者をサポート
- 資格取得支援制度(eラーニング、奨励金など)が充実
- 年間休日125日、平均残業31.7時間/月で働きやすい
「まずは実務経験を積みたい」「働きながら資格を取得したい」という方は、転職先の候補に入れてみてください。
あなたの資格取得に向けた挑戦の参考になれば幸いです。