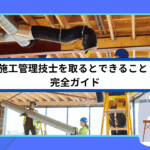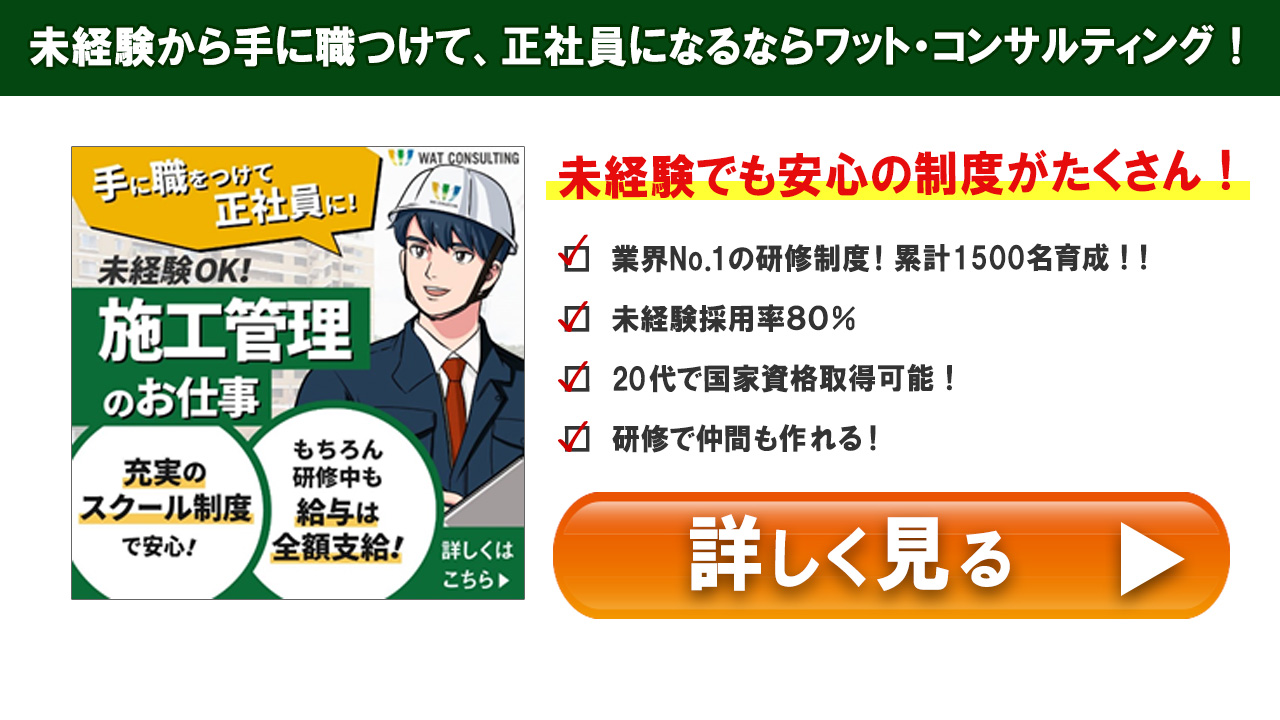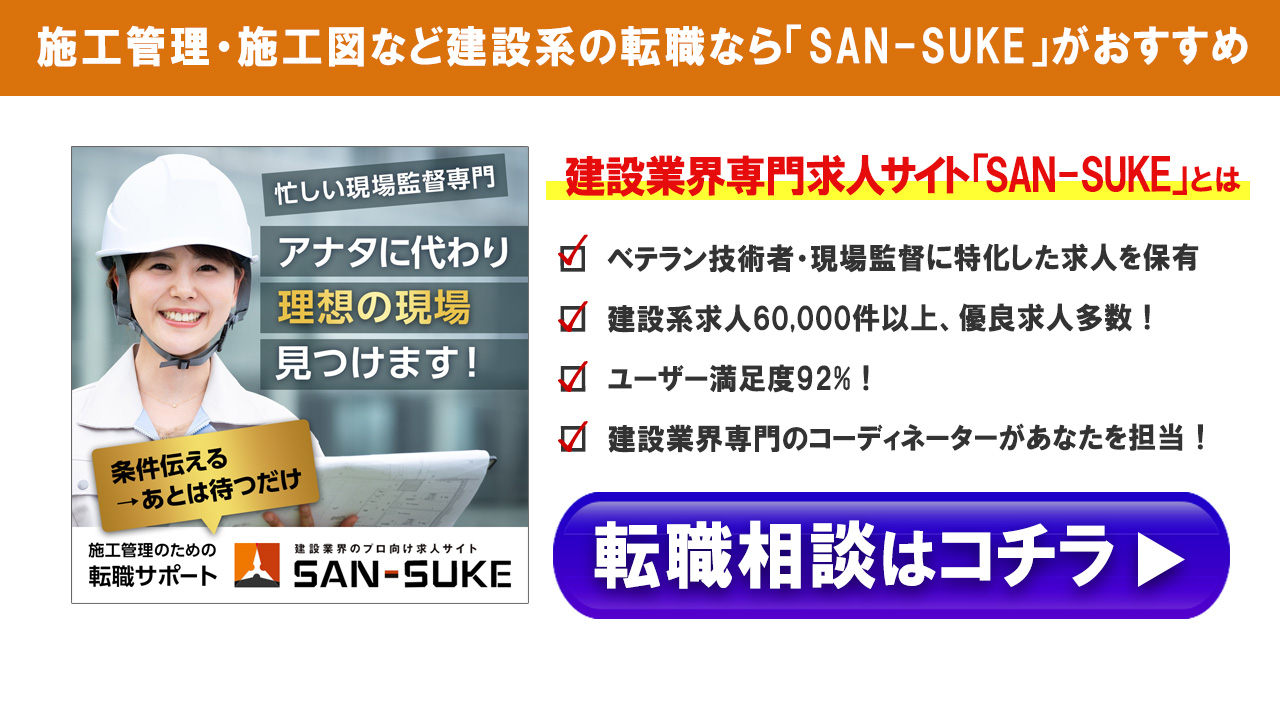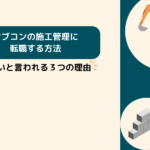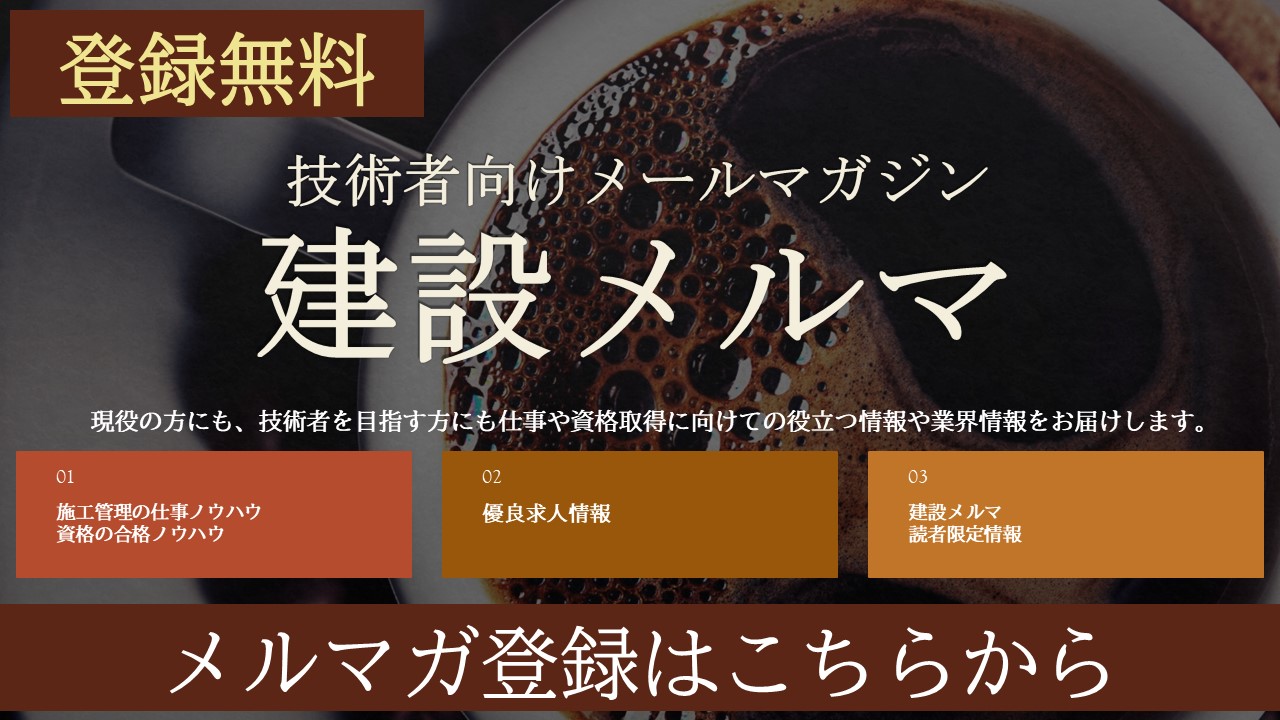電気工事にAIを導入すると、図面の読み取りや工程管理、見積などの作業が効率化され、ミスや無駄も減らせます。
AIは複雑な条件を一瞬で分析し、人手不足やベテラン不在への対策にもつながりやすいです。
現場のリアルな実情として、紙の図面や手書きの作業指示が煩雑に感じる場面は多いですよね?
この記事では、AIを活用する7つの方法と導入時の注意点をまとめています。
効率面の改善だけでなく、安全管理や施工品質の底上げにもヒントを得られるでしょう。
さっそく内容をチェックして、電気工事の現場をスムーズに進める第一歩を踏み出してみてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣を行う会社で、施工管理の転職サポートも実施しています。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号

目次
電気工事業務にAIを活用する7つの方法
電気工事業務にAIを活用する方法を紹介していきます。
電気工事業務にAIを活用する方法
- 図面やマニュアルの解析
- 施工計画や工程管理のサポート
- 見積もり作成
- 適切な人員配置や資材手配
- 施工ミスやトラブルの事前検知
- データの蓄積・分析で施工品質の向上
- 画像認識を用いた施工検査のサポート
AI活用の参考にしてみてください。
図面やマニュアルの解析
現場作業に入る前に、必ず設計図面や施工マニュアルを確認する必要があります。
紙の図面を人の目で見ながら、どこにどんな部材を付けるか確認するのは時間がかかりますし、見落としのリスクもあります。
そこでAIを使うと、手間とミスを大幅に減らしやすいです。
以下はAIができることの例です。
| AIの例 | 概要 |
|---|---|
| 文字認識(OCR) | スキャンした図面の文字や記号を読み取り、必要な情報をピックアップする |
| 画像解析 | 図面上のコンセントやスイッチなどのマークを自動で見つけ、一覧にまとめる |
| 文章解析 | マニュアルに書かれた膨大な説明文から、特定のキーワードが含まれる章だけを瞬時に検索する |
例えば「照明器具がどこに何個あるのか」をAIで調べられるようにしておけば、手計算で数えるよりも速く、数え間違いも起こりにくくなります。
施工手順書もAIに読ませておけば「屋外配線の防水対策」に関する手順だけをピンポイントで取り出すことが可能です。
慣れれば「図面やマニュアルを開いて探す」という時間を大きく削減できるでしょう。
以下は活用できるAIツールの具体例です。
| AIツール | 概要 |
|---|---|
| BIM(Building Information Modeling) | BIMは建物を3Dモデルで扱う技術です。AIを組み合わせると、PDFや画像の図面から壁や部屋を自動で判定し、短時間で3D化しやすくなります。 |
| 図面解析AIソフトウェア | CADやPDFの図面を読み込み、コンセントや壁などのシンボルを自動認識し、数量や位置を一覧で出す仕組みです。「拾いの匠AI」などの国内製品も増えています。 |
| AI-OCRツール | AI-OCRは文字を読み取る技術です。活字だけでなく手書きも高精度で判別し、見積書や図面の内容を素早くデータ化できます。 |
| 自然言語処理・チャットボット | 文章を理解する仕組みを使い、社内マニュアルやFAQをまとめて検索できます。チャットボットが質問に答えてくれるため、施工手順の確認が簡単になります。 |
施工計画や工程管理のサポート
電気工事は設備や内装など他の工事と並行して進むことが多いです。
そのため「いつ、どの工事が入るか」を調整するのは負担となるでしょう。
AIが入ると、これまで人の頭や経験で考えていた複雑なスケジュール調整をサポートしてくれます。
例えば以下のような場面があります。
| 目的 | AIを使うメリット |
|---|---|
| 工期を短くする | 人数や作業時間帯を変えた場合のプランをAIが複数パターン一瞬で作り出し、最も効率が良い計画を提案 |
| 他工種とぶつからないようにする | 電気工事の配線が終わらないうちに、クロス(壁紙)の工事が始まってしまう…などのトラブルを未然に防ぐ |
IoTセンサーやカメラを使って現場状況をリアルタイムでAIが見ていれば「ここが予定より遅れている」と警告を出してくれることもあります。
こうした機能を導入すると、監督者や管理担当者は全体を見渡しながら的確な指示を出しやすくなり、工事の遅れやムダを大幅に減らすことが期待できます。
以下は活用できるAIツールの具体例です。
| AIツール | 概要 |
|---|---|
| BIM連携の施工計画システム | BIMモデルとAIが連動し、工事の段取りや干渉を自動で見える化します。資材や工程を一元管理し、変更が出てもスムーズに再調整できます。 |
| AI搭載のプロジェクト管理・スケジューリングツール | 入力した条件をもとに、AIが複数の工程プランを一瞬で作成します。遅延リスクやコスト案も比較でき、最適な進め方を探しやすいです。 |
| IoT連携の現場管理システム | カメラやセンサーの映像をAIが解析し、進捗や出来高を自動判定します。少しのズレも早期発見でき、現場の段取りや安全管理を強化しやすいです。 |
| 資材管理・物流最適化ツール | 置き場の写真などをAIが解析し、必要量と搬入時期を自動予測します。余剰在庫や資材待ちを減らし、電気工事の工程停滞リスクを抑えやすくなります。 |
見積もり作成
電気工事の見積もりでは「照明器具の数」「コンセントの数」「使用するケーブルの長さ」など、図面から細かい情報を拾い出して計算する作業が必要です。
これも人の手でやると時間がかかり、数え漏れや二重計上が起きるリスクもあります。
AIを使った場合、まずは図面をスキャンして、文字や記号を読み取ります。
続いて、どんな部材がいくつ必要かを自動計算し、過去の実績データなどをもとにだいたいの単価を当てはめることが可能です。
担当者は現場ごとの事情に合わせて少し補正をかけるだけで、見積書のベースができるイメージです。
例えば、以下のように手順を進めます。
| 手順 | 概要 |
|---|---|
| 図面のスキャン | 紙の図面をPDFにしてAIにアップロード |
| 部材の抽出 | 画像解析で配電盤、照明、コンセントなどのシンボルを自動的に数える |
| 単価の適用 | 過去のデータや標準リストから、適切な単価を算出 |
| 最終チェック | 人が「夜間追加費用」「特殊形状の部材」などを微調整 |
この流れが定着すると、見積もりのスピードが早くなるだけでなく、精度のばらつきも減らせます。
電気工事の積算に慣れていないスタッフでも、AIの後押しで作業しやすくなるメリットもあるでしょう。
以下は活用できるAIツールの具体例です。
| AIツール | 概要 |
|---|---|
| OCR・画像認識 | 紙の図面やPDFを読み取り、数字やシンボルを自動で抽出します。配線や部材の拾い出しが短時間で行え、初心者でも扱いやすいです。 |
| 自然言語処理(NLP) | 文章をAIが理解・分類し、見積明細や資材名の表記ゆれを統一します。書類間の抜け漏れチェックにも役立ちます。 |
| ルールベースAI・専門知識の埋め込み | 社内ルールや標準計算式を登録し、部材や面積から自動で数量を見積もります。過去の経験則までAIに組み込める点が魅力です。 |
| 機械学習(ML) | 大量の過去データをAIが学習し、工事コストや工数を予測します。将来の資材価格やリスクも加味して、見積の精度を高めます。 |
| 生成AI(大規模言語モデル) | ChatGPTのようなAIが、過去の見積事例を基に新しい見積書を下書きします。担当者は最終チェックだけで済むので、大幅に手間を省きやすいです。 |
適切な人員配置や資材手配
電気工事現場では「せっかく熟練工を呼んだのに、別の作業が詰まっていて手待ちが多い」といったミスマッチが起こることもあるでしょう。
AIは工程表と連携しながら、どのタイミングでどのスキルをもつ作業者を投入すれば効率的か計算が可能です。
資格が必要な高圧受電設備や特殊工具を扱う作業など、専門性が高い場面ほどAIの活躍が期待できます。
さらに、資材についても「いつどのくらい発注すればいいか」を予測できます。
工事が始まってから「ケーブルが足りない」となってしまうと待機時間が発生してもったいないですし、逆に大量に仕入れ過ぎると保管スペースを圧迫してしまうでしょう。
AIは施工進捗や過去の発注履歴から最適な数を予測し、在庫を切らさず無駄も減らしてくれます。
人員と資材がかみ合えば、余計な手待ちや余剰在庫が削減され、トラブルの発生率が下がるでしょう。
経験者がいないと調整が難しかった現場運営が、より客観的な判断で円滑に進むようになります。
以下は活用できるAIツールの具体例です。
| AIツール | 概要 |
|---|---|
| 施工計画・スケジュール最適化ツール | AIが複数の工程案を瞬時に作成し、工期短縮やコスト削減を支援します。既存システムとも連携でき、電気工事の人員配置にも役立ちます。 |
| 資材発注・在庫管理のAIソリューション | 建設スケジュールに合わせ、AIが必要な資材を先読みし自動発注します。余剰在庫を減らし、納期遅れも防ぎやすくなります。 |
| フィールドサービス向けAI支援 | 設備点検や小規模工事などの依頼をAIが自動で割り振りし、スタッフの空き状況や技能に合わせた最適な派遣を行います。 |
施工ミスやトラブルの事前検知
配線の誤接続や取り付け位置の間違いなど、電気工事のちょっとしたミスは、後で気づくと大きなやり直しになりがちです。
AIを使えば、作業途中からでも施工の状態をチェックし、問題があればアラートを出す仕組みが作れます。
例えば、以下のような方法があります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| ケーブル番号の自動チェック | 撮影したケーブルの表示番号をAIが読み取って、図面の接続表と一致するかを照合する。 |
| 設備センサーの監視 | 分電盤や変圧器、配線の温度や電流を常に測定し、通常より高い数値が出たら「配線に異常があるかも」と通知。 |
こうした仕組みなら、施工ミスが起きてもごく早い段階で発見でき、工事全体に影響が広がる前に修正が可能です。
また、施工ミスによる火災や感電などの重大事故を防ぐ上でも非常に有効です。
AIが補助してくれるおかげで、現場担当者の見落としや疲労によるヒューマンエラーを減らせるでしょう。
以下は活用できるAIツールの具体例です。
| AIツール | 概要 |
|---|---|
| 品質管理AIシステム | 現場写真をAIが解析し、仕上がり不良や配線ミスを検出します。検査漏れを抑え、電気工事の品質を高めやすいです。 |
| 異常検知・予知保全システム | 電流や温度をAIが常時監視し、わずかな変化でもアラートを出します。機器の故障を早めに察知でき、保守コストも低減しやすいです。 |
| 施工管理AIツール | 写真やスケジュールをAIが照合し、進捗状況や施工ミスを自動で可視化します。遅れや手戻りを早期に発見でき、工程管理を楽にできます。 |
| BIM+AI設計支援ツール | BIMモデルとAIが連動して、設計段階から配線や回路をチェックします。ベテランのノウハウを取り込み、初期で設計ミスを防ぎやすいです。 |
データの蓄積・分析で施工品質の向上
AIを効果的に活用するには、現場から出てくる情報をこまめにデジタル化して残す習慣づくりが大切です。
例えば「施工前・施工中・施工後の写真」「作業員数や使用部材」「トラブル報告やクレームの内容」などを、社内システムやクラウドに蓄積しておきます。
| データの種類 | 分析で見たいポイント |
|---|---|
| 施工写真 | 作業ミスや仕上がり品質のばらつき |
| 作業時間・工数 | 遅延や人員ロスが起きやすい工程の特定 |
| 発注・在庫の履歴 | 資材不足や過剰発注が出るタイミングの傾向 |
| 過去の不具合事例 | どの部材や箇所に問題が集中しているか |
AIはこれらのデータから「雨天が続くとトラブルが増える」「作業が深夜に集中するとミス率が上がる」など、通常は見つけにくいパターンを明らかにしやすいです。
そこから得られる知見をもとに、施工手順や計画の組み方を改善し、品質を徐々に高められます。
蓄積されたノウハウは将来の現場にも応用できるため、組織としてのスキルアップにもつながるでしょう。
画像認識を用いた施工検査のサポート
施工が進んでいくときには、目視によるチェックが欠かせません。
ただし、建物全体をくまなく確認するのは時間も手間もかかるうえ、慣れない作業者の場合は見落としが増えることもあります。
画像認識のAIを使うと、写真や動画から「図面と違う場所に機器が取り付けられている」「ケーブルの配色が指定と異なる」といった点を自動で指摘できます。
具体的には以下のような流れです。
AIによる画像認識の流れ
- ヘルメットの小型カメラやスマホやタブレットで現場を撮影
- その画像データをクラウド上のAIにアップロード
- AIが図面やBIMモデルを参照して指摘をリスト化
- 指摘された箇所を人間が再チェック・修正する
ドローンなどを使えば、高所や床下のように人が入りにくい場所の点検も画像認識で行えるようになります。
検査に要する時間を節約しながら、抜け漏れも防ぎやすくなるので、工期短縮と品質アップを両立できるのがメリットです。
こうした流れを一度作れば、検査書類の作成や写真の整理なども含め、日々の業務負担が減っていく可能性があります。
担当者が把握できる情報量が増える分、完成後のクレームや追加工事のリスクを減らせるでしょう。

電気工事業務にAIを導入する際の注意点
AIを導入する場面ではメリットが期待できる一方で、以下のような注意点があります。
電気工事業務にAIを導入する際の注意点
- 品質の高いデータをAIに学習させる
- 人間によるチェックを怠らない
- AIを使った業務のトレーニングを実施する
こちらもAIを導入する際の参考にしてみてください。
品質の高いデータをAIに学習させる
AIの精度は、学習に用いる情報の信ぴょう性に左右されやすいです。
入力ミスや記録漏れのあるデータを与えると、間違った結果が出たり、施工計画や見積作成でズレが起こりやすくなります。
例
図面のスキャン精度が低かったり、過去の施工履歴が抜けたままだと、AIが誤った傾向を学習してしまうかもしれません。
品質を保つには、データを一元管理できるプラットフォームを用意する方法が有用です。
社内の担当が施工完了後に写真や数量を同じフォーマットで登録し、間違いに気づいたらすぐ訂正する流れを徹底しましょう。
さらに、定期的な棚卸しのタイミングで、図面や施工報告が正しく揃っているかをチェックするとより安心です。
データ品質を高めるための手段
- 統一した形式で写真や数値を登録
- 定期的に棚卸しして抜けを早期発見
- 不備を発見した段階で即修正できる運用フロー
こうした取り組みを積み重ねると、AIに渡すデータが安定し、見積や工程管理の精度が期待どおりに向上しやすくなります。
人間によるチェックを怠らない
どれほど優れたAIでも、すべての場面で完全な判定を示すとは限りません。
特に電気工事では想定外の配線経路や機器の組み合わせが出てくることもあり、AIが学習していないケースに遭遇する可能性が考えられます。
センサーで異常を検知しなかったとしても、本当に安全とは限らない場面があるため、人が目視で確認する作業が欠かせません。
例
古い建物の改修現場では、図面と実際の配線が一致しない事例が起きやすく、AIが混乱する可能性があります。
監督やベテラン作業員が図面との誤差を把握し、AIの結果を確認するとトラブルを避けやすいです。
さらに、緊急時に「どこが配電の基点か」を即座に判断できるのは、AIより現場経験のある人間の場合が多いです。
AIだけに頼りすぎない工夫
- ベテラン技術者が現地で配線状態を逐次確認
- 定期的に作業ミーティングを開いて機械判定を再検証
- 不明点があれば必ず試験やテスターで追加チェック
人が最終責任を担う態勢を維持すれば、AIと協力しながら安全かつ効率の良い施工を進めやすくなります。
AIを使った業務のトレーニングを実施する
多機能なAIツールを導入しても、現場の担当者がAIツールの使い方を理解していないと、効果を発揮しにくいです。
電気工事に長く携わる人ほど紙の図面や従来型の工法に慣れているかもしれず、新しいIT操作への抵抗を覚える場合も考えられます。
そこで早い段階で簡単な研修や勉強会を開き、AI活用の流れを知ってもらう機会を整えるのが賢明です。
例
月に一度の朝礼や安全会議の時間を使い、タブレットやパソコンでAIを操作するデモを実施するのも有効です。
最初は見積の計算や写真のアップロードなど、工程がシンプルなものから始めると抵抗感を抱きにくいです。
経験の浅い作業員とベテランが一緒に触れてみると、得意分野や苦手分野がはっきりし、互いに補い合う土台ができます。
以下はAIレーニング計画の例です。
| 期間 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1週目 | AI概要説明・画面操作体験 | 初心者が仕組みをイメージしやすい |
| 2〜4週目 | 簡単な見積や写真解析 | 実務と結びつけて慣れていく |
| 5週目〜 | 応用機能の検証・共有 | 部署全体でノウハウを蓄積 |
業務トレーニングを段階的に進めれば、急なシステム変更が心理的負担になりにくく、社内のメンバーでAIを使いこなしやすくなるでしょう。
まとめ
電気工事でAIを導入すると、図面やマニュアルの解析から施工計画の最適化、見積の効率化、適切な人員配置や資材手配、トラブルの事前検知、データ分析を通じた施工品質向上、画像認識による検査支援まで幅広く活用できます。
一方で、入力データの整合性や人間による最終確認、段階的な研修を行う工夫が必要です。
上手に取り入れることで、工事全体の生産性を高めながら安全性や精度を保ち、電気工事現場の働き方を変える可能性があるため、導入を検討してみてください。