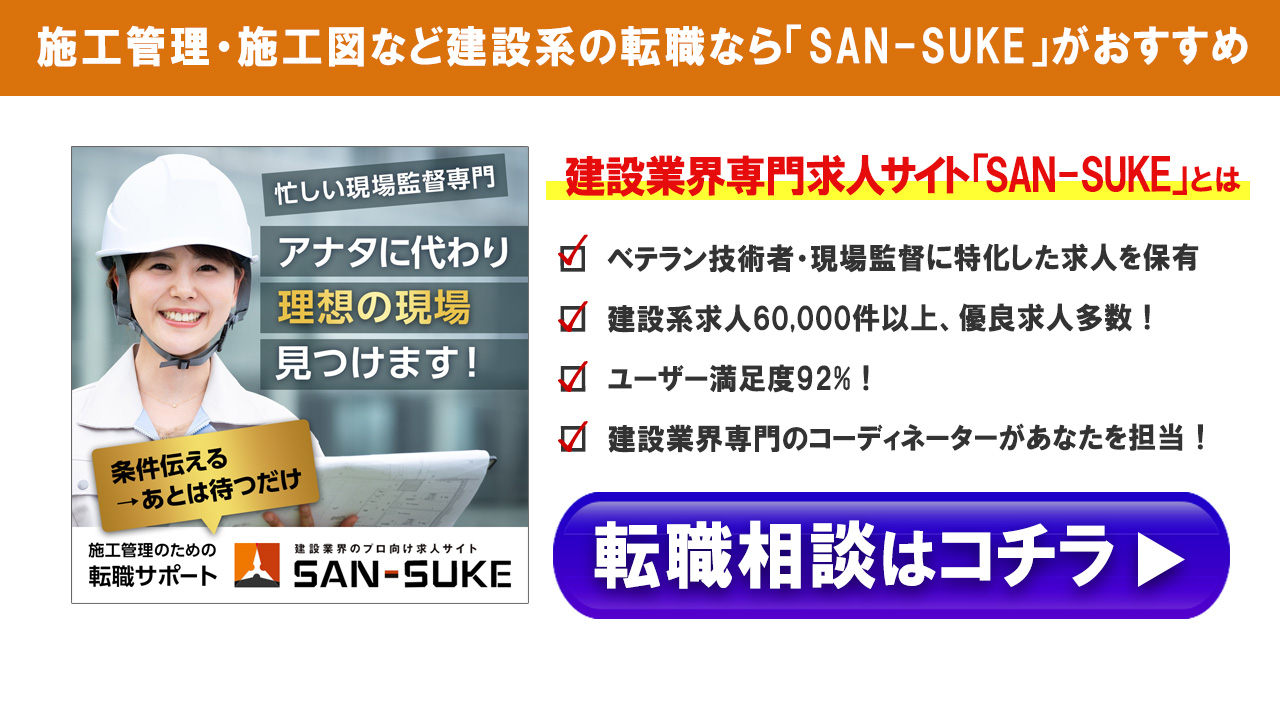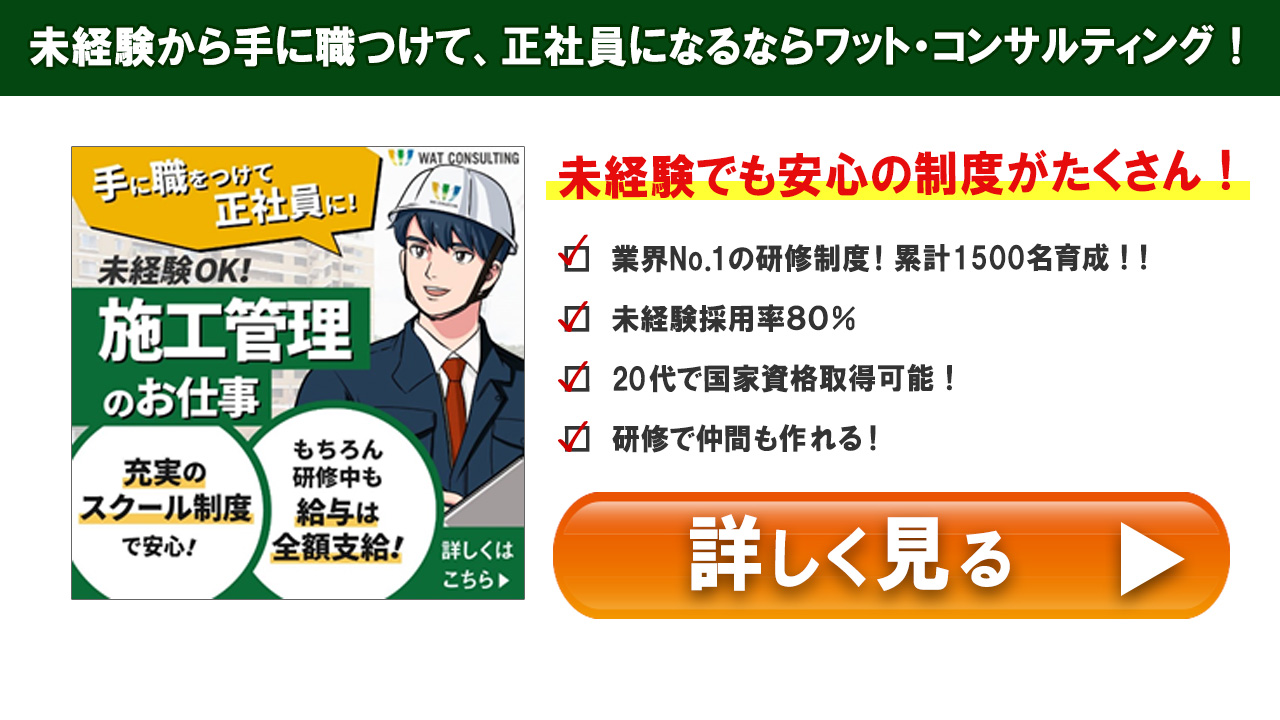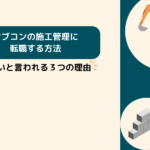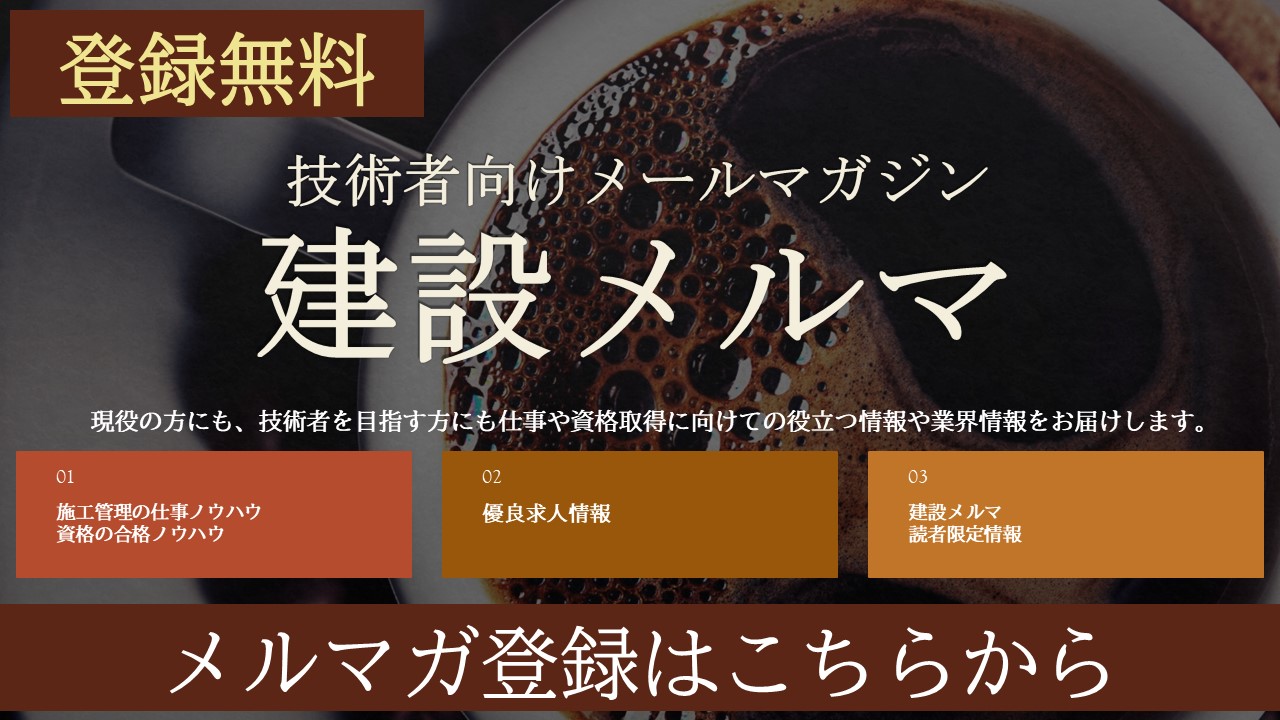どんなことができるの?
操作方法はどうやって勉強すればいいの?
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- Rebroの特徴がわかる
- Rebroの価格や勉強方法がわかる
- Revitとの違いがわかる
Rebro(レブロ)について解説します。
業務効率化などに有益なソフトなので、検討してみてください。
目次
Rebro(レブロ)とは
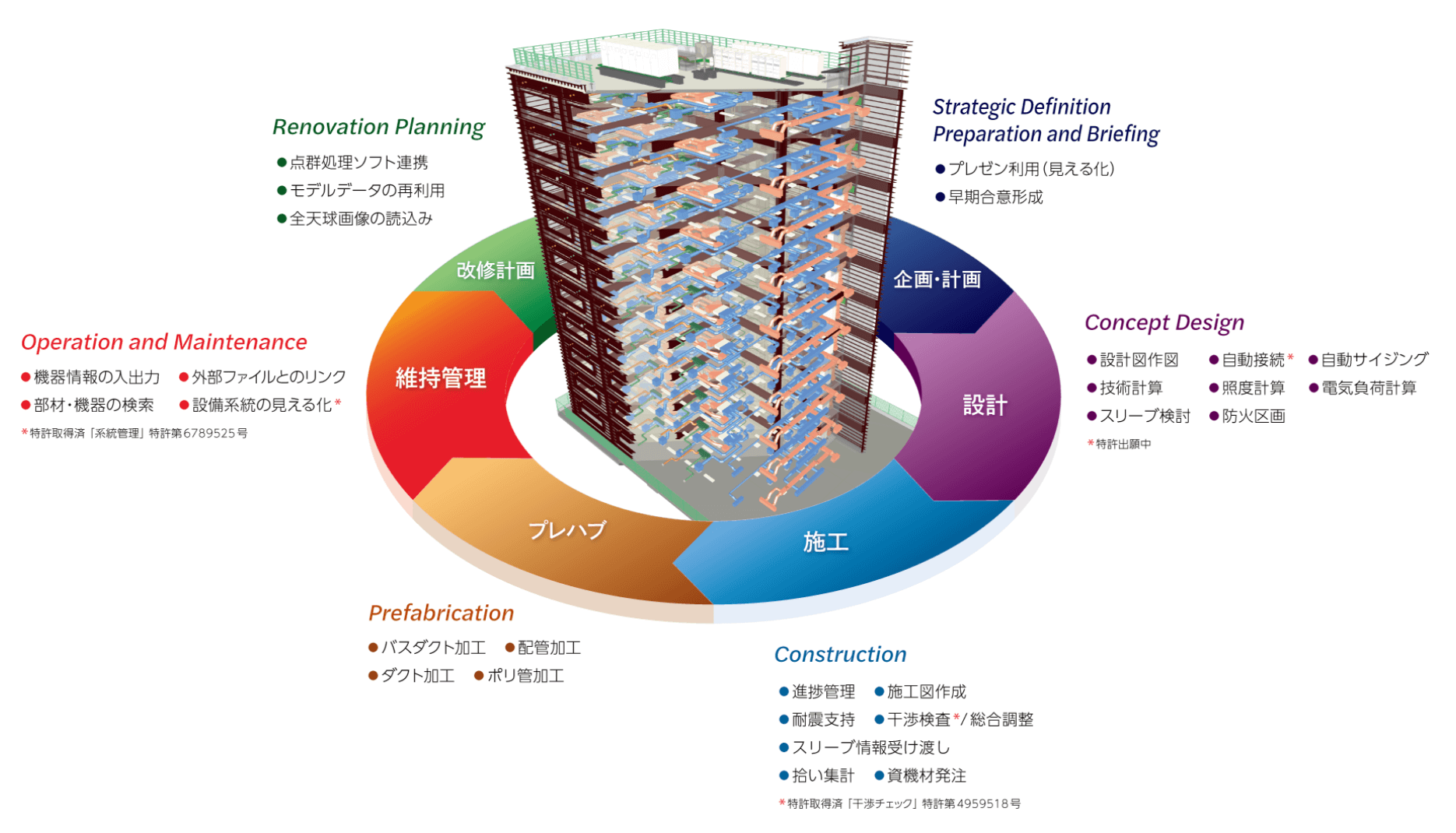
Rebroとは、建築設備専用の3次元CADソフトです。
具体的には、下記のような設計に使えます。
- 空調設備
- 衛生設備
- 電気設備
設計、施工、メンテナンス、改修設計にも活用できます。
開発元はNYK SYSTEMSです。
Rebroの特徴
Rebroの大きな特徴は、BIMソフトに対応していることです。

近年はBIMソフトが普及しているため、BIMとの互換性が重視したいところですね。
※BIMについては、BIMやCIMソフトの建築や土木の設計のメリットにまとめてます。
設計データから平面図、断面図、詳細図、衛生図面、空調図面、スリーブ図などを切り出せるため、図面を1つずつ作成する必要がありません。
各図面は連動しているため、1つ修正すると他の図面も修正されます。
図面をチームで共有できるため、誰かが図面を修正すれば、常に最新版の図面を確認することも可能。
詳しくはNYK SYSTEMSのサイトを見てもらうとわかりますが、直感的な操作ができるのも大きな魅力です。
CGを確認しながら設計できたり、360°回転させて細部をチェックできます。
断面カットや干渉検査もできるため、ミスも減りやすいかと。
また、CGの動画も作れるため、合意形成にも有益です。
Rebroの価格
Rebroには総合版と電気版があります。
- 総合版:全機能が搭載
- 電気版:電気設備設計向け
ダイキンや大塚商会のサイトによると、価格は下記のとおりです。
- 総合版:1,100,000円(税込)
- 電気版:935,000円(税込)
また、2年目以降は下記の保守料金が発生します。
- 1本:66,000円(税込)/年
- 複数台:52,800円(税込)/年・本
保守があるため、新しいバージョンのソフトを買い直す必要はありません。
また、1ヶ月単位で使えるレンタルプランもあります。
価格は、1本あたり16,500円/月です。
Rebroの導入向けの補助金アリ
ちなみにRebroの導入には、中小企業や小規模事業者向けの補助金が使えます。
下記は2022年時点での補助金です。
- IT導入補助金:購入費用の50%を補助(30~150万円)
- 中小企業経営強化税制or中小企業投資促進税制:即時償却か最大10%の税額控除
補助金もNYK SYSTEMSが提案してくれるので、問い合わせをしてみましょう。
マニュアルや講習会で勉強できる

結論、Rebroは導入後のサポートがかなり充実しています。
具体的には下記のような無償サポートあり。
- マニュアル
- 動画教材
- 無償講習
- 社内教育用のライセンス
追加費用が発生しないのは大きなメリットです。
※無償講習は、今のところ東京と大阪で開催。
もちろん電話やメールのサポートもあるので安心です。
RebroとRevitの違い


違いは下記のとおりです。
| Rebro | Revit | |
| ソフトの種類 | CAD | BIM |
| 設計の範囲 | 建築設備 | 意匠・構造・設備・施工 |
| 価格 | 製品価格
2年目以降の保守料金
|
|
そもそも「RebroはCAD」「RevitはBIM」という大きな違いがあります。
また、Rebroは建築設備設計に特化しているのに対して、Revitは総合建設業でも利用可能。
Rebroは導入費用が大きいですが、保守料金が安いです。
一方、Revitは期間ごとに料金がかかるイメージ。
Revitはバージョンアップに対応しているので、Rebroと同じくソフトの買い直しは必要ありません。
Revitの詳細は、Revitとは?できることや価格を解説【使い方の勉強方法も紹介します】を参考にどうぞ。
まとめ【Rebroの特徴を知って導入を検討してみましょう】

最後にもう一度、Rebroの代表的な特徴をまとめておきます。
- BIMソフトに対応している
- 設計データから平面図、断面図、詳細図、衛生図面、空調図面、スリーブ図などを切り出せる
- 各図面は連動しているため、1つ修正すると他の図面も修正される
- 直感的な操作が可能
- CG化や360°回転で細部をチェックできる
- CGの動画を作れるので合意形成に有益
- 断面カットや干渉検査もできるため、ミスが減りやすい
NYK SYSTEMSでは、Rebroのデモンストレーションや、実機を操作できる体験セミナーも実施しているので、まずはRebroにさわってみましょう。
実機に触れながら検討してもいいと思います。
業務効率化に有益なソフトなので、導入を検討してみてください。