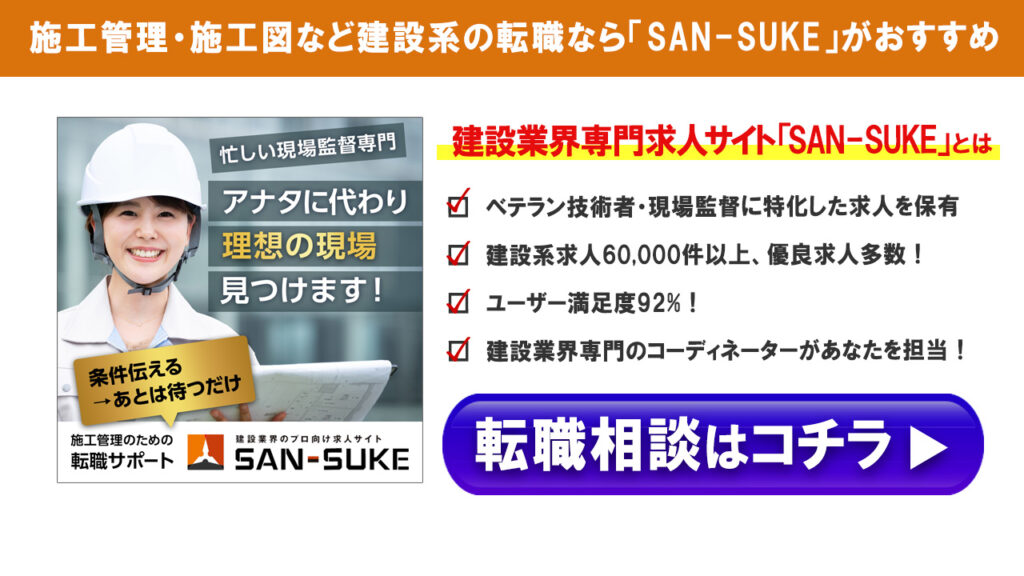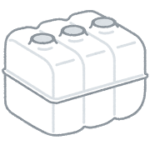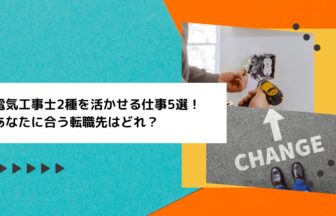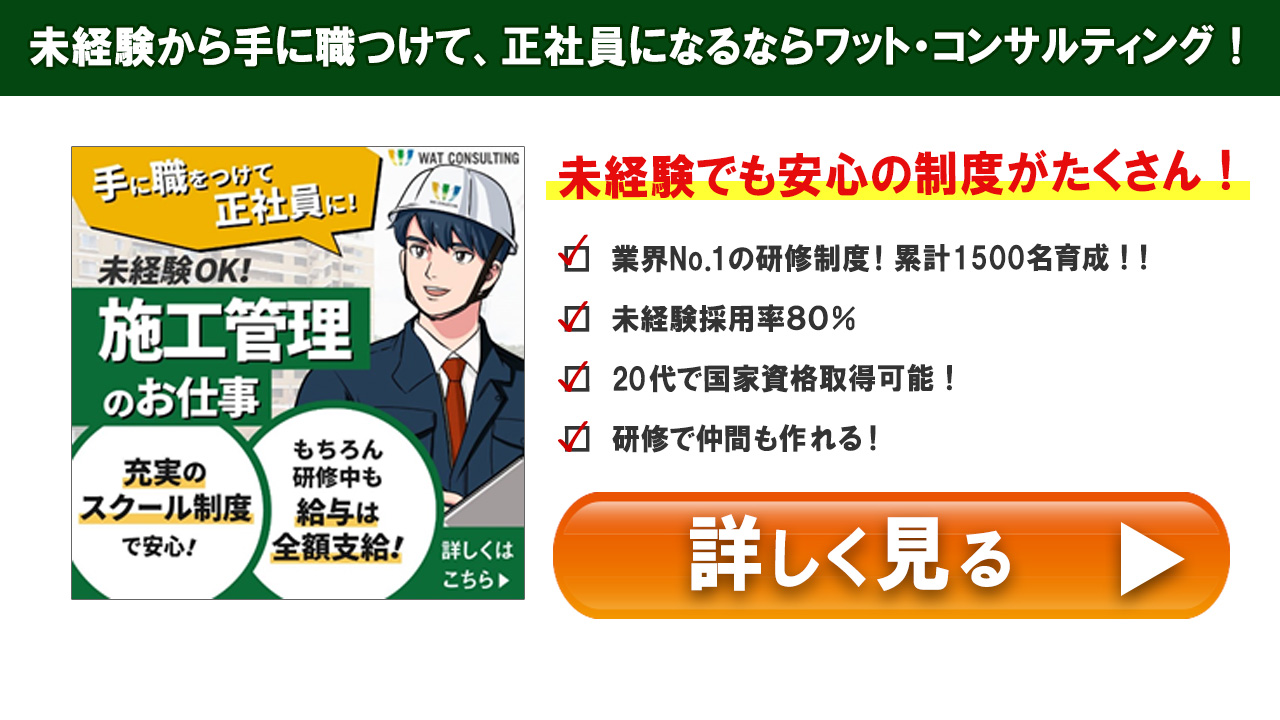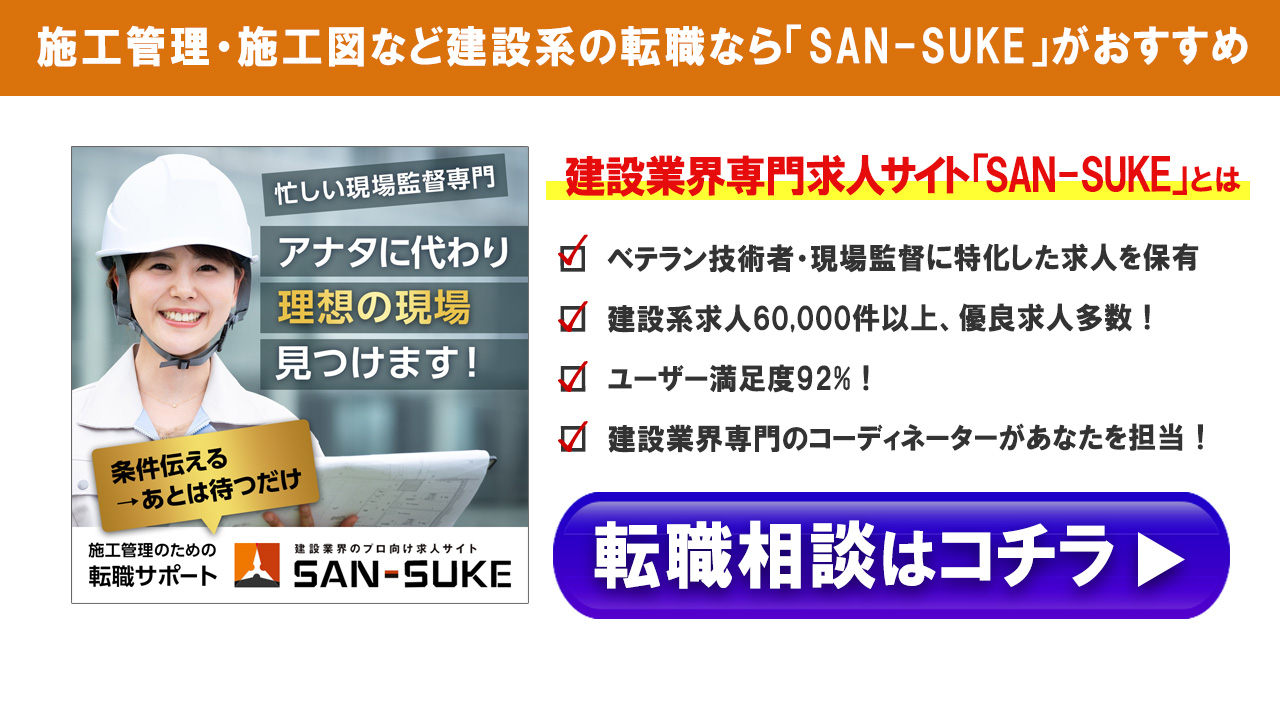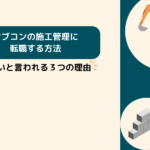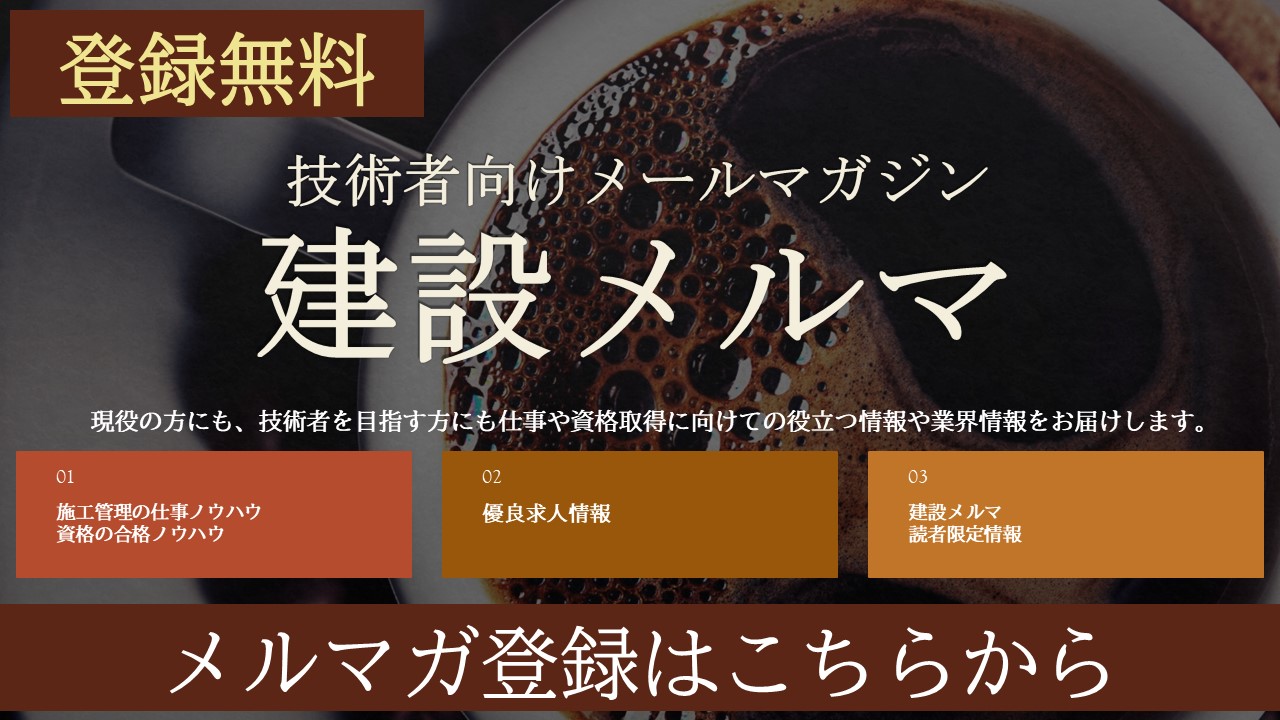もし難関資格だったら、勉強が大変そう…
勉強方法のコツとか知りたいな。
あと、防犯設備士と併せて取得しておいた方がいい資格ってある?
資格をとってキャリアアップしたいんだよね。
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- 防犯設備士の試験の難易度がわかる
- 防犯設備士の試験情報がわかる
- 防犯設備士と併せて取得したい資格がわかる
防犯設備士とは、公益社団法人日本防犯設備協会が主催する民間資格です。
公益社団法人日本防犯設備協会は警察庁や関連団体と連携しながら防犯設備の調査・研究を行うとともに、防犯設備の専門家の資格として、防犯設備士資格を発行しています。
※防犯設備士は2021年4月時点で30,000人を超えています。
建築設備会社の社員さんなど、多くの人が取得している重要な資格です。
この記事では、防犯設備士の難易度や試験内容を解説するので、試験対策の参考にしてみてください。
セットで取得したい資格も紹介するので、キャリアアップのイメージにどうぞ。
目次
防犯設備士の試験の難易度【合格率は高め】

防犯設備士の試験は、そこまで難しくありません。
合格率は公表されていませんが、合格率は70〜80%台なので、きちんと勉強すれば合格できると言えるでしょう。
そもそも防犯設備士は、講習を受けてから試験を受けるスタイルです。
先に講習を受けられるので、割と合格しやすい試験です。
2021年度の試験からオンライン講習がスタート【くりかえしの視聴が可能】
2021年度の試験から、講習がオンライン形式になりました。
しかも、講習はくりかえしの視聴が可能。
場所を選ばずしっかり学習できるので、以前より合格しやすいと思われます。
防犯設備士の合格基準【60%以上の正答】
試験の合格基準は「60%以上の正答」です。
試験問題については下記のとおり。
- 試験時間:110分
- 出題数:40問
- 問題形式:択一式、穴埋め、◯×問題
試験は全国で約300ヶ所のテストセンターにて、パソコン操作(マウスで正答をクリック)で受験します。また受験会場は日時・場所を選択して自分で予約します。
記述式問題などがないため、そこまで難しくない試験です。
きちんと勉強して試験に臨みましょう。
防犯設備士の試験内容【パソコンで受験】

受講を終了すると、試験を受けることができます。
前述のとおり、試験は全国で約300ヶ所のテストセンターにてパソコン操作で受験します。
試験科目は下記のとおり。
- 防犯の基礎
- 電気の基礎
- 設備機器(侵入警報設備、防犯カメラ設備、出入管理設備、インターホン設備、不正持出し監視設備、防犯グッズ)
- 設備設計
- 施工・維持管理
暗記系の問題が中心ですが、下記のジャンルは少しだけ計算問題もあります。
- カメラの焦点距離
- オームの法則
講習では図で表されていたものも、試験問題になると文章になっているケースがあるため、読解力と想像力も必要です。
講習でやっていない問題も出ますので、基礎がわかってないと解けないようになっています。
つまり、丸暗記だけでは合格できないので、きちんと理解する勉強が必要です。
防犯設備士の細かい試験情報【年4回実施】
防犯設備士の試験情報を紹介します。
| 受験資格 | 防犯設備士の講習を受講した人 |
| 申込期間(年4回) | 1回目:4~5月
2回目:7~8月 3回目:10~11月 4回目:1~2月 |
| 申込方法 | 日本防犯設備協会のホームページから申込 |
| 講習時期(年4回) | 1回目:4〜6月
2回目:7〜9月 3回目:10〜12月 4回目:1〜3月 |
| 試験会場 | 全国約300ヶ所のテストセンター |
| 試験時期(年4回) | 1回目:4〜6月
2回目:7〜9月 3回目:10〜12月 4回目:1〜3月 |
| 受験費用(日本防犯設備協会の非会員の場合) | 受験料:11,000円
受講料(テキスト代込み):33,000円 過去問題集(1年分):2,200円 合計:46,200円 (過去問題集を2年分購入すると48,400円) |
ちなみに試験は予約制ですが、試験日の3日前までであれば、受験地や時間の変更が可能ですので、急なスケジュール変更にも対応できます。
また、合格後、資格者証の申請が必要です。カードサイズの資格者証は必須で5,500円、A4サイズ掲示用資格証書は任意で3,300円が必要です。
詳しくは、公益社団法人日本防犯設備協会のホームページを確認してみましょう。
【ちなみに】防犯設備士は更新制度あり
防犯設備士を取得したら、3年ごとに更新しないと資格を維持できません。
更新を申請すると自宅に資格更新用テキストと問題が送付され、解答用紙を返送すれば資格更新ができます。また、2021年度から地域限定での「更新講習」も試行されています。更新講習の場合には、解答用紙の提出は不要で講習参加のみで更新が可能です。
更新費用は11,000円です。
忘れずに更新するようにしましょう。
防犯設備士の勉強方法【過去問題集は2年分を買う】
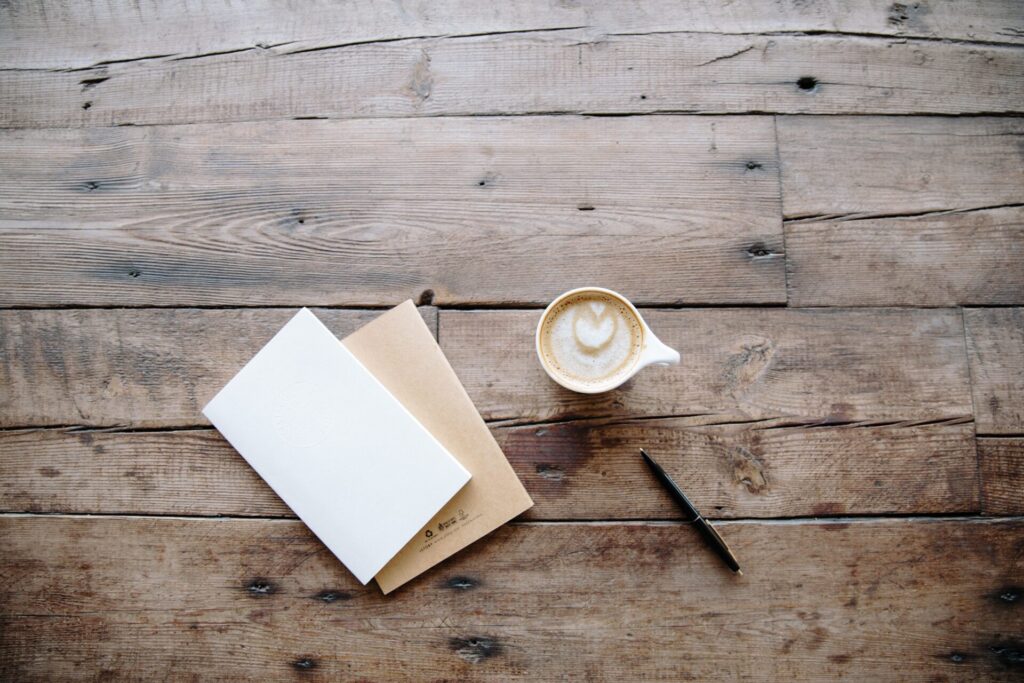

結論、日本防犯設備協会が販売している過去問題集を2年分購入してください。
過去問と似た問題が出題されやすいので、過去問に触れるのが一番だから。
1年分で2200円なので、安い投資だと思います。
もし不合格になってしまうと、また受験費用がかかってしまうので、一発合格するためにも過去問題集は2年分がおすすめです。
テキスト+オンライン講習→過去問をくりかえし解く
王道の勉強方法ですが、下記の3ステップでOKです。
- テキストを見ながらオンライン講習を受ける
- あとはひたすら過去問をくりかえし解く
- 間違えたところは、テキスト、講習をよく見て理解する
「まずは基礎知識を身につけて、あとはひたすら実戦」というイメージです。
過去問は、できれば5回は解いてください。
問題と答えを丸暗記できれば、合格率はかなり上がります。
防犯設備士とあわせて取得したい3つの資格


資格を取って、キャリアアップしていきたいんだよね。
結論、下記の3つがおすすめです。
- 消防設備士
- 電気工事士
- 建築設備士
1つずつ解説しますね。
①消防設備士
おすすめの理由は、建築設備の守備範囲を広げられるから。
消防設備士には、下記のようなジャンルがあります。
| 種類 | 点検・整備・工事の対象 |
| 特類(甲種のみ) | 新ガス消火剤
加圧排煙設備 複数の総合操作盤 インバーター制御スプリンクラーポンプなどの特殊消防用設備 |
| 1類(甲・乙) | 屋内消火栓設備
スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 屋外消火栓設備 パッケージ型消火設備など |
| 2類(甲・乙) | 泡消火設備
パッケージ型消火設備など |
| 3類(甲・乙) | 不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 パッケージ型消火設備など |
| 4類(甲・乙) | 自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備 消防機関へ通報する火災報知設備 共同住宅や住戸用の自動火災報知設備など |
| 5類(甲・乙) | 金属製避難はしご
救助袋 緩降機 |
| 6類(乙種のみ) | 消火器 |
| 7類(乙種のみ) | 漏電火災警報器 |
参考:一般財団法人消防試験研究センター「消防設備士免状の種類」
特に6類は誰でも受験できるのは、まずは6類から挑戦してみると良いでしょう。
詳しくは、消防設備士の試験内容や合格率からみる難易度にまとめてます。
②電気工事士
おすすめの理由は、カンタンな電気工事が必要なときに活躍できるから。
防犯設備やその他の設備工事を行う際は、電気工事が必要になるシーンもあります。
電気工事は電気工事士しかできないため、いざというときのために取得しておくのがおすすめです。
第二種であればそこまで難しくないので、スキルアップのためにも挑戦してみましょう。
電気工事士については、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツに詳しくまとめてます。
③建築設備士
おすすめの理由は、建築設備系の最高峰の資格だから。
建築設備士は電気・給排水・空調設備などの専門知識をもち、建築士に対して建築設備の設計や工事監理のアドバイスをする国家資格です。
資格があれば二級建築士・木造建築士の受験資格を得られますし、建築設備士として4年以上の実務経験があれば一級建築士の受験資格も得られます。
建築設備の分野でキャリアアップしていくなら、いずれは取得したい資格の1つなので、興味あれば挑戦してみてください。
建築設備士については、建築設備士の受験資格や試験の難易度!独学でも合格できるのか?に詳しくまとめてます。
まとめ【防犯設備士の難易度はそこまで高くない。さっそく勉強を始めよう】

この記事をまとめます。
- 防犯設備士はオンライン学習できるようになった
- オンライン講習はくりかえし視聴できるので勉強しやすい
- 合格率は高めなので、そこまで難しい試験ではない
- 過去問題集を2年分購入して、くりかえし解こう
ということで、さっそく日本防犯設備協会のホームページから、講習と試験の申し込みをしてみてください。
2年分の過去問題集を購入するのもお忘れなく。
オンライン講習をくりかえし見て、過去問をくりかえしといて合格を目指しましょう。
また、防犯設備士と併せて取得したいおすすめの資格は下記の3つです。
- 消防設備士
- 電気工事士
- 建築設備士
3つの資格の詳細は、下記の記事にまとめたので参考にどうぞ。
あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!