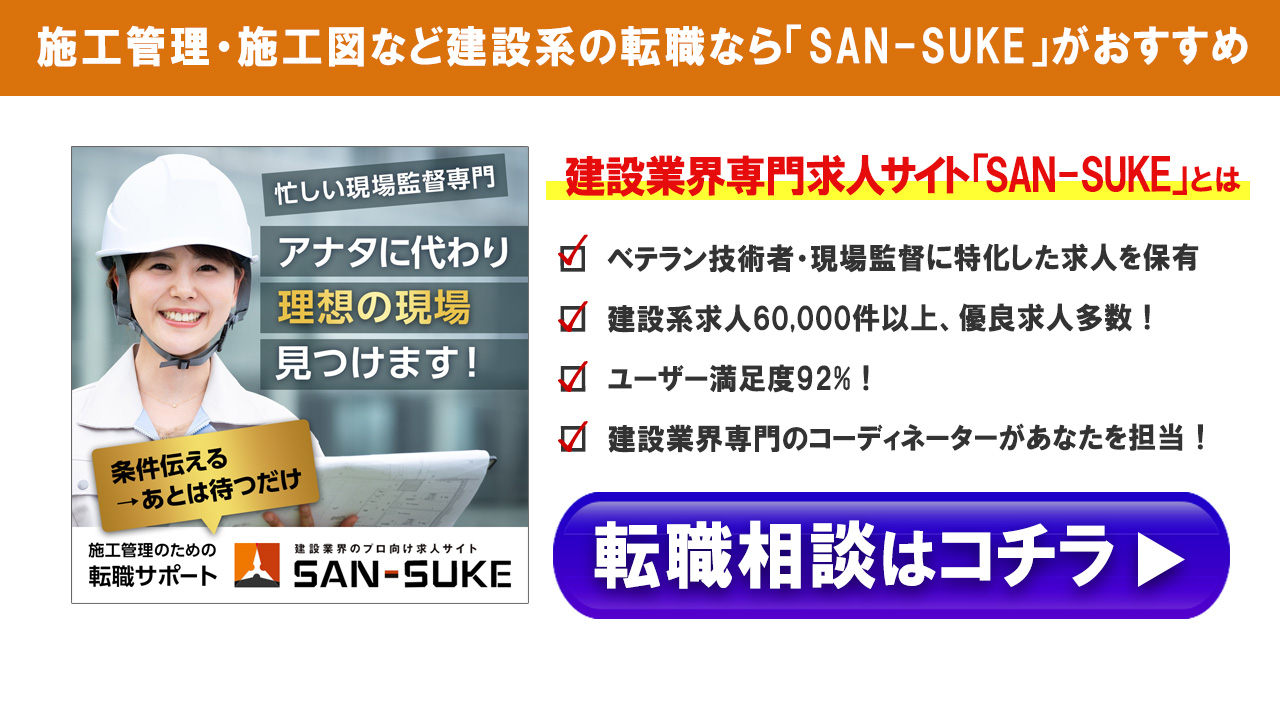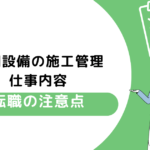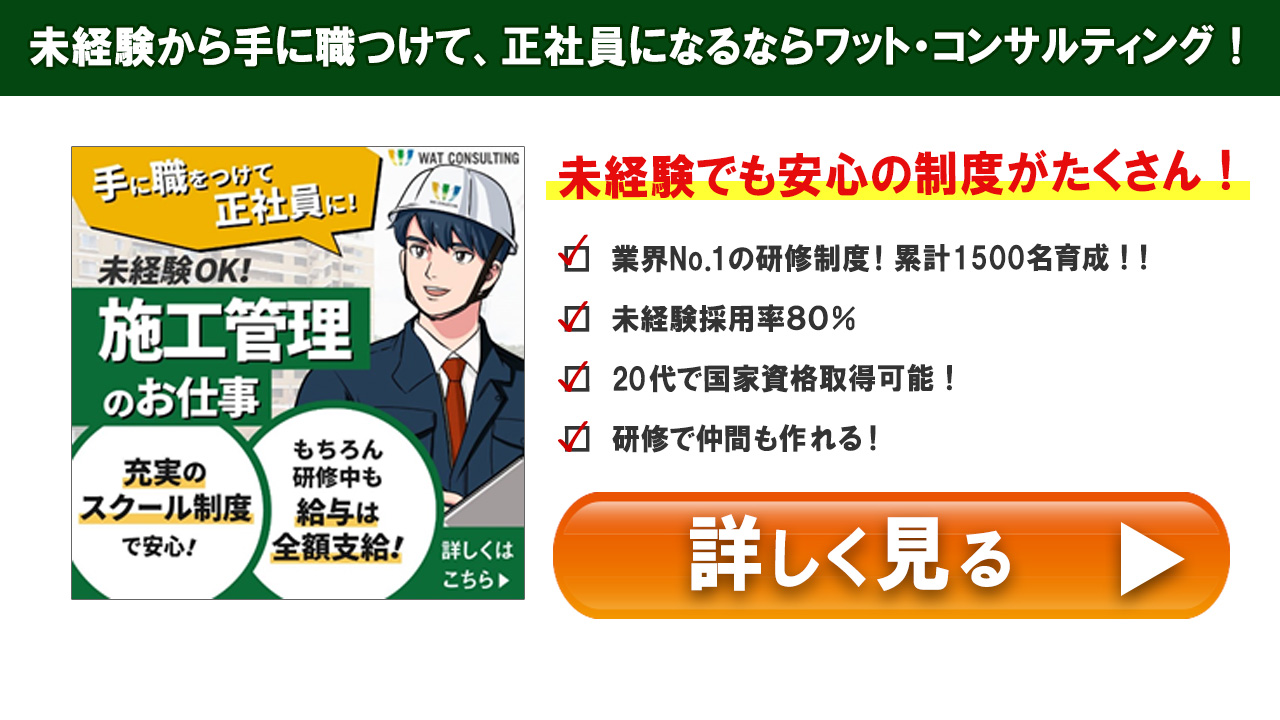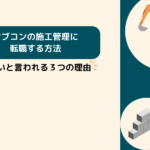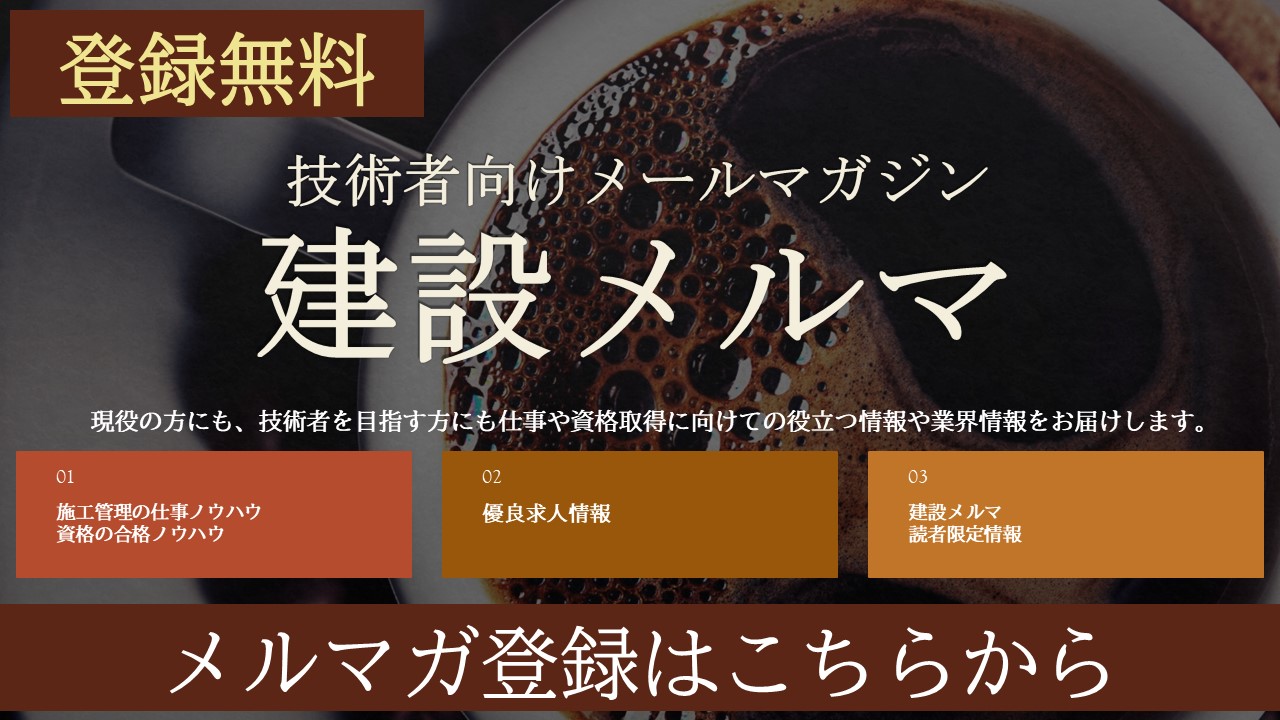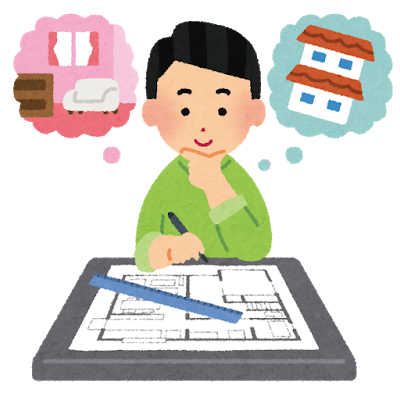
計算方法とか、建築基準法はどうなってるんだっけ?
あと、バリアフリー設計についても知っておきたいな。
という疑問に答える記事です。
この記事の内容は下記のとおり。
- スロープの勾配の計算方法を解説
- スロープ勾配1/8・1/12・1/15の早見表
スロープの勾配について解説します。
建築基準法とバリアフリー法では、勾配の基準が違うので注意してください。
建物の用途や、利用者の立場を考えた設計が重要です。
スロープ勾配の計算方法や、勾配の早見表も作成したので、設計の参考にしてください。
目次
スロープの勾配の計算方法を解説
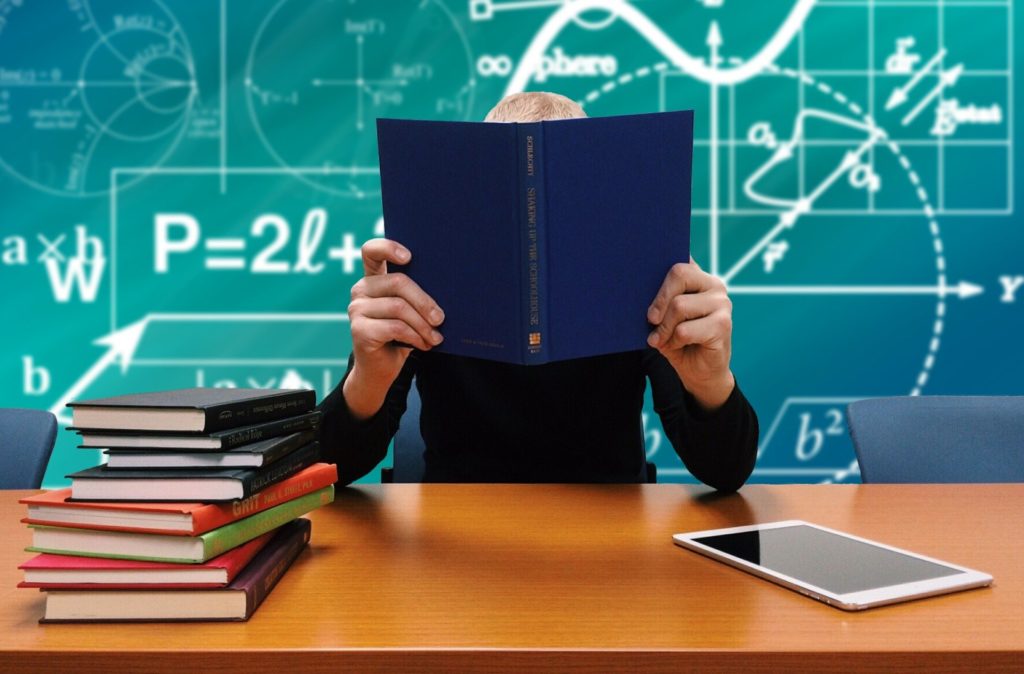
スロープの勾配の計算方法は、高さに対して、水平距離でどれくらいの長さをとるかで計算します。
例えば、高さ10cm上がるスロープで、水平距離100cmなら、勾配は1/10となります。
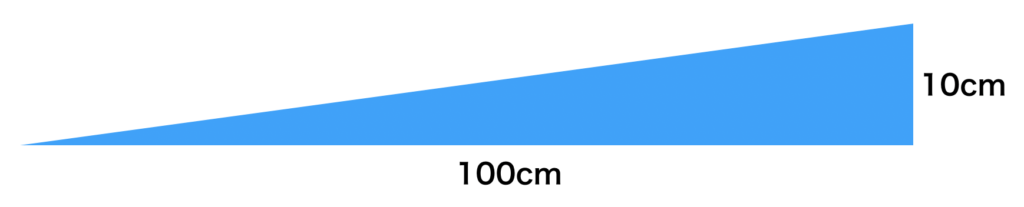
ちなみに、1/10の角度は約5.7°です。
※三角形の角度計算のサイトが便利です。
建築基準法におけるスロープの勾配【ただし好ましくない】
建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)によると、下記のように決められています。
- 勾配は、1/8を超えないこと
- 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上ること
ちなみに、1/8の角度は約7.1°です。
【建築基準法違反】スロープ勾配1/6の角度
例えば、1/6の角度を計算すると約9.5°です。
たしかに、角度10°近くはかなり急勾配です。
特に車いすでは上がることが困難ですし、下るのも危険です。
なのでスロープは、次に紹介するバリアフリー法で設計する方が良いですね。
【こっちを基準にする】スロープの勾配基準【バリアフリー法編】
バリアフリー法では、スロープの勾配基準が決められています。
バリアフリー法には、下記の2つの基準があります。
- 最低限の基準:建築物移動等円滑化基準
- 望ましい基準:建築物移動等円滑化誘導基準
参考:国土交通省「バリアフリー法」
最低限の基準:建築物移動等円滑化基準の内容
最低限の基準は下記のとおりです。
- 手すり:片側
- スロープの幅:120cm以上
- スロープ勾配:1/12以下
望ましい基準:建築物移動等円滑化誘導基準の内容
望ましい基準は、下記のようになっています。
- 手すり:両側
- スロープの幅:150cm以上
- スロープ勾配:1/12以下、屋外は1/15以下
できるだけ「望ましい基準」に近づけるようにしましょう。
スロープが長くなりすぎるときは、75cm以下ごとに150cm以上の踊り場を設置してください。
スロープ勾配1/12の角度計算【車いすの自走の限界】
ちなみに、車いすで自走で上る限界は1/12と言われています。
計算すると、角度は約4.8°です。
だいぶ緩やかに見えますが、車いすの自走はかなり重労働です。
特に、お年寄りだとかなり困難。
できれば1/15が望ましいです。
スロープ勾配1/15の角度計算【車椅子の自走ができる】
車いすで自走で上りやすいのは、1/15以下です。
角度にすると、約3.8°ですね。
これでかなり緩やかになります。
【ちなみに】車のスロープの勾配
国土交通省の駐車場設計施工指針によると、車のスロープは12%以下が望ましいです。
普通乗用車以下の車両を対象にする場合は、やむを得ない場合は17%まで増やすことができます。
ちなみに12%とは、水平距離100cmに対して高さ12cm上がることです。
角度にすると、約6.8°です。
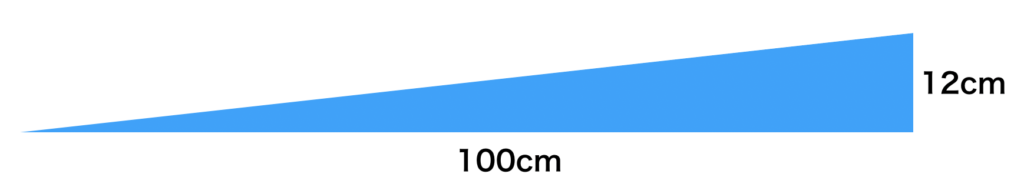
スロープ勾配1/8・1/12・1/15の早見表
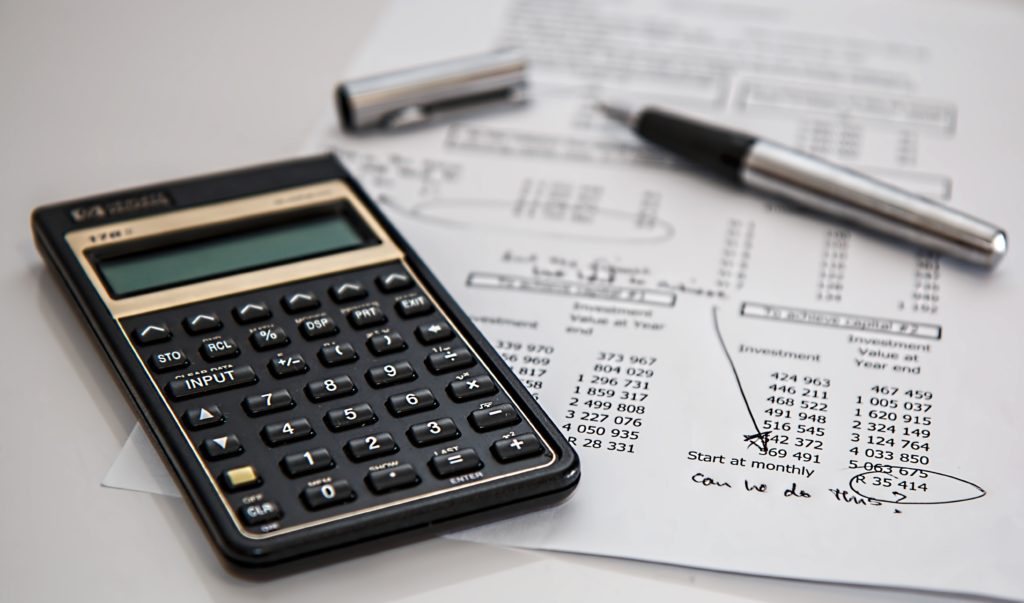
すぐにわかるように、スロープの早見表を作りました。
設計の参考にしてください。
| 勾配 | 1/8 | 1/12 | 1/15 |
| 角度 | 7.125° | 4.763° | 3.814° |
| スロープの長さ(高さ10cmの場合) | 80cm | 120cm | 150cm |
| 介助者(上り) | きつい | 普通 | 楽 |
| 介助者(下り) | 後ろ向き | 前向きOK | 前向きOK |
| 自走(上り) | 無理 | きつい | 普通 |
| 自走(下り) | 無理 | 危ない | 大丈夫 |
あまりにもスロープが長くなりすぎるなら、折り返し地点・踊り場を設置しましょう。
まとめ【スロープ勾配は1/12以下が望ましい】

この記事をまとめます。
- スロープ勾配は、高さに対して、水平距離の長さで計算
- 建築基準法では1/8以下になっているが、バリアフリー法の方が望ましい
- バリアフリー法のスロープ勾配は、1/12が最低限、1/15以下が望ましい
- 車のスロープは12%以下にすること
- スロープが長くなりすぎるなら、折り返しや踊り場を設置
スロープの設計の参考になればうれしいです。
ちなみに、階段と手すりの記事もあるので、参考にしてみてください。
あなたの仕事の参考になればうれしいです!