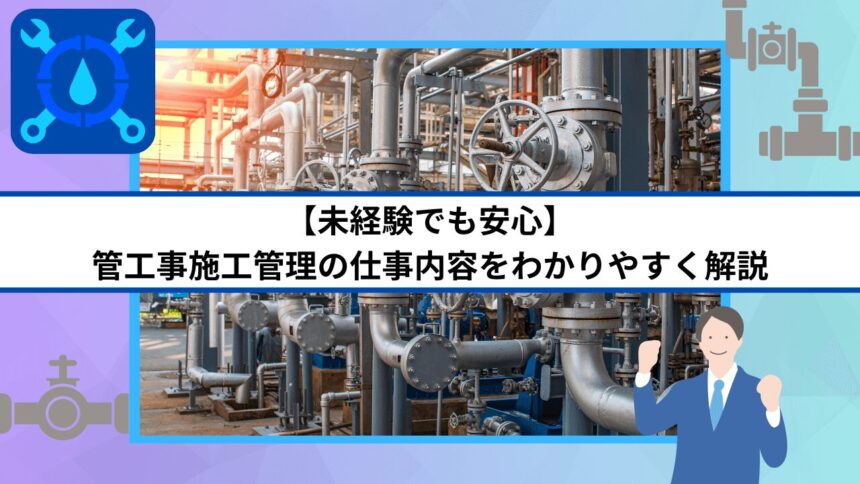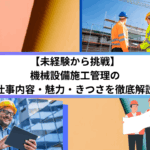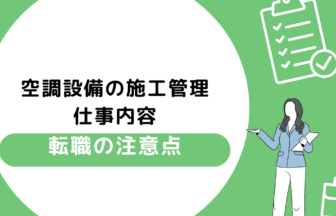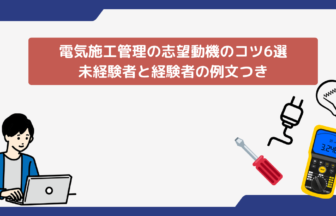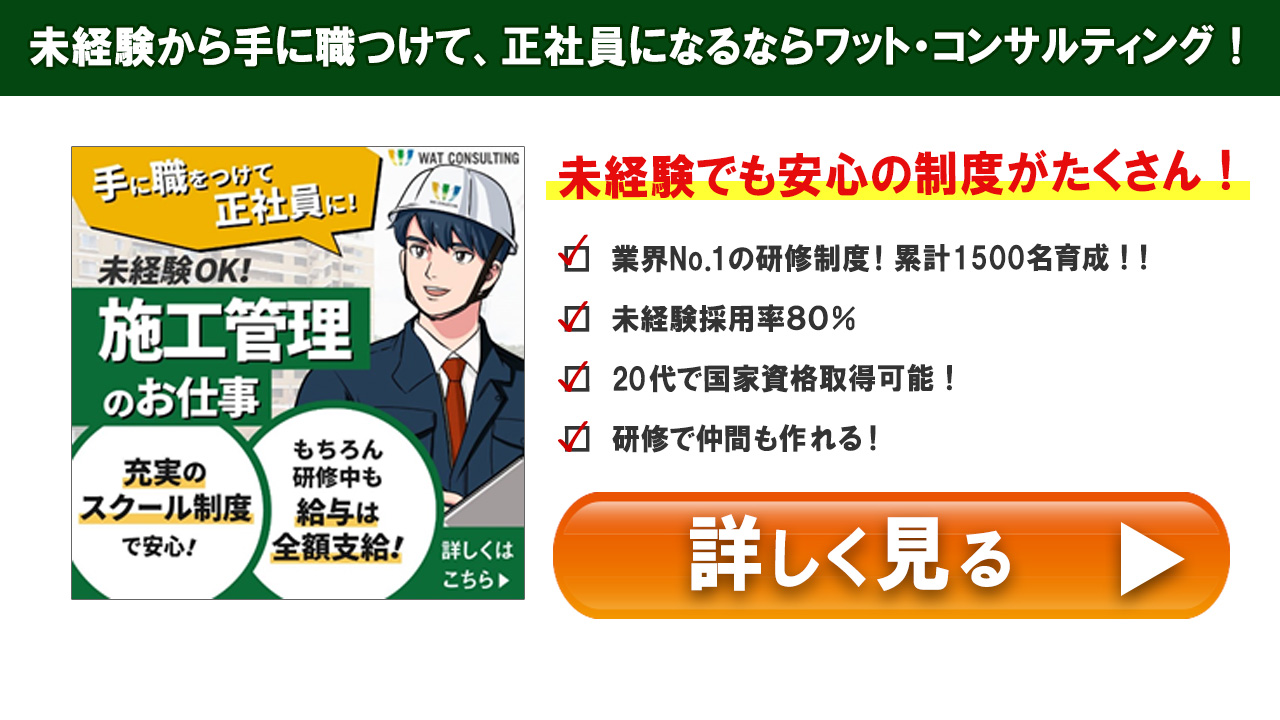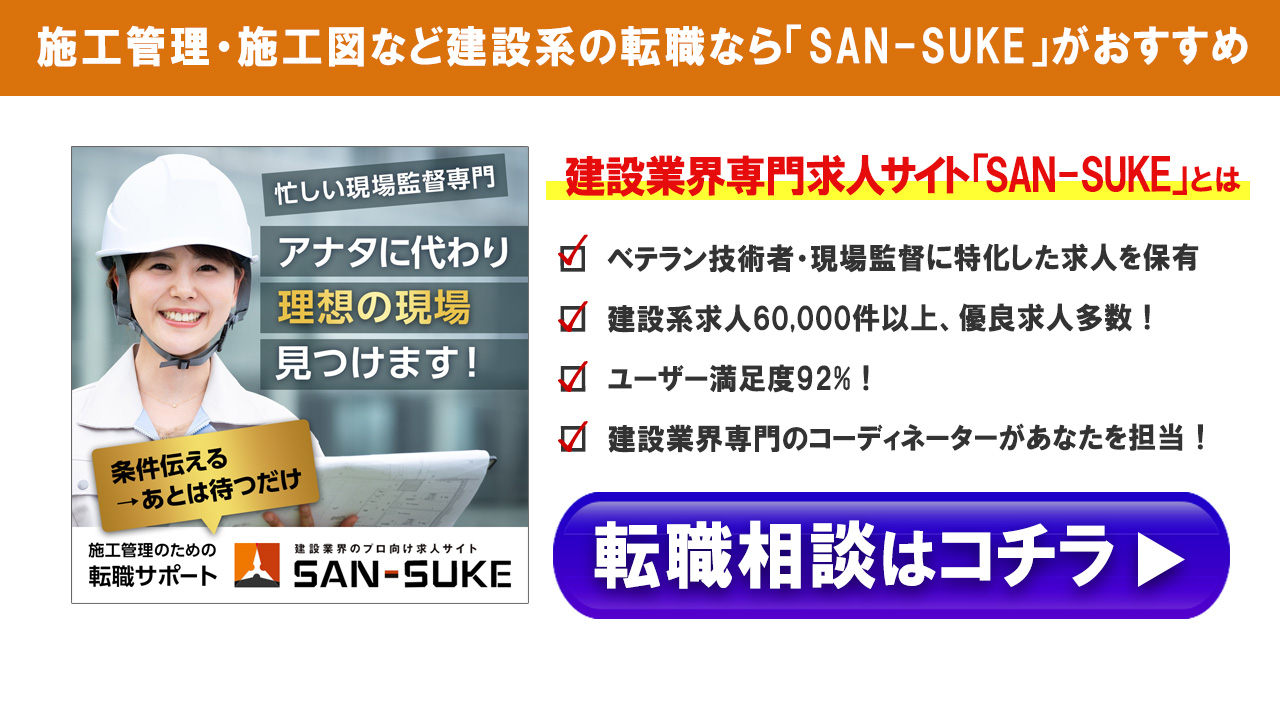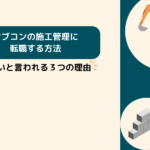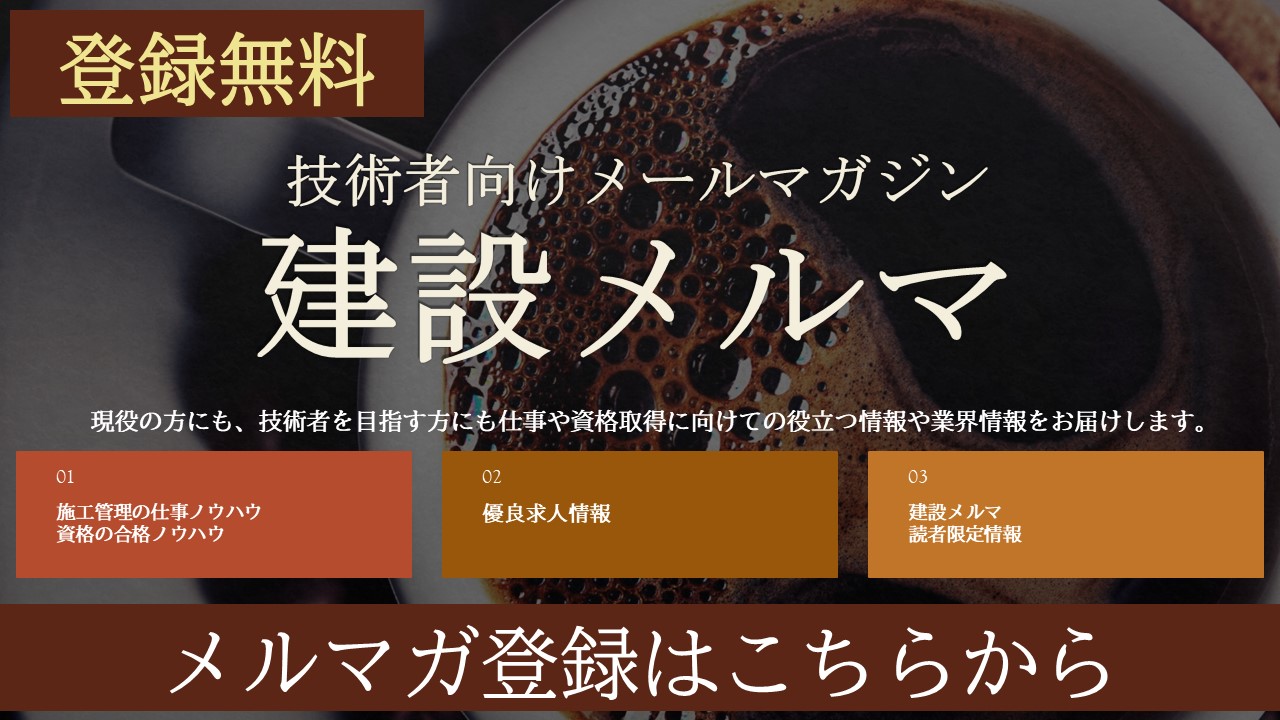「管工事施工管理って何をする仕事なの?」
「未経験からでも挑戦できる仕事なの?」
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかること
- 管工事施工管理の基本と仕事内容
- 管工事施工管理のきついところ5選
- 管工事施工管理のメリット5選
- 管工事施工管理に向いている人・向いていない人の特徴
- 未経験から管工事施工管理に転職するコツ
私たちワット・コンサルティングは、施工管理の技術者派遣の会社です。
未経験から管工事施工管理に転職したい方を募集しています。
管工事施工管理は水道・空調・ガス・衛生設備など、配管工事を監督・管理する仕事です。
インフラに関わる需要の安定性や将来性、快適な生活環境づくりに貢献できるやりがいなど、多くの魅力があります。
ポイント
年収800万円以上も狙える職種です。
この記事では、管工事施工管理の本当の姿を「きついところ」と「メリット」の両面から解説します。
あなたの適性を見極め、より良いキャリアを選択したい方は最後まで読んでみてください。
この記事の監修者
施工管理の技術者派遣を行う会社。これまで1500名以上の未経験者を施工管理として育成した実績あり。
- 労働者派遣事業許可番号 派13-304593
- 有料職業紹介事業許可番号 13- ユ-304267
- 特定建設業 東京都知事許可 (特-1) 第150734号
目次
管工事施工管理とは【基本の解説】
管工事施工管理は、建物に欠かせない水道・空調・ガス・衛生設備などの配管工事を監督・管理する不可欠な業務です。
図面通りに配管が設置されているか確認し、工事全体の品質を保証する役割をもちます。
現場では職人との連携や工程調整はもちろん、安全管理や品質確保まで幅広い責任を担当します。
水や空気、燃料の流れを制御する設備を扱うため、細部まで注意を払わなければなりません。
管工事には以下の主要分野があります。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 水道 | 給排水や浄化槽などを扱い、飲料水や生活排水の配管を担当 |
| 空調 | 冷暖房や換気の設備を配置し、室内環境を適切に保つ |
| ガス | ガス配管を設置して調理や暖房に必要なエネルギーを供給 |
| 衛生設備 | トイレや手洗いなどの衛生管理に関係し、快適さを左右する |
管工事施工管理は、これらすべての分野を統括し、建物の機能性と快適性を確保する役割を担っています。
適切な配管設計と施工は、建物の安全性と長寿命化にも直結します。
ちなみに管工事施工管理の種類については、以下の記事も参考にしてみてください。
参考記事
管工事施工管理技士の仕事内容
管工事施工管理技士は、配管工事の現場責任者として全体を統括します。
多岐にわたる業務の中でも、特に重要な5つの管理業務があります。
管工事施工管理の仕事内容
- 工程管理:工事スケジュールの策定と進捗管理
- 安全管理:現場の安全対策、労災防止
- 品質管理:配管の施工品質や使用資材のチェック
- 原価管理:予算どおりに工事を収めるための調整
- コミュニケーション:下請け・職人・施主との折衝
配管は一度壁や床に埋め込まれると、修正が非常に困難になります。
そのため、施工段階での綿密なチェックが不可欠です。
小さなミスが後々大きな問題につながる可能性があるため、高い精度と注意力が求められます。
参考記事:【完全解説】施工管理の仕事内容をわかりやすく解説!会社選びのコツも紹介
管工事施工管理の一日のスケジュール例
朝は現場の安全確認や当日の作業指示が中心で、午後は打ち合わせや調整業務、夕方以降は進捗確認と翌日の準備が主な流れとなります。
一日のスケジュールの例は以下のとおりです。
| 時間帯 | 主な内容 |
|---|---|
| 7:00~7:30 | 現場到着、機材や足場の点検、安全確認 |
| 7:30~8:00 | 朝礼とミーティング、当日の作業工程を共有 |
| 8:00~12:00 | 配管工事の進捗管理、施工図との整合性チェック、写真撮影 |
| 13:00~15:00 | 施主や建築側との打ち合わせ、工程修正が必要な場合は調整 |
| 15:00~17:00 | 材料の手配や書類作成、職人への指示内容を整理 |
| 17:00~19:00 | 追加作業の有無を現場で再確認、日報の記入や安全点検 |
| 19:00~20:00 | 次日の段取りを確認、全体を巡回して後片付け、退社 |
工事の進行状況によって、計画変更や緊急対応が必要になることもあります。
管工事は夜間に進めるケースもあるでしょう。
そのため、柔軟に対応できる判断力と問題解決能力が必要です。
現場の状況を常に把握し、先を見越した準備ができることが効率的な工事進行を実現します。
特に配管工事は他の工種との調整が必要なため、建築や電気工事などの担当者とのコミュニケーションも欠かせません。
一日の終わりには作業記録を残し、翌日の準備を整えることで、継続的に円滑な工事を進められます。
参考記事:施工管理(現場監督)の一日の流れや仕事のスケジュール
未経験から管工事施工管理に転職した人の体験談
私たちワット・コンサルティングで、管工事施工管理をしているE.Sさんの体験談を紹介します。
警察官として勤務していたE.Sさんは、「形として残る成果が見える仕事がしたい」という思いから、管工事施工管理への転職を決意しました。
E.Sさん
警察官時代は日々の業務が形に残りにくく、もっと目に見える達成感を感じられる仕事に挑戦したいと考えていました。
建設業界なら自分の関わった建物が形として残るため、やりがいを感じられると思いました。
転職先を探す中で、研修制度が充実しているワット・コンサルティングを選びました。
未経験者向けの体系的なカリキュラムがあることが決め手となったそうです。
E.Sさん
パソコン操作に苦手意識があったため、研修中は図面の読み取りやCAD操作などに苦労しました。
しかし、基礎から丁寧に教えてもらえたおかげで、徐々に理解できるようになりました。
現場配属後は、先輩社員のサポートもあり、実務にスムーズに適応できたといいます。
現在は主に写真撮影や配管経路の確認、職人さんとの打ち合わせなどを担当しています。
E.Sさん
最初の現場で携わった建物が完成したときは、想像以上の達成感がありました。
自分が確認した配管が建物の機能を支えていると思うと、大きな責任とやりがいを感じます。
今後のキャリアプランについては、管工事施工管理技士の資格取得を目指し、将来的には現場リーダーとして活躍したいと考えているそうです。
E.Sさん
警察官から建設業界への転身は大きな挑戦でしたが、学びながら成長できる環境を選んだことで、安心して新しいキャリアをスタートできました。
これから資格を取得して、さらにスキルアップしていきたいです。
未経験からでも、適切な研修と現場でのサポートがあれば、管工事施工管理の道で活躍できる可能性があることがわかります。
管工事施工管理のきついところ5選
管工事施工管理には、細やかな調整やリスクへの対応が欠かせません。
大変な面もありますが、それらを乗り越えることで得られる達成感も大きいです。
管工事施工管理のきついところ
- 狭い配管スペースでの施工調整
- 水・ガスなど漏れやすいリスク管理
- 配管材料の種類や規格が多彩
- 隠蔽部分の工事なのでミスできない
- 電気・建築側との連携が必要
以下では、それぞれのきつい部分の具体的な例や対処法について詳しく解説します。
関連記事:管工事施工管理のきついところ4選【他の施工管理との比較も紹介】
狭い配管スペースでの施工調整
狭い配管スペースでの施工調整は、思わぬ苦労が積み重なる部分です。
梁や天井裏、壁の内側など、限られた空間へ配管を通すだけでも手間取ります。
例えば、集合住宅の玄関横にある配管シャフトは、給排水や電気配線が集約されて混雑しがちです。
以下のような環境が代表的です。
狭い配管スペースの例
- 天井裏にダクトが交差している建物
- 配管シャフトが電気設備と重複している住戸
- 壁内部が既存の配管や補強材で埋まっている現場
こうした場所では、図面や現地測量を念入りに突き合わせる必要があります。
狭いスペースに正確な配管を収めるには技術と集中力が求められますが、そのぶん完成時の満足感も大きいです。
水・ガスなど漏れやすいリスク管理
水やガスの配管にミスがあると、漏れによって建物の資産価値や安全面に大きな影響が及びます。
給排水管のパッキンが劣化していたり、ガス管の接合部が緩んでいたりすると、天井裏の浸水やガス臭が発生する事例があります。
ポイント
高圧のガス管や大量の水が流れるラインでは、とくに注意が必要です。
圧力検査やリークテストを入念に行い、小さな兆候も見逃さない姿勢が求められます。
初期段階の確認を徹底すれば、安心感が高まるだけでなく、施工後の仕上がりにも良い影響が期待できます。
配管材料の種類や規格が多彩
配管の材料は金属系から樹脂系まで幅広く、運ぶものや場所によって最適な素材や規格が異なります。
以下の表は代表的な材料と用途の例です。
用途に合わない組み合わせを選ぶと、強度不足や不具合の原因になります。
さまざまな規格を把握し、素材の特性と合わせて最適な組み合わせを考える必要があります。
材料の違いを理解すればするほど、現場での信頼度と知識量が高まり、柔軟な提案ができるでしょう。
隠蔽部分の工事なのでミスできない
配管は壁の内側や天井裏、床下など外から見えない部分に敷設されるケースが多いです。
建物が完成してから不具合が判明すると、コンクリートの撤去など大がかりな補修になる場合があります。
例
基礎下の配管が割れていた場合、床をはつって新たにやり直す必要が生じることもあります。
施工段階で圧力テストや目視検査を繰り返しておけば、後からトラブルに悩まされるリスクが減ります。
念入りに確認し、確実に仕上げることで、完成後の建物が問題なく機能し、関係者からの評価も上がるでしょう。
電気・建築側との連携が必要
管工事は水道や空調だけでなく、電気ケーブルや梁などの建築要素と干渉する場面が多いです。
例えば、空調配管を通そうとしたとき、梁の補強工事や電気幹線ルートと重なり、進め方を再検討する必要が出てきます。
ポイント
こうした状況に対応するには、関係部署や協力業者との密な報連相が欠かせません。
施工手順や資材の選定をお互いにすり合わせておくと、スムーズに作業が進み、余計なやり直しも減ります。
連携が取れている現場ほど質の高い仕上がりにつながり、仕事への満足度も増していきます。
管工事施工管理のメリット5選
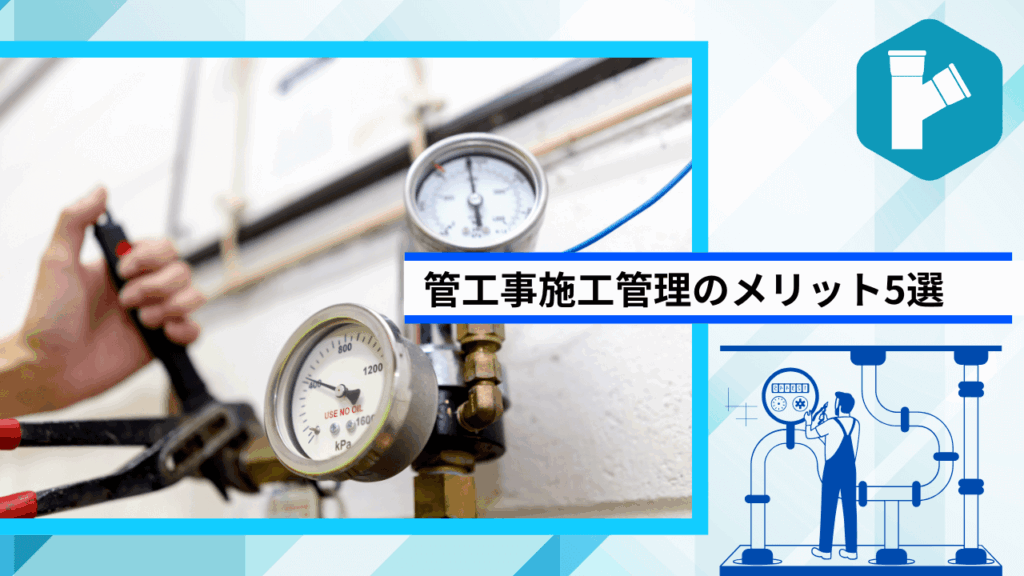
一方、管工事施工管理のメリットは以下の5つです。
管工事施工管理のメリット
- 「快適さ」に貢献できる
- インフラに関わる仕事で需要が安定している
- 年収アップを見込める
- スキルアップすると転職が有利になる
- 将来性がある
メリットも1つずつ解説していきます。
「快適さ」に貢献できる
暮らしに必要な水や空調を整える役割を担うのが管工事施工管理です。
例
シャワーの温度やエアコンの効き目など、建物利用者が日々感じる快適さを左右します。
給排水が円滑だとカビや悪臭を抑え、換気が適切だと室内環境も過ごしやすいでしょう。
現場で調整を重ねて設備を配置しきった場面では「生活の質に直結する仕事だ」と感じる機会が多いです。
建物全体の居住性が高まるほど、施主やテナントからの評価も高まり、達成感を味わえます。
インフラに関わる仕事で需要が安定している
管工事施工管理は、水道やガスといった社会基盤の工事を支えます。
人々が安心して水を使い、燃料を供給できる体制を作るため、需要が途切れにくいです。
ポイント
管路の老朽化や耐震化の遅れが全国的に存在するため、新築だけでなく改修案件も増えています。
ガス設備の切り替え工事や自治体が進める上下水道の更新など、仕事の範囲が幅広いのも特色です。
出典:国土交通省|持続可能な管路更新に資する官民連携について 【最終報告】
長期的に整備を進めるプロジェクトが多いため、安定して働き続けやすい職種といえます。
社会基盤を維持する意識がもてるので、責任が大きいぶん達成感も高まりやすいです。
年収アップを見込める
経験を積むほど給与水準が向上しやすい職種であり、資格を取得すると好条件で働ける場面が増えます。
以下の表は、管工事施工管理の経験年数ごとの年収イメージです。
| 経験年数 | 年収の目安 |
|---|---|
| 0〜3年 | 300〜400万円前後 |
| 4〜6年 | 400〜500万円前後 |
| 7〜10年 | 500〜600万円前後 |
| 10年以上 | 600万円以上を狙いやすい |
管工事施工管理技士の資格や1級を取得すれば、大手やサブコンへの転職が期待でき、給与水準も上を目指しやすくなります。
着実に実績を積みながらスキルを深めれば、より高い収入を見込みやすいでしょう。
関連記事
スキルアップすると転職が有利になる
管工事施工管理を続けると、現場調整や工程管理、配管材料の知識など多面的なスキルを身につけられます。
建築や電気と連携しながら仕事を進める機会もあるため、幅広い業種に通じるコミュニケーション能力が高まるでしょう。
ポイント
工事規模が大きいほど高度な技術が求められ、そこで得た経験は採用面で評価されやすいです。
有資格者や経験者の数が不足している企業も多く、転職市場で探される場面が多くなります。
活躍の場が広がることで、待遇アップやキャリア形成の選択肢も増えるでしょう。
将来性がある
配管技術はZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の導入など、最新の建築トレンドと強く結びついています。
近年は省エネや再生可能エネルギーに注目が集まっており、技術革新が進む領域でもあります。
以下の表は、よく聞かれる新しい技術の一例です。
| 最新技術 | 特徴 |
|---|---|
| ZEH | 断熱・省エネ設備で消費エネルギーを抑える設計 |
| 太陽光発電 | 屋根上にパネルを設置し、売電や自家消費を図る |
| 地中熱利用 | 地中の熱を熱源として空調や給湯に活かす |
| ヒートポンプ式 | 空気や水の温度差を利用して効率的に熱交換する |
こうした分野への適応が求められる場面では、管工事施工管理の知識がより重宝されます。
設備の新技術に触れられるだけでなく、建物のエコ性能を高める提案もできるようになるでしょう。
社会のニーズと建築技術が変化しても、配管工事の重要度が下がることは考えにくいため、先々の展望は明るいです。
参考記事:施工管理は将来性がある7つの理由|AIで仕事がなくなることは考えにくい
管工事施工管理のキャリアパス

管工事施工管理の主な就職先は以下のとおりです。
管工事施工管理の就職先
- 設備工事会社
- 正社員派遣
- サブコン
管工事施工管理でスキルアップしたあとのキャリア選択肢もあわせて紹介していきます。
設備工事会社で働く
設備工事会社で働くと、空調や給排水、衛生など幅広い分野の案件を経験できます。
官公庁案件や商業施設の設備改修など、多種多様な現場を担当しながら専門性を高められる点が特長です。
ポイント
社内で資格取得を支援している会社もあり、未経験からでも着実にステップを踏めるでしょう。
案件が豊富なため、スケジュール管理や工程調整を重ねるなかでリーダーシップを育める場面が多いです。
長く腰を据えて働くうちに、管理者や部門責任者へ昇進する道が開ける場合があります。
また、建築や電気サイドと連携する機会があるため、知識の幅が広がる点も魅力です。
正社員派遣で働く
正社員派遣は、派遣会社に正社員として採用され、別の企業の管工事現場で働く方法です。
給料や社会保険は派遣会社が整えるため、安定した処遇を受けながら複数の現場を経験しやすいです。
以下は正社員派遣の管工事施工管理で働くメリットです。
正社員派遣で働くメリット
- 多様な現場を回り、経験の幅が広がる
- 派遣会社が福利厚生を用意している場合が多い
- 勤務期間を柔軟に調整しやすい
- 研修が充実している派遣会社が多い
他社に派遣される立場上、配管や安全管理の研修をしっかり受けられる仕組みが整っているケースがあります。
新人や未経験者でも基礎知識を学びやすく、実務に入るハードルを下げやすいでしょう。
正社員派遣の施工管理については、施工管理の派遣で働く19のメリットと14のデメリット|やめとけと言われる理由も参考にしてみてください。
ワット・コンサルティングは優良派遣事業者
ワット・コンサルティングは優良派遣事業者認定を受けています。
この認定は、法令遵守や福利厚生の充実度、キャリア形成支援など厳しい基準をクリアした企業だけに与えられるものです。
そのため、安心して管工事施工管理の正社員派遣として働けます。
ワット・コンサルティングの特徴
- 定着率83.2%(業界平均70%)を実現
- 60日間の充実した研修カリキュラム
- 資格取得支援制度あり
- 社会保険完備で福利厚生も安心
転職先の候補として情報収集してみてください。
サブコンで働く
サブコンとは、ビルや施設の設備工事を一括で請け負う大手企業を指します。
配管や空調、衛生など専門性の高い業務が多く、実績を積んだ管工事施工管理には魅力的な就職先です。
中小の設備工事会社とサブコンの管工事施工管理の年収イメージは以下のとおりです。
| 雇用先 | 年収イメージ |
|---|---|
| 中小の設備工事会社 | 350万円〜700万円前後 |
| サブコン(大手) | 500万円〜1000万円以上の例もある |
中小規模の会社よりもサブコンは、大掛かりなプロジェクトを担当する分だけ給与水準が高くなっています。
設備工事会社や派遣などで経験を重ね、1級管工事施工管理技士を取得すると、サブコンに転職できる可能性があります。
大手企業で大規模案件に携わりたいなら、専門知識を深めてサブコンへのステップアップを目指しましょう。
参考記事:サブコンの施工管理に転職する方法|きついと言われる3つの理由
管工事施工管理でスキルアップした場合のキャリアの選択肢
管工事施工管理で積んだ実務は、さまざまな職域で活かされます。
以下の表は代表的なキャリアの例です。
| キャリア | 内容 |
|---|---|
| 設計・積算職 | 配管図面を作成したり、コスト見積を進めたりしてプロジェクトを支援する |
| 技術営業 | 施主や企業へ設備提案し、工事受注や予算調整を担う |
| 管理職・マネージャー | 組織を率いて人員配置や複数現場を調整し、経営面にも関与する場面が増える |
| 独立・フリーランス | 豊富な知識をもとに、自ら案件を受けながら自由な働き方を選ぶ |
現場で身に着けた工程調整や図面への理解は、設計や営業でも大きな強みになります。
将来は自ら事業を立ち上げる選択肢もあるため、長期的に視野を広げると仕事へのモチベーションが高まるでしょう。
管工事施工管理に向いている人の特徴

「自分は管工事施工管理に向いているのかな?」と気になると思います。
管工事施工管理に向いている人の特徴は以下のとおりです。
あなたがいくつ当てはまるかチェックしてみてください。
管工事施工管理に向いている人の特徴
- 空間把握力がある人
- 縁の下の力持ちタイプ
- 新しい技術を学ぶ好奇心がある
- チームワークが得意
1つずつ詳しく解説していきます。
関連記事:施工管理に向いている人の特徴11選|向いてない人の特徴4選も解説
空間把握力がある人
空間把握力がある人は管工事施工管理に向いています。
管工事施工管理では、壁や天井裏など見えない部分に通る配管を正確に把握する必要があります。
図面を見ながら配管ルートを考え、干渉しないように設計する場面が多いため、頭の中で三次元をイメージする力が欠かせません。
ポイント
地下ピットや梁が入り組んだ大きな施設では、他の設備と干渉しないための微調整が頻発します。
そうした環境でもスムーズに対処できる人は、現場で重宝されやすいです。
空間把握力を身につけるほど、見落としの少ない施工が可能になり、配管全体を安全かつ効率よく仕上げられます。
縁の下の力持ちタイプ
配管は建物の裏側に配置され、外からは見えにくいため、派手さを感じにくいかもしれません。
しかし、水道や空調が正常に機能しなければ暮らしの質は下がります。
そのため、人の快適さを裏から支える「縁の下の力持ちタイプ」管工事施工管理に向いています。
例えば、以下のような経験がある方は、管工事施工管理でやっていける可能性があるでしょう。
例
- 倉庫内作業で商品管理を完遂した
- 文化祭の準備係として裏方作業に取り組んだ
- 部活動の大会運営を支え、無事に大会を成功させた
このように前に出なくてもチームを支える役割にやりがいを感じるなら、管工事施工管理で貢献しやすいです。
新しい技術を学ぶ好奇心がある
新しい技術を学ぶ好奇心がある人も、管工事施工管理に向いています。
管工事分野では、新素材の配管や省エネ技術、BIM(建築情報モデル)などの進歩が加速しています。
設計図を三次元化して干渉を少なくする方法、溶接レスでの配管接合技術などが導入され、法規面でも環境基準が更新されやすいです。
ポイント
定期的に最新の知識へ触れ、積極的に取り入れようとする姿勢が求められます。
例えば、ヒートポンプ方式の普及に伴って冷媒配管の扱いが変わりつつあり、これらに対応するには常に勉強し続ける姿勢が欠かせません。
新しい技術を面白いと感じられる人は、日々成長を重ねやすいでしょう。
チームワークが得意
管工事施工管理は、職人や他の工種と共に施工を進める仕事です。
建築や電気の担当と連携し、配管が梁や配線と干渉しないよう話し合う場面も多いです。
周囲と相談しながら施工手順を整え、チームワークを活かせる人は、管工事施工管理に向いています。
以下は管工事未経験でも役立つチームワークの経験例です。
例
- 飲食店で他スタッフと連携してスムーズに料理を提供した
- チーム全体で試合を見直して成績を上げた
- 共同研究のプロジェクトでメンバーの負担を分散させた
こうした経験を活かせば、現場のコミュニケーションを円滑にし、工事全体をうまくまとめやすいです。
管工事施工管理に向いていない人の特徴
一方、管工事施工管理に向いていない人の特徴は以下のとおりです。
| 特徴 | 解説 |
|---|---|
| 協調性を発揮したくない人 | 他の工種や職人と連携せずに進めると、施工が滞りやすい |
| 屋外や高所での業務を避けたい人 | 配管ルートによっては天井裏や外部足場での点検が必要な場面がある |
| 新しい技術や法改正に興味がない人 | 常に改良が進む設備工事に対応しないと、知識不足が生じやすい |
| 予測外の変更を嫌う人 | 工程変更や突発的なトラブルに対応する場面が多い |
管工事施工管理は、柔軟なやり取りや技術への関心を保てる人に向いています。
上記の項目が強く当てはまるなら、適合度が低いかもしれません。
未経験から管工事施工管理に転職するとき失敗を防ぐコツ
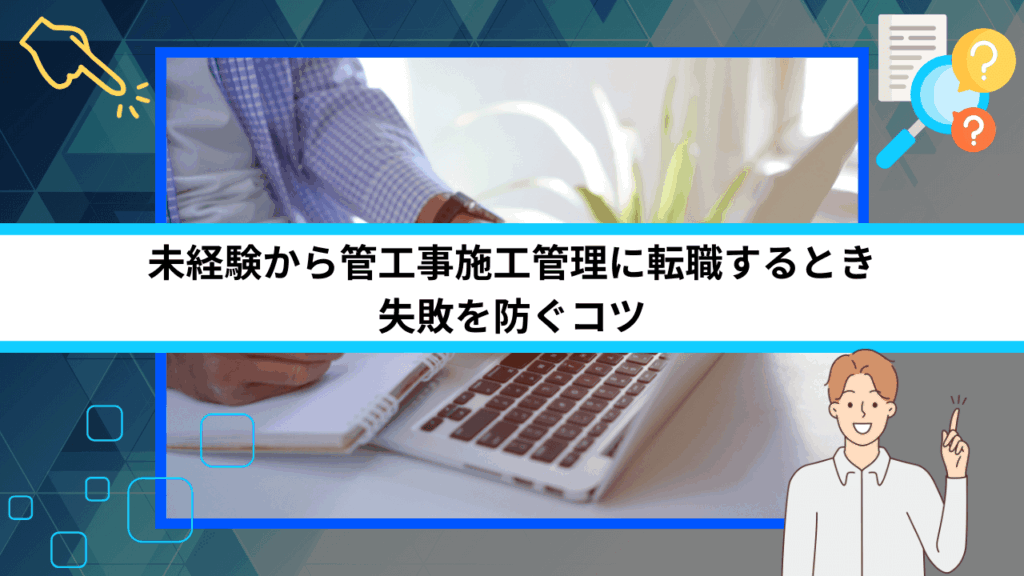
転職の失敗を防ぐコツ
- 新人研修が充実している企業を選ぶ
- 志望動機を固めておく
- 管工事施工管理に活かせる経験をアピールする
- 応募する企業のキャリアプランを調べておく
1つずつ解説していくので、スムーズに管工事施工管理のキャリアを始めたい方は実践していきましょう。
参考記事:未経験でも施工管理に転職できる!転職に失敗しない9ステップ
新人研修が充実している企業を選ぶ
未経験から管工事施工管理に転職する際は、新人研修が充実している企業を選ぶのがおすすめです。
新人研修が整っていない環境だと、配管作業や工程管理などの基礎がわからなくなり、現場で戸惑うリスクが高まります。
注意
特に、管工事施工管理は安全確認や品質チェックなど作業が多いため、未経験者が手探り状態で現場に出るのは不安が大きいです。
2ヶ月ほどの新人研修が設けられていれば、配管図の読み方や材料の特徴、安全管理の方法などを一通り学びやすくなります。
研修によって図面と実際の現場を結びつける力も身につきやすく、現場配属後もスムーズに動けるでしょう。
求人サイトや会社のホームページを確認して、研修期間の長さや研修内容が明示されている企業を選ぶと安心です。
ワット・コンサルティングの新人研修は業界トップクラス
ワット・コンサルティングでは、60日間の体系的な研修プログラムを用意しています。
管工事施工管理の基礎知識から現場での実践的なノウハウまで、段階的に学べるカリキュラムが特徴です。
研修内容の一例
- 配管図面の読み方・作成方法
- 管材料の種類と特性の理解
- 施工管理に必要な安全対策
- 工程管理・原価管理の基礎
- 現場でのコミュニケーション術
未経験者でも確実にスキルを身につけられるよう、経験豊富な講師陣が丁寧に指導します。
研修終了後も現場でのフォロー体制が整っているため、着実にキャリアを積み上げられる環境です。
安心して働ける知識・スキルを身につけたい方は、ワット・コンサルティングの求人もチェックしてみてください。
志望動機を固めておく
未経験者は採用担当から「なぜ管工事施工管理を志望したのか」と問われる場面が多いです。
はっきりと答えられないと、入社後にすぐ辞める恐れがあると思われる可能性が高まります。
そこで、筋道の通った志望動機を用意しておくと印象が良くなります。
以下は志望動機の型です。
志望動機の型
- 企業を志望する理由
- 管工事施工管理を選んだ理由
- これまで身に付けた強み
- 入社後の目標や資格取得への意欲
志望動機の例文は以下のとおりです。
志望動機の例文
貴社が挑戦的な設備案件を積極的に受注している点に魅力を感じ、管工事施工管理として新しい技術に関わりたいと思いました。
入社前から専門書を読み進め、図面の基礎や配管材料の特徴を自主的に学習しています。
前職では商品ディスプレイを任され、売上や在庫状況を分析して改善策を提案してきました。
そういった実行力や計画性を活かし、配管ルートの最適化や工程調整でも成果を出したいです。
将来的には1級管工事施工管理技士の取得を視野に入れ、貴社の大規模案件をより安全で効率的に進める役割を担うことを目標にしています。
具体的なエピソードを交えて、自身の強みが配管工事や施工管理にどう役立つかを示すと納得感が増します。
参考記事:施工管理が未経験の人の志望動機の作り方と例文【研修で会社を選ぶ】
管工事施工管理に活かせる経験をアピールする
未経験でも、これまでの仕事やアルバイトで身につけた経験が管工事施工管理に結びつく場合があります。
接客業ならコミュニケーションを学び、倉庫業務なら計画性や在庫管理を磨ける場面があるでしょう。
以下は活かせるスキルをまとめた例です。
過去の仕事内容を振り返り、どのように工事の現場で役立つかを具体的に説明すると採用担当への説得力が増します。
アピールの例文
前職ではコンビニの深夜シフトで責任者を任されていました。
商品の納品管理や品出しのタイミングを調整するなかで、計画立案やスタッフとの連携を学びました。
管工事施工管理では、職人の段取りや配管材料の発注など、似たような調整作業が多いと思います。
日ごろから周囲とコミュニケーションをとりながら進捗を管理していた経験を活かし、工事の安全と品質を同時に守りたいです。
アピールについては、施工管理の自己PRの書き方|例文も紹介も参考にしてみてください。
応募する企業のキャリアプランを調べておく
応募先がどのようなキャリアパスを想定しているかを理解し、自分の将来像と重ねると採用される確率が高まります。
管工事施工管理は資格取得と経験によって任される範囲が変わるため、企業が用意しているキャリアプランを把握して面接に臨むことが大切です。
面接官に「入社後の将来像」を明確に伝えると「この人は自社で長く活躍してくれそうだ」と思ってもらいやすいでしょう。
企業のキャリアプランを調べる方法
- 企業の公式サイトや採用ページを読んで方針を確認する
- 転職サイトや口コミサイトの社員インタビューを探す
- 会社説明会や面談で先輩社員や採用担当に直接尋ねる
具体的には、以下のようにキャリアプランを伝えてみてください。
入社後の将来像を伝える例文
入社後はまず現場で配管と施工手順を学び、2年以内に2級管工事施工管理技士の合格を目指したいです。
貴社では設備改修や大規模案件にも力を入れていると拝見しましたので、そこで経験を積みながら5年後には1級資格の取得を狙い、大型プロジェクトをまとめられる存在を目標にしています。
ゆくゆくは後輩の育成にも関わり、職場全体の技能向上に貢献したいです。
そういった長期的な視点で努力を続けます。
キャリアプランについては、未経験者向け!施工管理の10年後のキャリアプラン|面接の例文も紹介も参考にしてみてください。
管工事施工管理技士とは【資格の解説】
管工事施工管理技士は、配管工事の工程管理や品質管理、安全管理などを担う国家資格です。
建物を機能させる配管の責任者になれるため、建設業界での評価が高く、キャリアアップにもつながります。
以下では1級と2級の違い、合格率や試験の難易度、受験資格を順に見ていきましょう。
1級管工事施工管理技士と2級管工事施工管理技士の違い
管工事施工管理技士には1級と2級があり、担当できる工事の規模や役割に違いがあります。
以下の表は、1級と2級がそれぞれ担える業務の範囲をまとめたものです。
1級を取得すると、監理技術者になれる点が特徴です。
監理技術者は高額工事の現場で安全管理や品質管理を統括し、チームを主導します。
一方、2級は主任技術者として現場の配管作業を管理し、中小規模の工事をまとめる立場に立ちやすいです。
経営事項審査でも1級は5点、2級は2点加点されるため、企業が1級保持者を求める場面も多いです。
資格を活用して転職や昇給を狙うなら、1級を目指すメリットは大きいでしょう。
管工事施工管理技士の合格率や試験の難易度
管工事施工管理技士の試験は、1級と2級いずれも第一次検定と第二次検定に分かれます。
過去3年の平均合格率を見てみると、以下のような傾向があります。
| 資格 | 第一次検定の合格率 | 第二次検定の合格率 |
|---|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 33.9% | 63.8% |
| 2級管工事施工管理技士 | 56.2% | 61.5% |
参考:国土交通省
- 令和4年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級) 「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
- 令和4年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定 「第一次検定」合格者の発表
- 令和3年度管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
- 令和3年度 1級管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定「第一次検定」合格者の発表
- 令和2年度 管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定(1級・2級)合格者の発表
1級は第一次検定が難しく、第二次検定の方が合格しやすい傾向です。
いずれも実務経験を問う内容や、施工計画の理解度を問う問題があります。
市販のテキストや通信講座などを活用して対策を進めると、合格への可能性が高まります。
管工事施工管理技士の受験資格
管工事施工管理技士を受けるには、学歴や実務経験などの要件が定められています。
令和6年度からの改正で、第一次検定の受験は1級が19歳以上、2級が17歳以上なら誰でも挑戦できるようになりました。
出典:国土交通省|令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります
未経験でも最初から1級の一次検定を受けて、最短5年で1級を取得する道を選ぶことが可能です。
一方、2級を経由して1級を目指す場合は、最短8年ほどかかるため、特に理由がなければ1級から受験する方がスピーディーにキャリアアップしやすいでしょう。
ただし、二次検定には実務経験が必要です。
1級は合格後の実務期間が5年以上必要になるなど、細かい基準があるため、時間の見通しを立てて計画的に準備を進めることが大切です。
管工事施工管理技士の受験資格については、令和6年度から施工管理技士試験の受験資格が改正される|3つの注意点も解説も参考にしてみてください。
管工事施工管理技士の勉強方法
管工事施工管理技士の勉強方法は、大きく分けて独学・新人研修・通信講座の3つがあります。
| 勉強方法 | 特長 |
|---|---|
| 独学 | コストを抑えられるがモチベーション管理が課題 |
| 新人研修 | 給料をもらいながら勉強できる |
| 通信講座 | サポート・教材が充実し、未経験者でも学びやすい |
自分の状況や予算に合わせて勉強方法を選んでみてください。
資格取得支援制度がある会社に転職するのがおすすめ
資格取得支援制度がある会社へ転職すると、働きながら管工事施工管理技士を目指しやすいです。
実務で配管図を扱いつつ、必要な理論を研修で学べば、試験対策と仕事の両方を進められます。
例
転職先が受験料や教材費を一部負担してくれるケースもあり、経済的な不安が減る点は大きなメリットです。
現場で経験を積みながら知識を深められるため、勉強内容が実務と結びつきやすく、理解が定着しやすいでしょう。
既存の社員からノウハウを教われば、過去問や参考書で知識を固めるだけでなく、実際の工程管理や安全管理のコツも身につきます。
会社のサポート体制を確認し、資格取得に向けて動きやすい環境を選ぶと、スムーズにステップアップしやすいです。
ワット・コンサルティングはe-ラーニングで学べる
ワット・コンサルティングでは、管工事施工管理技士の資格取得に向けたe-ラーニングシステムを導入しています。
いつでもどこでも自分のペースで学習できるため、仕事と両立しながら効率的に資格取得を目指せます。
e-ラーニングの特長
- スマートフォンやタブレットでも学習可能
- 過去問題を繰り返し解ける演習機能
- 苦手分野を分析して効率的に学習できる
- 資格取得に向けた学習進捗管理機能
また、資格取得時には奨励金制度もあり、キャリアアップを会社全体でバックアップしています。
管工事施工管理技士の資格を取得していきたい方は、ワット・コンサルティングの求人もチェックしてみてください。
管工事施工管理技士に合格するコツ
管工事施工管理技士の試験対策では、まずテキストや参考書で全体をざっと読み、大まかな範囲と重要項目を把握するのがコツです。
その後は過去問を何度も解き、出題傾向や苦手分野を見つけましょう。
施工管理試験は過去に出題された問題が出題されることが多いです。
過去5年分を最低3周ほど解くと合格率が高まります。
スキマ時間を活かすならアプリ学習が効果的です。
スマートフォンで過去問を解けば、通勤や休憩中にも問題演習が進められます。
記述式の問題は施工計画や工程管理の流れを理解しないと解答できないため、暗記だけでなく全体像を頭に描きながら勉強を進めましょう。
復習の際は苦手部分をノートにまとめ、徐々に精度を上げると得点アップが期待できます。
参考記事:1級2級管工事施工管理技士の試験勉強におすすめのアプリ16選
管工事施工管理技士の勉強時間の目安
管工事施工管理技士は、最低でも3ヶ月ほどの勉強時間を確保しましょう。
勉強時間の目安は、学習ペースや初期知識によって変わりますが、大まかな指標は以下のとおりです。
| 期間 | 学習目安 |
|---|---|
| 1〜2週目 | 基礎固め(テキスト通読・用語整理) |
| 3〜4週目 | 過去問演習(5年分を1周) |
| 2ヶ月目 | テキスト再確認+過去問2周目 |
| 3ヶ月目前半 | 重点強化+過去問3周目 |
| 3ヶ月目後半 | 模擬試験形式で総仕上げ |
勉強時間を確保できない場合は、もう少し早くから勉強を始めるのがおすすめです。
管工事施工管理についてよくある質問
最後に、管工事施工管理についてよくある質問に答えていきます。
管工事施工管理と他の施工管理の違いは?
管工事施工管理以外には以下のような施工管理があります。
管工事施工管理は、冷暖房や給排水、空調など配管を通じて人々の暮らしや設備環境を支える仕事です。
| 種類 | 主な対象 |
|---|---|
| 管工事施工管理 | 配管設備(冷暖房・空調・給排水など) |
| 建築施工管理 | 建物全体の構造や仕上げ |
| 土木施工管理 | 道路・橋梁・河川・トンネルなどのインフラ |
| 造園施工管理 | 庭園や公園、緑地環境のデザイン・整備 |
| 電気工事施工管理 | 建物の電気配線や照明設備 |
| 電気通信工事施工管理 | ケーブル・通信設備の設置や調整 |
他の施工管理については、以下の記事も参考にしてみてください。
参考記事
未経験でも管工事施工管理で本当にやっていける?
きちんとスキルアップしていけば、未経験でも管工事施工管理で活躍していける可能性があります。
入社直後は資材運搬や簡単な図面確認などからスタートします。先輩の指導を受けながら工程調整や施工図の理解を深める流れが一般的です。
ポイント
安全管理や品質管理などの基本を学び、少しずつ配管ルートの検討や職人への指示を任されるようになるケースが多いです。
資格試験の学科内容は現場の実務とも密接につながっており、実際に作業を見ながらテキストで復習すると知識が定着します。
長期間の研修がある企業や、上司や同僚が新人をフォローする文化が根づいている組織を選ぶと、未経験でもスムーズに成長できる可能性が高まります。
業務をこなすうちに段取り力やトラブル対応力が身につき、自信をもって配管計画や工事進捗を管理できるようになります。
管工事施工管理としてスキルアップしていくコツは?
まずは、新人研修が充実している企業へ転職することがスキルアップの近道です。
実務をこなしながら知識を身につける環境を得やすいからです。
現場監督の基礎や配管材料の種類を研修で学んだうえで、先輩と一緒に設備点検や職人との打ち合わせを経験すると、座学と実践が結びつきます。
研修後も継続的にスキルを磨くなら、以下のポイントが参考になります。
スキルアップのポイント
- 現場の写真を撮り、問題点や改善策を考察
- 1級管工事施工管理技士の勉強を始める
- 社内外の勉強会やセミナーに参加する
- 他の工種や部署との連携を積極的に図る
管工事の世界は新素材や省エネ技術が登場する頻度が高く、学ぶほど業務の幅が広がります。
実務と資格の双方で段階的にスキルアップを目指すと、効率よくキャリアを高められます。
管工事施工管理技士と併せて取得すると良い資格は?
管工事施工管理技士とあわせて勉強すると、業務範囲が広がる資格がいくつか存在します。
以下の表は代表的な例で、それぞれ管工事に関連する分野を補強する資格です。
| 資格名 | 特長 |
|---|---|
| 浄化槽設備士 | し尿や雑排水を浄化する設備を扱い、営業所に配置必須となるケースが多い |
| 給水装置工事主任技術者 | 給水管を設置・修繕する際に必要で、管工事の延長線上で取得しやすい |
| 上下水道部門の技術士 | 流体力学や水質管理など高度な知識を扱い、大規模上下水道プロジェクトに強い |
浄化槽設備士は、し尿や生活排水を浄化する設備の管理に携わる場面で必須とされています。
給水装置工事主任技術者は給水管工事を施工する際の主任技術者として重要です。
上下水道部門の技術士は、国家試験の中でも高レベルの専門資格であり、大型の上下水道計画やインフラ整備をリードする立場を目指せます。
管工事施工管理技士との相乗効果で業務範囲を広げたい人は、自分がかかわりたい分野に合わせてこれらの資格の取得を検討すると良いでしょう。
まとめ
最後にもう一度「管工事施工管理のきついところ」と「メリット」をまとめておきます。
| きついところ | ・狭い配管スペースでの施工調整 ・水、ガスなど漏れやすいリスク管理 ・配管材料の種類や規格が多彩 ・隠蔽部分の工事なのでミスできない ・電気、建築側との連携が必要 |
| メリット | ・「快適さ」に貢献できる ・インフラに関わる仕事で需要が安定している ・年収アップを見込める ・スキルアップすると転職が有利になる ・将来性がある |
さっそく管工事施工管理に向けて転職活動を始めていきましょう。
未経験から管工事施工管理に転職するときは、以下のポイントに注意すると失敗を防げます。
転職の失敗を防ぐコツ
- 新人研修が充実している企業を選ぶ
- 志望動機を固めておく
- 管工事施工管理に活かせる経験をアピールする
- 応募する企業のキャリアプランを調べておく
くりかえしですが、ワット・コンサルティングでも、管工事施工管理の未経験者さんを募集しています。
60日間の研修制度があるため、管工事施工管理の基礎をしっかり身につけてから働けます。
ワット・コンサルティングの強み
- 定着率83.2%(業界平均は約70%)
- 未経験者の採用率80%
- 累計1500名の未経験者を育成
- 社会保険完備+資格取得奨励金あり
転職先の候補に加えてみてください。
あなたの転職活動の参考になればうれしいです!