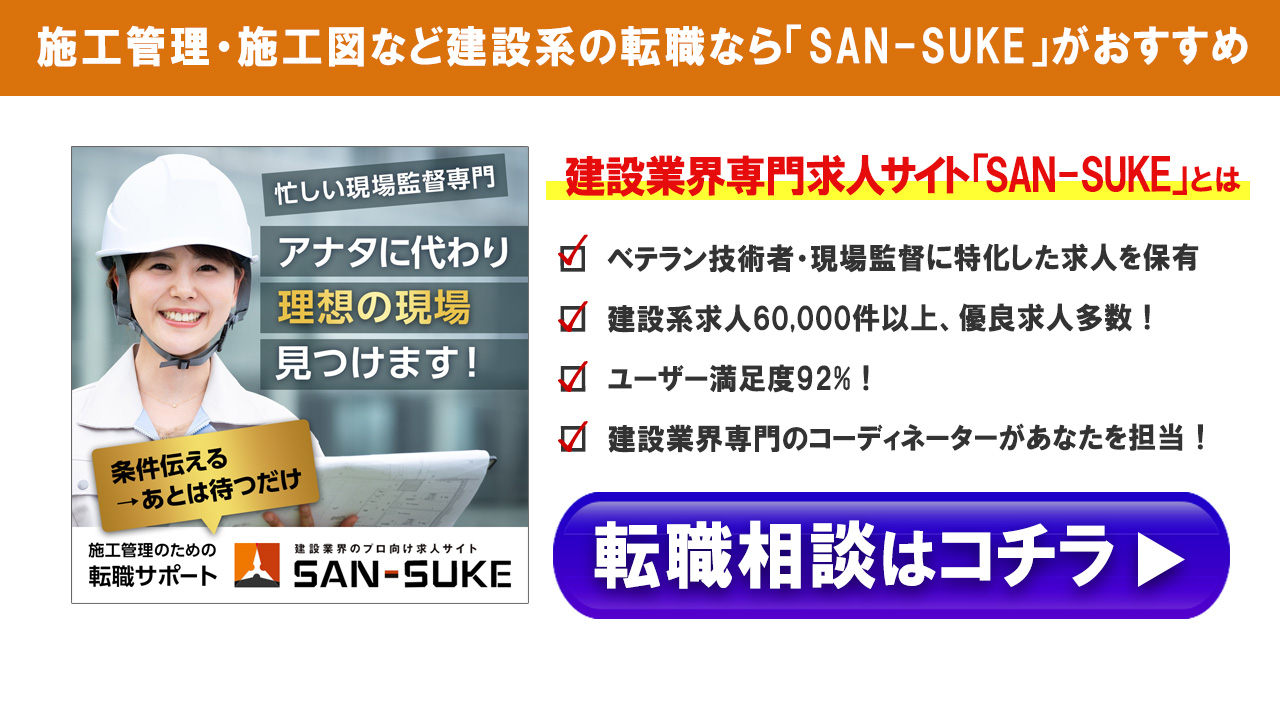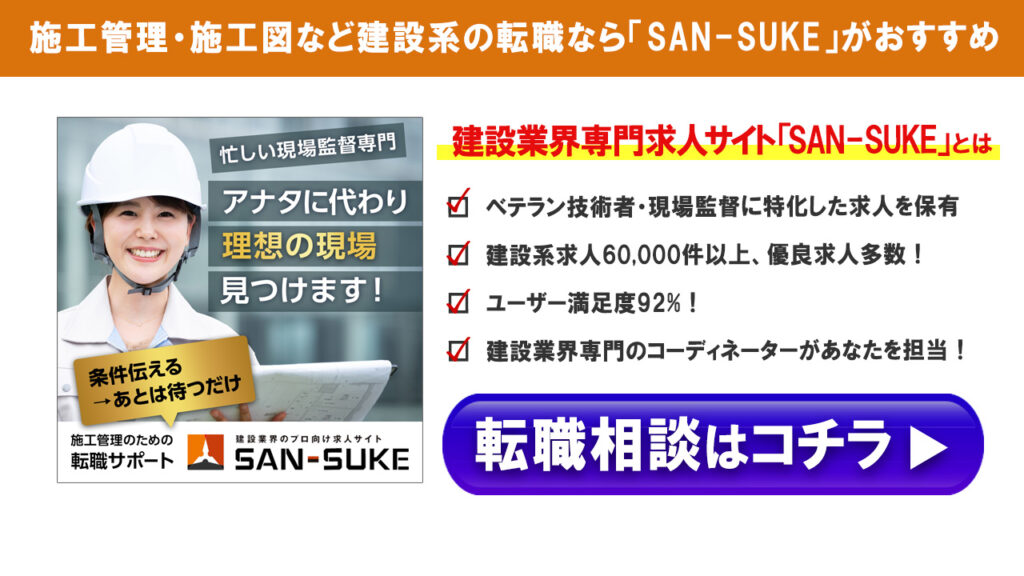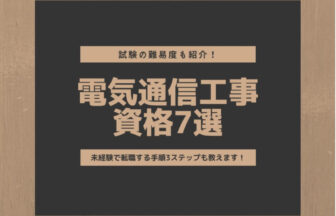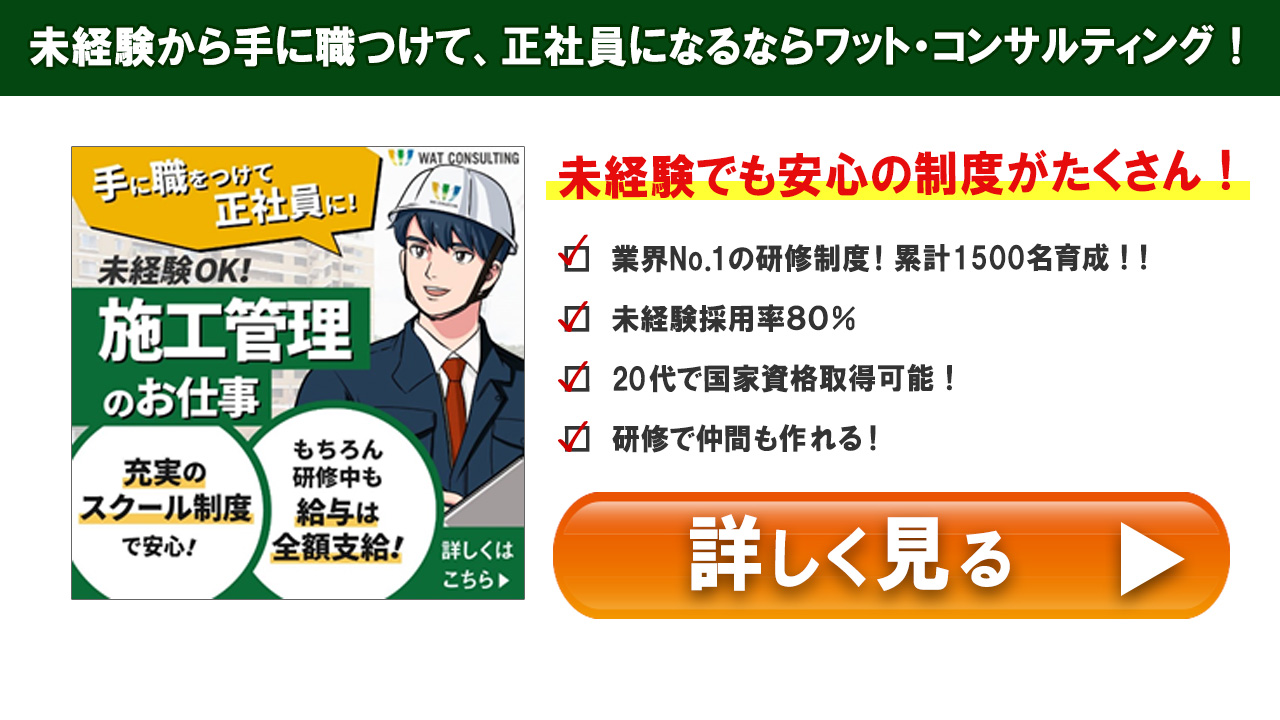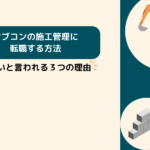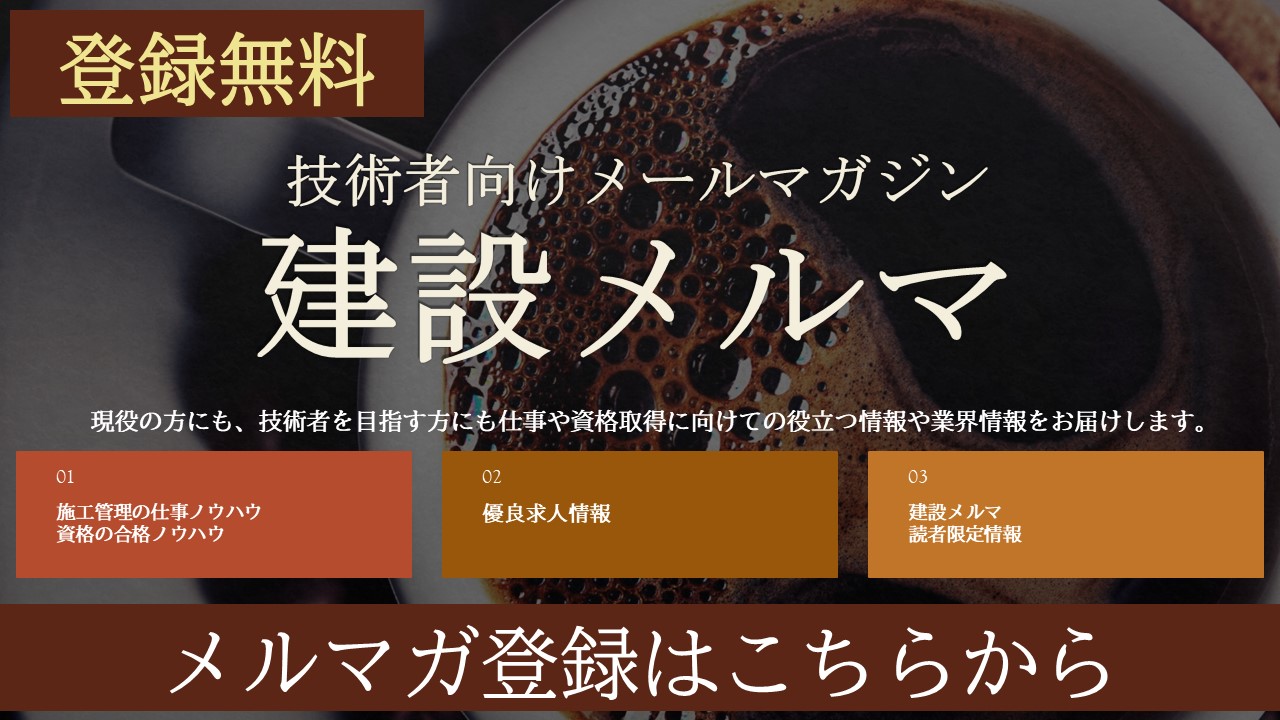合格率はどれくらいなの?
資格をとりたいんだけど、仕事が忙しいから勉強できるか不安…
勉強のコツとかも教えてほしいな。
キャリアアップ、収入アップしていきたい!
こういった疑問や不安に応える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- 2級電気工事施工管理技士とは?
- 合格率から見る2級電気工事施工管理技士の難易度
- 2級電気工事施工管理技士の試験問題
- 2級電気工事施工管理技士の受験資格
- 勉強方法や勉強時間
- 2級電気工事施工管理技士と併せて取得したい資格
私たちワット・コンサルティングは、施工管理の転職サポートを行う会社です。
この記事では、2級電気工事施工管理技士の難易度を中心に解説していきます。
結論、計画的に正しく勉強すれば合格できる試験です。
勉強のコツも解説するので、2級電気工事施工管理技士を取得したい人は最後まで読んでみてください!
「前置きはいいから、早く試験の難易度を教えて!」という人は、2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度をクリックすると、該当箇所にジャンプできますよ!
目次
2級電気工事施工管理技士とは?


2級電気工事施工管理技士とは、建築基準法で規定された電気工事の安全管理・工程管理・品質管理・原価管理などの施工管理業務を行う国家資格です。
建設現場の電気工事には電気工事施工管理技士を配置しなければならないと建設業法で定められているので、重要な資格です。
電気工事施工管理技士に合格すると国土交通省の署名入りの合格証書をもらえます。
主宰は一般財団法人建設業振興基金です。
2級電気工事施工管理技士の仕事内容
2級電気工事施工管理技士は、下記のような電気工事の現場監督を行います。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
具体的な業務内容は下記のとおり。
- 工程管理:施主との契約に合った工事ができているか、スケジュール管理
- 安全管理:現場作業員の安全を守るための管理
- 品質管理:部材の規格や寸法の管理、建設物の品質の管理
- 原価管理:工事の原価計算をして利益を管理
- 出来形管理:施主の希望する規格基準に限りなく近い精度で完成させるための管理
- 行政への申請
施工管理の仕事内容は、電気工事の現場監督(施工管理)の仕事内容や給料【未経験の会社選び】も参考にどうぞ。
2級電気工事施工管理技士を取得する3つのメリット

結論、下記のメリットがあります。
- 年収が上がりやすい
- 転職が有利になる
- 計装士試験の学科Bが免除される
前述のとおり、電気工事の現場には電気工事施工管理技士を配置しなければいけません。
つまり、電気工事施工管理技士がいないと工事を受注できないのです。
会社にとってなくてはならない存在になれるため、年収は上がりやすいです。
もちろんどの会社も電気工事施工管理技士を採用したいため、転職も有利になります。
また、計装士の学科Bが免除されるため、資格を取得しやすいのもメリットです。
※計装士については、計装士の合格率や難易度【1級と2級の試験内容や受験資格も解説】にまとめています。
電気工事施工管理技士の1級と2級の違い

簡単にいうと、1級と2級では取り扱える工事の規模が違います。
- 1級電気工事施工管理技士:大規模電気工事の取り扱いが可能
- 2級電気工事施工管理技士:中小規模の電気工事の取り扱いまでが可能
具体的な違いは下記のとおりです。
| 1級電気工事施工管理技士 | 2級電気工事施工管理技士 | |
| 一般建設業の専任技術者 | 〇 | 〇 |
| 主任技術者 | 〇 | 〇 |
| 特定建設業の専任技術者 | 〇 | × |
| 監理技術者 | 〇 | × |
1級電気工事施工管理技士はすべての工事を取り扱えますが、2級は特定建設業の専任技術者と監理技術者になれません。
特定建設業とは、下請に出す工事の総額が4500万円以上、建築一式工事の総額が7000万円以上の工事のことです。
監理技術者とは、特定建設業の工事現場に専任で配置される技術者のことです。
1級電気工事施工管理技士は監理技術者が必要な大規模な電気工事を請け負えるため、2級より転職に有利です。
※もちろん2級電気工事施工管理技士も有利ですが。
2級よりも1級の方が年収が高くなりやすいですし、大手企業に転職できる可能性が高くなります。
電気工事業者は常勤で雇用している施工管理技士によって点数が与えられます。
この点数は「経営事項審査」といい、下記が加算されます。
- 2級の施工管理技士:2点
- 1級の施工管理技士:5点
- 監理技術者講習を受けたらさらに1点追加
経営事項審査の点数が高い建設会社は公共工事の受注を受けやすくなるなど大きなメリットがあります。
1級電気工事施工管理技士を雇用すると企業にもメリットがあるから、資格手当などがもらえて年収が上がるイメージです。
ちなみに1級電気工事施工管理技士については、1級電気工事施工管理技士の合格率や難易度!効率的な勉強方法にまとめています。
2級電気工事施工管理技士補を取得するメリット
2021年の試験から、新たに「技士補」が追加されました。
文字どおり「施工管理技士を補佐する資格」です。
従来は第一次検定に合格しても、第二次検定に合格しないと資格が付与されませんでした。
第一次検定合格の有効期限は1年なので、翌年の試験でも不合格だと、また第二次検定からやり直しです。
でも2021年からは、下記の結果でも「技士補」の資格が与えられるようになりました。
- 第一次検定:合格→技士補の資格が与えられる
- 第二次検定:不合格
技士補になれば、以後、第二次検定のみに合格すれば2級電気工事施工管理技士を取得できます。
勉強のモチベーションも維持できる感じですね。
技士補については、技士補はいつから?【答え:2021年から!どんな資格かも解説】にまとめています。
電気工事施工管理技士の就職先
電気工事施工管理技士の主な就職先は下記などです。
- 電気工事会社
- 建設会社
- プラント施工会社
- ハウスメーカー
特に1級電気工事施工管理技士は大型工事の施工管理ができるため、大手企業への就職・転職も可能です。
最初は中小の電気工事会社で実務経験を積んで、電気工事施工管理技士の資格を取得してから大手企業へ転職する人もいます。
2級電気工事施工管理技士の年収や給料【取得するメリットが大きい】

2級電気工事施工管理技士の平均年収は450万円くらいです。
前述のとおり年収が上がりやすいため、取得するメリットは大きいでしょう。
2級より1級の方が年収が高く、勤務する会社が大手企業であれば年収が高くなります。
- 2級電気工事施工管理技士で中小企業に勤めている:平均年収は400万~500万円くらい
- 1級電気工事施工管理技士で大手企業に勤めている:年収700万円以上の人もいる
特に発電所、プラント施工などの大規模工事を行う電気工事施工管理技士の年収は高くなります。
稼ぎたい人は1級を目指すことと、大手企業への転職を目指しましょう。
電気工事施工管理技士を取得すると資格手当がもらえる会社が多いです。
資格手当の相場は下記のとおり。
- 1級:4000〜2万円/月
- 2級:3500〜1万円/月
「電気工事がなくなる」ということは考えにくいため、今後も長く稼げる資格といえます。
電気工事施工管理技士の年収については、電気工事施工管理技士の年収【給料を上げる2つの方法】も参考にどうぞ。
電気工事施工管理技士に向いている人の特徴
電気工事施工管理技士に向いている人の特徴は、下記のとおりです。
- トラブルが起きても冷静に判断を下せる人
- 安全な現場環境をつくれる人
- 施主や業者、現場の職人さんと良好な人間関係を築ける人
- リーダーシップのある人
- スケジュール管理能力が高い人
- 数字に強い人
電気工事施工管理技士は、現場監督として工事すべての総指揮をとる仕事です。
工事全体を把握して、的確な指示を出さなければいけません。
もちろん無事故で工事を終わらせるのは使命です。
他にも下記のような力が必要です。
- 工期を守るのもプロとして必要なので、優れたスケジュール管理能力が必要
- 原価管理があるので数字に強くないといけない
- 最適な工事原価で最高の建築物を造る力が必要
施工管理に向いてる人の特徴は、施工管理に向いてる人の特徴30選【未経験で就職する方法も解説】にもまとめてます。
2級電気工事施工管理技士の合格率から見る難易度


結論、合格率は下記のとおりです。
※試験は第一次検定と第二次検定があります。
| 年度 | 第一次検定 | 第二次検定 |
| 平成23年 | 55.1% | 47.9% |
| 平成24年 | 60.4% | 41.6% |
| 平成25年 | 67.1% | 44.9% |
| 平成26年 | 54.4% | 39% |
| 平成27年 | 55.2% | 40.4% |
| 平成28年 | 58.7% | 41.6% |
| 平成29年 | 62.8% | 40% |
| 平成30年 | 61.6% | 43.2% |
| 令和元年 | 58.7% | 45.4% |
| 令和2年 | 58.5% | 64.1% |
| 令和3年 | 56.2% | 58.8% |
参考:CIC日本建設情報センター「施工管理技士の合格率[全国平均]」/令和3年度 建築・電気工事施工管理技術検定(1級・2級)「第一次検定(2級後期)」及び「第二次検定」合格者の発表
過去11年の合格率の平均値は下記のとおりです。
- 第一次検定:59%
- 第二次検定:46.1%
- 合計の合格率:27.2%
合格率が約27%なので、難易度は高めといえるでしょう。
2級電気工事施工管理技士は第二次検定の方が合格率が低いです。
後述しますが、第二次検定では記述式問題が出るため難しい試験。
また、試験を受験する人の多くは、仕事をしながら勉強することになります。
「仕事をしながら勉強を時間を確保できない…」という人が多いことから、不合格になってしまう人も多いです。
いかに勉強時間を確保できるかが、試験の難易度を左右します。※勉強のコツも後述します。
2級電気工事施工管理技士の試験問題
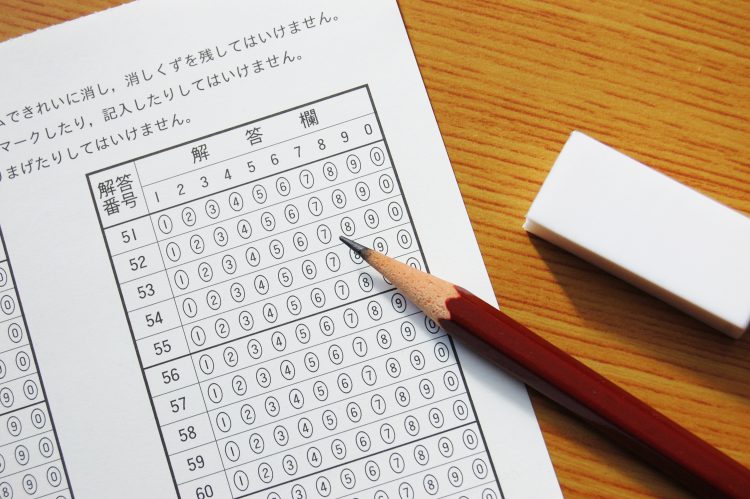

ここからは、第一次検定と第二次検定の試験問題をそれぞれ見ていきましょう。
第一次検定の試験問題
第一次検定の試験時間は2時間30分で、問題は下記のとおり。
| 科目 | 解答方式 | 出題数 |
| 電気工学(電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学、建築学など) | 四肢択一 | 12問中8問に解答 |
| 電気設備(発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など) | 四肢択一 | 19問中10問に解答 |
| 関連分野 | 四肢択一 | 6問中3問に解答 |
| 必須1問 | ||
| 施工管理法(能力問題) | 五肢択一 | 必須4問 |
| 施工管理法(施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など) | 四肢択一 | 10問中6問に解答 |
| 法規 | 四肢択一 | 12問中8問に解答 |
すべてマークシートです。
選択問題が多いため、ある程度は得意ジャンルを絞って得点できるでしょう。
施工管理法の能力問題のみ「五肢択一×必須問題」なので、重点的に勉強するのがおすすめです。
第二次検定の試験問題
第二次検定は2時間で下記が出題されます。
| 科目 | 解答方式 | 出題数 |
| 施工管理法(能力問題) | 記述式 | 必須3問 |
| 施工管理法 | 四肢択一 | 必須2問 |
すべて必須問題なので、苦手ジャンルを避けることができません。
鬼門は記述式問題です。
下記など、あなたの施工経験を記述していきます。
- 工事名
- 工事場所
- 電気工事の概要
- 工期
- この電気工事でのあなたの立場
- あなたが担当した業務の内容
- あなたが留意した事項と理由
- あなたがとった対策や措置
また、技術的な内容に解答する記述問題も出題されます。
第二次検定の施工経験記述の出題傾向
第二次検定の施工記述問題のテーマは下記の2つです。
- 安全管理
- 工程管理
1年おきにテーマが変わる傾向です。
- 2019年:安全管理
- 2020年:工程管理
- 2021年:安全管理
- 2022年:工程管理
試験前に、安全管理と工程管理で文章を作っておきましょう。
試験本番で文章を考えている時間はありません。
2級電気工事施工管理技士の試験内容

2級電気工事施工管理技士の試験概要は下記のとおりです。
| 試験地 |
|
| 願書申込 |
|
| 試験時期 |
|
| 合格発表 |
|
| 受験手数料 |
|
| 申込方法 |
|
2級電気工事施工管理技士の合格基準
ちなみに、2級電気工事施工管理技士の合格基準は下記のとおりです。
| 第一次検定 | 60%以上の正答※24問以上/40問に正答すれば合格 |
| 第二次検定 | 60%以上の正答 |
4割は間違えられる試験です。
ちなみに、第二次検定の記述式問題の採点基準は公表されていません。
2級電気工事施工管理技士に合格したら免状申請が必要
試験に合格したら、2級電気工事施工管理技士の免状を申請しましょう。
申請手続きをすると、国土交通省から合格証明書が発行されます。
2級電気工事施工管理技士に合格すると合格通知書が届くので、その合格通知書に書かれている手順で手続きを進めればOKです。
2級電気工事施工管理技士の受験資格


2級電気工事施工管理技士の受験資格は大きく4つの区分に分かれています。
- 最終学歴と実務経験による受験資格
- 第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状の交付を受けた人
- 第一種電気工事士免状の交付を受けた人
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた人
こちらも、4つの受験資格のどれかを満たしていること、かつ、1年以上の指導監督的実務経験年数が必要です。
ちなみに、第一次検定のみの受験であれば、満17歳以上で受験できます。
詳しい受験資格については、一般財団法人建設業振興基金のサイトに記載されているのでチェックしてみてください。
2級電気工事施工管理技士の実務経験に認められるもの
2級電気工事施工管理技士の実務経験に認められるものは、下記があります。
| 工事種別 | 電気工事の内容 |
| 構内電気設備工事 |
|
| 発電設備工事 |
|
| 変電設備工事 |
|
| 送配電線工事 |
|
| 引込線工事 | 引込線工事など |
| 照明設備工事 |
|
| 信号設備工事 |
|
| 電車線工事 | 鉄道に伴う、
|
| ネオン装置工事 | ネオン装置工事など |
| 上記の増改設工事も実務経験に含まれる | |
また、業務としては下記が実務経験に該当します。
- 施工管理
- 設計監理
- 施工監督
第一次検定が免除になるケース
下記に該当する場合は、第一次検定が免除されます。※第二次検定の受験だけでOK
- 第一次検定に合格している人(技士補)
- 電気・電子部門、建設部門の技術士で2級電気工事施工管理技士の第一次検定の受験資格がある人
【当然ですが】電気工事施工管理技士の実務経験の虚偽申告はNG
当たり前ですが、虚偽の実務経験を申告して電気工事施工管理技士を受験するのはNGです。
具体的には、下記のようなペナルティが予想されます。
- 資格の取り消し
- 3年受験できない
- 企業名の公表
- 営業停止
- 資格を使って取得した建設業許可の取り消し
大きな問題に発展することもあるので、虚偽の申告はやめましょう。
この辺は、電気工事施工管理技士の実務経験を虚偽申告するとヤバい【危険です】に詳しくまとめてます。
2級電気工事施工管理技士の勉強方法
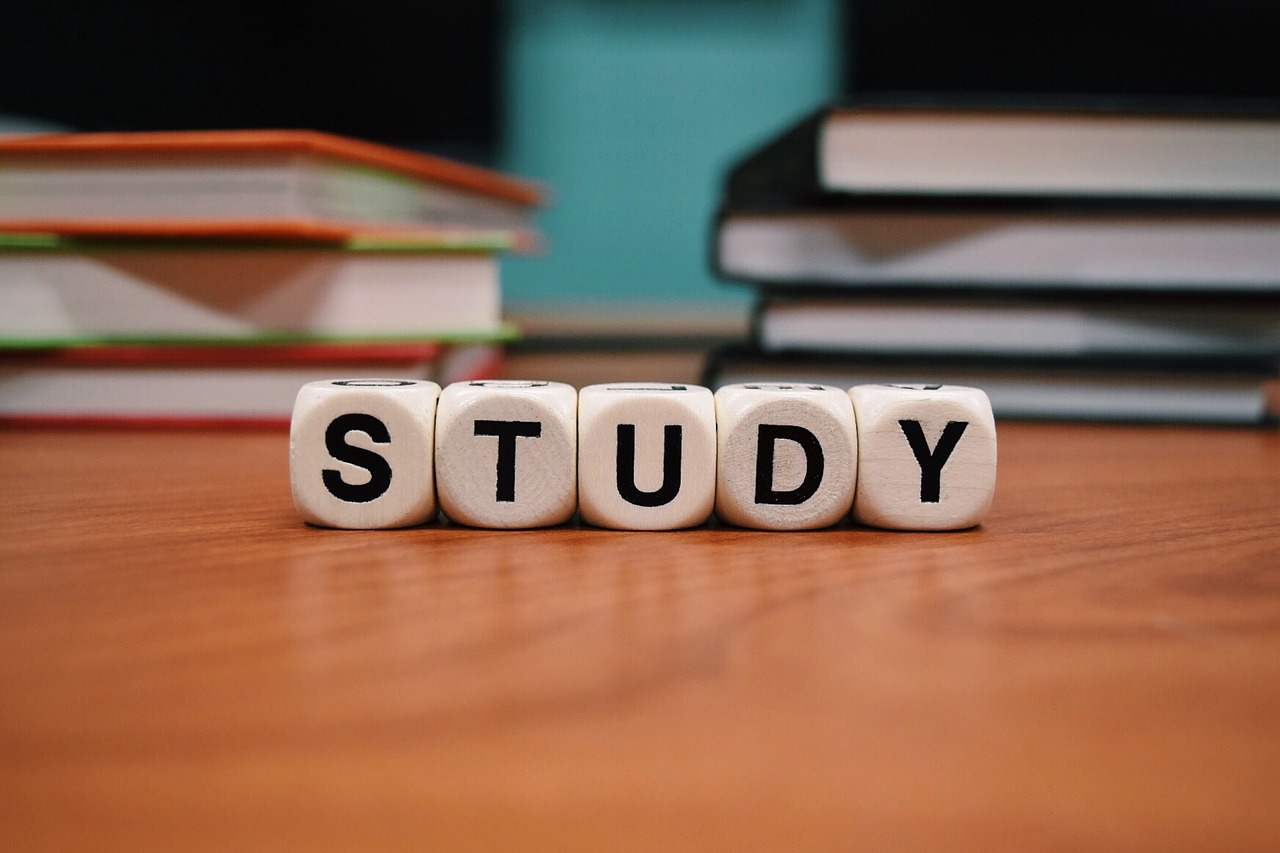

仕事が忙しいから、効率的に勉強したい…
効率的な電気工事施工管理技士の勉強方法を解説します。
- 独学で勉強する
- アプリで勉強する
- 通信教育で勉強する
- 講習会・講座・予備校に通う
仕事をしながら勉強する人が多いですから、自分に合う勉強方法を選びましょう。
①独学で勉強する
独学は自分のペースで勉強できるため、仕事をしながら勉強する人は独学が多いです。
まずは参考書(テキスト)と過去問集を購入してください。
ページの中身を見れるため、ネットではなく書店で購入するのがおすすめです。
パラパラとページをめくってみて、自分が勉強しやすそうな本を選びましょう。
参考書と過去問集を購入するときのコツは、最初から何冊も参考書と過去問集を買わないことです。
まずは参考書1冊、過去問集1冊だけを買って勉強しましょう。
※何冊も買うと勉強の効率が落ちます。
まずはざっと参考書(テキスト)を読んでみましょう。
わからないところは重点的に読み込んで勉強してみてください。
参考書を読んだら過去問集を最低でも3周は解いて勉強してください。
できれば、過去5年分くらいの過去問を解くとかなり良いです。
特に苦手なジャンルは何周も解くようにしてください。
独学で合格するコツは、毎日少しずつでも勉強を続けることです。
仕事の日は勉強せず、休日だけ勉強しようとするのはなかなかやる気がでないものです。
1日1時間でも30分でもいいので、毎日コツコツ勉強するのが合格のコツ。
おすすめのテキスト・参考書・問題集
電気工事施工管理技士のおすすめのテキスト・参考書・問題集は下記のとおりです。
②アプリで勉強する
2級電気工事施工管理技士向けの勉強アプリは下記の2つです。
アプリなので、スキマ時間でも勉強しやすいですよ。
ただし、アプリだけで合格するのは難しいので、本・通信教育・講習会などを併用しましょう。
③通信教育で勉強する
通信教育のメリットは、合格率の高いテキストで勉強できることと、担当講師に添削してもらえることです。
特に、第二次検定の経験記述は添削をしてもらうと良いでしょう。
DVDや音声、動画の通信教育もあります。
電車通勤の人は通勤中に勉強することもできます。
また、模擬試験を受けられる通信教育もあるため、自分の実力を試すにもおすすめです。
④講習会・講座・予備校に通う
講習会・講座・予備校に通って勉強する人もいます。
ただし、仕事をしながら勉強する場合は通うのが難しい人も多いです。
普段は独学や通信教育で勉強して、試験間近に講習会に参加するのも良いでしょう。
電気工事施工管理技士の代表的な講習会をご紹介します。
2級電気工事施工管理技士の勉強時間

勉強時間の目安を知りたい。
合格するために必要な勉強時間は約300〜400時間です。
| 勉強時間 | 勉強期間 |
| 1日1時間 | 約12ヶ月 |
| 1日2時間 | 約6ヶ月 |
| 平日1時間、休日3時間 | 約10ヶ月 |
勉強期間は余裕をもったスケジュールを組みましょう。
2級電気工事施工管理技士と併せておすすめの資格4選【転職も有利】


キャリアアップしていきたいんだよね。
結論、下記の4つがおすすめです。
- 電気工事士
- 建築設備士
- 電気主任技術者
- 設備設計一級建築士
資格を取得することで年収アップしたり、転職も有利になるでしょう。
それぞれ下記の項目もまとめたので、キャリアアップの参考にしてみてください。
- どんな資格?
- おすすめの理由
- 受験資格
- 合格率
- 試験の難易度
電気工事士
| どんな資格? | 電気工事の業務独占資格 |
| おすすめの理由 | 電気工事の知識を深められるから |
| 受験資格 | 誰でも受験できる※ただし第一種は5年以上の実務経験がないと免状が交付されない |
| 合格率 |
|
| 試験の難易度 |
|
施工の資格ですが、施工管理が勉強しておいて損はありません。
職人さんに指示を出すときに、施工面の知識もあるとコミュニケーションをとりやすいから。
第二種は誰でも受験できるため、まずは取得してみるのがおすすめです。
電気工事士の詳細は、電気工事士1種2種の資格難易度や合格率!勉強や技能試験のコツにまとめています。
建築設備士
| どんな資格? | 建築士に対して建築設備の設計や工事監理のアドバイスを行う |
| おすすめの理由 | 設備全体の知識を深められるから |
| 受験資格 | 所定の実務経験年数がある一級建築士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、空気調和・衛生工学会設備士、電気主任技術者など |
| 合格率 | 約20% |
| 試験の難易度 | ★★★★☆ |
電気に限らず、設備全体の設計知識が増えるためおすすめです。
設計寄りの資格ですが、図面を見る力がつくため、施工管理の仕事にも活かせます。
1級電気工事施工管理技士を取得すれば受験資格を得られるため、2級に合格したら1級も受験してみましょう。
建築設備士の詳細は、建築設備士の試験の難易度!独学でも合格できるのか?にまとめています。
電気主任技術者
| どんな資格? | 事業用電気工作物や自家用電気工作物の保安業務を行う |
| おすすめの理由 | 工事計画も行うため知識を活かせるから |
| 受験資格 | 誰でも受験できる |
| 合格率 |
|
| 試験の難易度 | ★★★★★ |
電気工作物の保安業務の資格ですが、工事計画も勉強するため施工管理に活かせます。
ただし、試験の難易度は電気系資格の中でも最高峰。
いずれ挑戦してみるのがおすすめです。
電気主任技術者の詳細は、電気主任技術者・電験試験の難易度や年収!三種二種一種のコツにまとめています。
設備設計一級建築士
| どんな資格? | 3階以上で床面積5000㎡超の建築物の設備設計や適合性の確認を行う |
| おすすめの理由 | 図面を見る知識が深まるから |
| 受験資格 |
|
| 合格率 | 約40% |
| 試験の難易度 | ★★★★☆ |
設備設計を行う資格です。
設計寄りの資格ですが、図面を見る力がつくのでおすすめ。
ただし、一級建築士がないと受験ができないため、いずれ建築方面の勉強もしたい人は視野に入れておきましょう。
設備設計一級建築士の詳細は、設備設計一級建築士の難易度を合格率や受験資格から分析してみたにまとめています。
まとめ【2級電気工事施工管理技士の難易度は高いがしっかり勉強すれば合格できる】

この記事をまとめます。
- 2級電気工事施工管理技士を取得すると年収アップしやすかったり、転職が有利になる
- 2級は一般建設業にて主任技術者を担当できる
- 第一次検定×第二次検定の合格率は約27%
- 第二次検定の経験記述問題が難しい。事前に文章を作っておこう
- 勉強方法は本で独学、アプリで勉強、通信教育、講習会
2級電気工事施工管理技士は不足しているため、資格を取得すれば転職も有利になり、年収も上がります。
実務経験が必要ですが、きちんと勉強すれば合格できる資格です。
仕事をしながら勉強するのは大変なことですが、さっそく今日から勉強を始めてみましょう。
今日できないことは明日もできないし、結果、ずっとできません。
いつかは頑張って勉強しないといけないので、それなら今日から始めた方がいいかと。
試験の合否は1点が左右します。
不合格になると、また勉強のやり直しでかなり大変ですよ。
1点でも多くとって合格する方法はただ1つ、1日も速く勉強を始めることです。
ちなみに、電気工事施工管理技士の資格を取得して転職を考えてる人は、自分に合う企業を探しましょう。
転職に失敗したくない人は、施工管理(現場監督)の転職先の会社選びのコツ【転職活動方法も解説】を参考にどうぞ。
- ブラック企業を選ばない方法
- あなたに合う会社を見つける方法
などを解説しています。
あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!