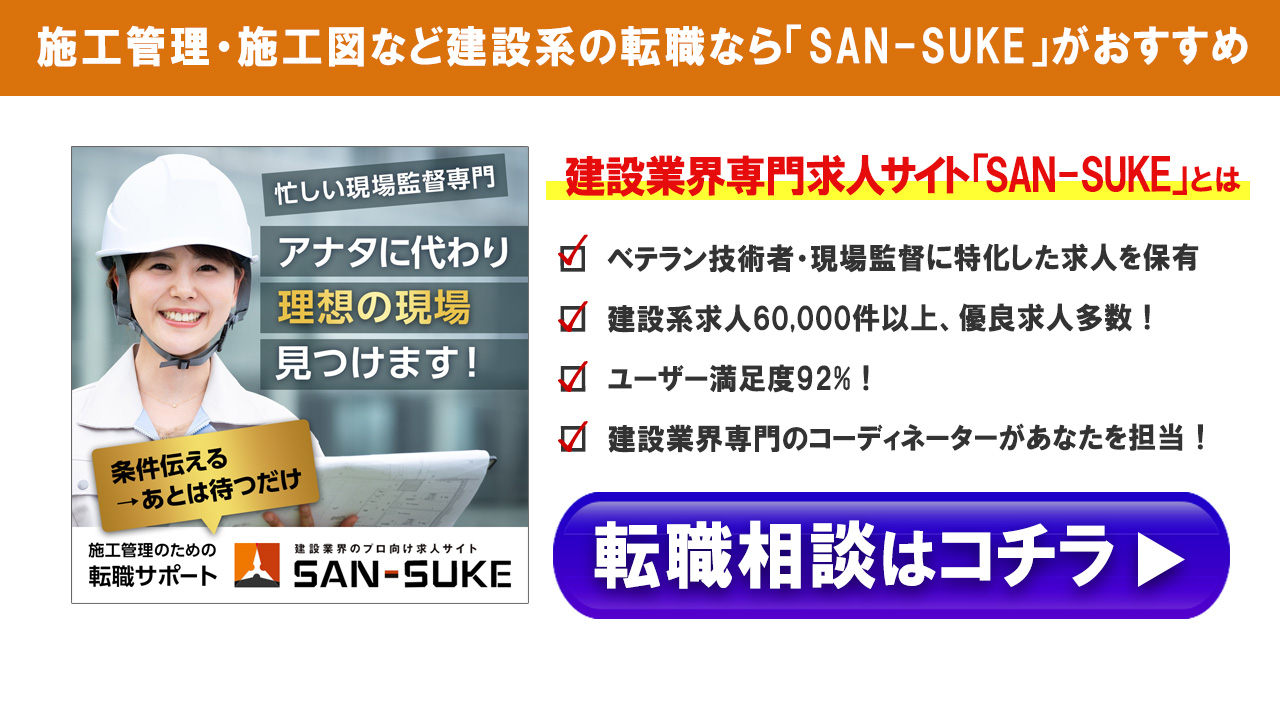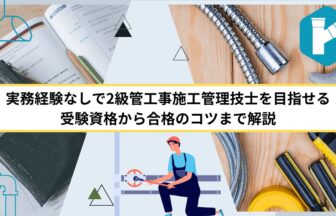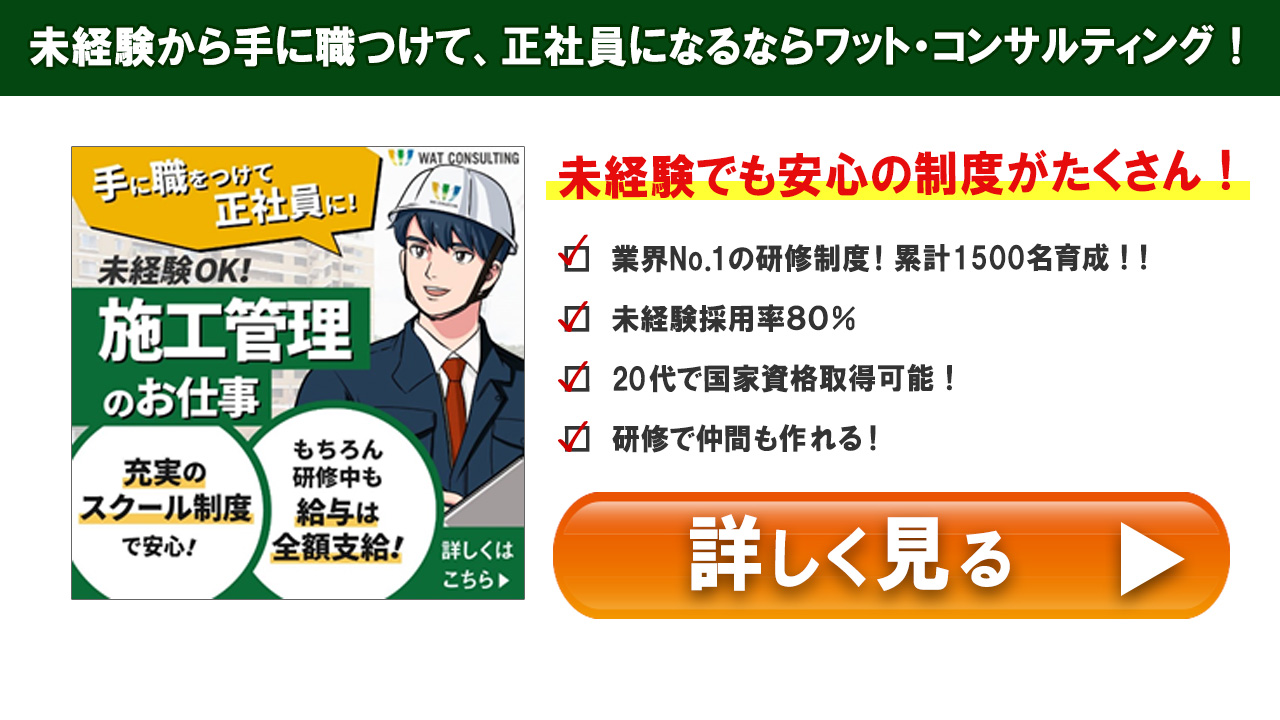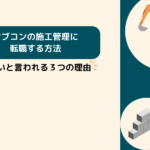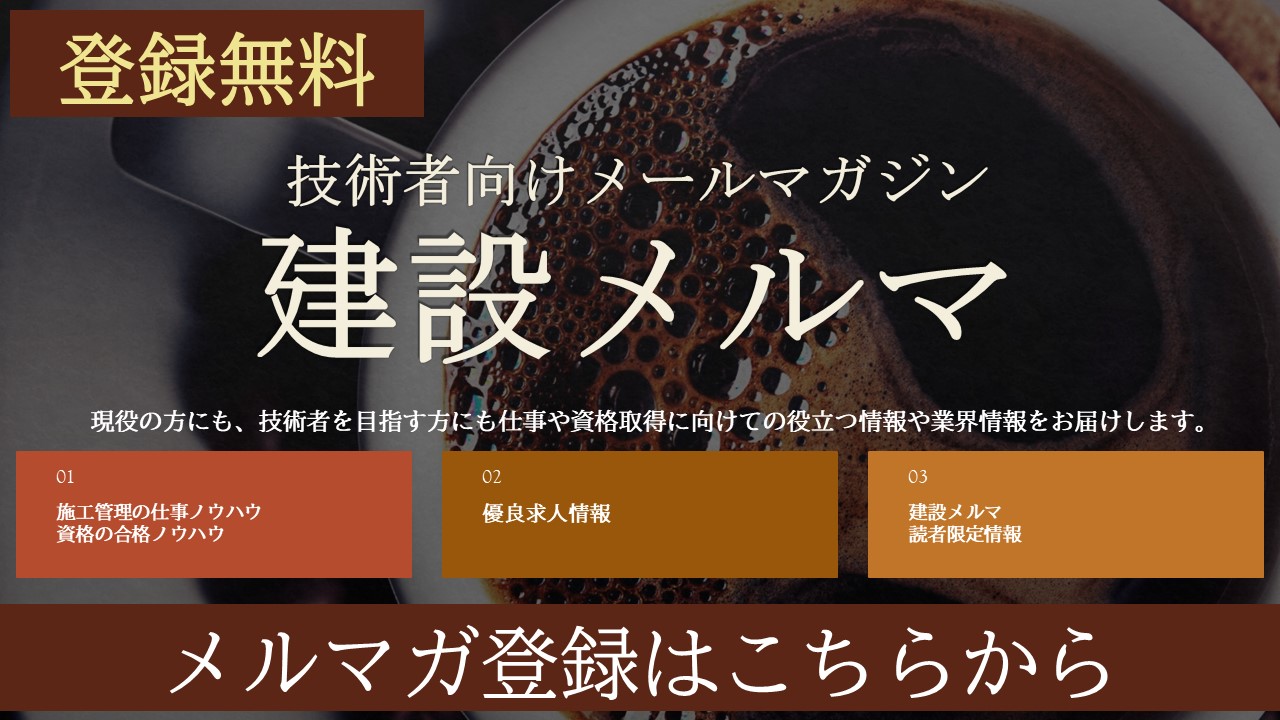そもそも建築設備士は設計もやるの?
あと、設備設計一級建築士との違いも知りたいな。
こういった疑問に答える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- 建築設備士と建築士の違いがわかる
- 建築設備士と設備設計一級建築士の違いがわかる
- 建築設備士と設備系の施工管理技士の違いがわかる
この記事では、建築設備士と建築士の違いを解説します。
具体的には、下記の項目で違いを解説していきます。
- 仕事内容
- 年収
- 技術者の種類
- 試験の合格率
- 試験の難易度
- 経営事項審査の点数
- 独立
また、設備設計一級建築士や設備系の施工管理技士との違いも解説します。
資格の違いを知って、キャリアアップの参考にしてみてください!
建築設備士と建築士の違い
| 建築設備士 | 建築士 | |
| 仕事内容 | 建築士に設備設計や工事監理のアドバイスを行う | 建築設計や工事監理を行う |
| 年収 | 500~800万円 | 500~1000万円 |
| 技術者の種類 | 主任技術者と専任技術者※1年以上の実務経験が必要 | 一級:監理技術者二級・木造:主任技術者 |
| 試験の合格率 | 約20% | 約10% |
| 試験の難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 経営事項審査の点数 | 1点(1年以上の実務経験が必要) | 一級:5点二級・木造:2点 |
| 独立 | ◯(建築士など他の資格もあった方が良い) | ◎ |
最大の違いは、建築士が設計や監理を行うのに対し、建築設備士はアドバイスのみを行うこと。
建築設備士は「建築士に設備設計や工事監理のアドバイスを行う資格」であり、基本的には自ら設計・監理を行うことはありません。

と思うかもしれませんが、建築設備士を取得すると実務経験なしで建築士試験を受験できます。
詳しくは、建築設備士のメリット5選【試験の難易度や勉強のコツも解説する】にまとめています。
ちなみに、建築士には下記の3種類があります。
| 資格 | 設計範囲 |
| 一級建築士 | すべての建築物の設計が可能 |
| 二級建築士 | 延べ床面積300㎡以下/高さ13m以下/軒高9m以下/3階以上木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以下/高さ13m以下/軒高9m以下/3階以上
木造の一般建築物で延べ床面積1000㎡以上/高さ13m以下/軒高9m以下/1階建て |
| 木造建築士 | 木造で延べ床面積300㎡以下高さ13m以下
軒高9m以下 2階建てまでの設計が可能 |
ちなみに、一級建築士で2年以上の実務経験があると、建築設備士の受験資格を得られます。
建築士資格については、下記の記事にまとめたので参考にしてみてください。
建築設備士と設備設計一級建築士の違い
| 建築設備士 | 設備設計一級建築士 | |
| 仕事内容 | 建築士に設備設計や工事監理のアドバイスを行う | 3階以上で床面積5000㎡超の建築物の設備設計や適合性の確認 |
| 年収 | 500~800万円 | 700~1000万円 |
| 技術者の種類 | 主任技術者と専任技術者※1年以上の実務経験が必要 | 監理技術者 |
| 試験の合格率 | 約20% | 約40% |
| 試験の難易度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 経営事項審査の点数 | 1点(1年以上の実務経験が必要) | 5点 |
| 独立 | ◯(建築士など他の資格もあった方が良い) | ◎ |
そもそも設備設計一級建築士は、一級建築士として5年以上の設備設計の実務経験がないと受験できません。
つまり、一級建築士の先にある資格です。
合格率は設備設計一級建築士の方が高いですが、一級建築士で実務経験を積まないと受験できない点から、難易度はかなり高いといえるでしょう。
一方、建築設備士は先ほどお伝えしたとおり、建築士に設備設計や工事管理のアドバイスを行う資格です。
設計や監理の有無が大きな違いです。
ただ、建築設備士から取得しておいて損はありません。
設備設計一級建築士の受験前に講習を受ける必要があるのですが、建築設備士として建築士に設計・監理のアドバイスを行った経験があれば、一級建築士を取得する前の経験も実務経験にカウントされます。
また、設備設計一級建築士の修了考査(試験)で「建築設備に関する科目」が免除されます。
設備設計一級建築士については、設備設計一級建築士の難易度を合格率や受験資格から分析してみたに詳しくまとめています。
建築設備士と設備系の施工管理技士の違い
| 建築設備士 | 設備系の施工管理技士 | |
| 仕事内容 | 建築士に設備設計や工事監理のアドバイスを行う | 現場の施工管理業務を行う |
| 年収 | 500~800万円 | 400~1000万円 |
| 技術者の種類 | 主任技術者と専任技術者※1年以上の実務経験が必要 | 1級:監理技術者2級:主任技術者 |
| 試験の合格率 | 約20% | 約25% |
| 試験の難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 経営事項審査の点数 | 1点(1年以上の実務経験が必要) | 1級:5点2級:2点 |
| 独立 | ◯(建築士など他の資格もあった方が良い) | ◯ |
建築設備士が設計に関する資格であるのに対し、施工管理技士は現場の管理業務を行います。
施工管理技士は設計図面を見ながら工事を進める立場なので、業務範囲がまったく違います。
設備系の施工管理技士の仕事内容は、設備施工管理の6つの仕事内容【きついところや激務の感じも解説】を参考にどうぞ。
ちなみに、設備系の施工管理技士は下記の種類があり、それぞれ1級と2級があります。
- 管工事施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
詳しくは下記の記事を参考にどうぞ。
まとめ:建築設備士と他の資格の違いを知っておこう

建築設備士・建築士・設備設計一級建築士・設備系の施工管理技士の違いを解説してきました。
まとめると、4つの資格の大きな特徴は下記のとおりです。
- 建築設備士:建築士に設備設計や工事監理のアドバイスを行う
- 建築士:建築設計や工事監理を行う
- 設備設計一級建築士:3階以上で床面積5000㎡超の建築物の設備設計や適合性を確認する
- 設備系の施工管理技士:現場の施工管理業務を行う
違いを知りつつ、どの資格を取得するか考えていきましょう。
ちなみに建築設備士を取得するコツは、建築設備士の試験の難易度!独学でも合格できるのか?にまとめています。
あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです!