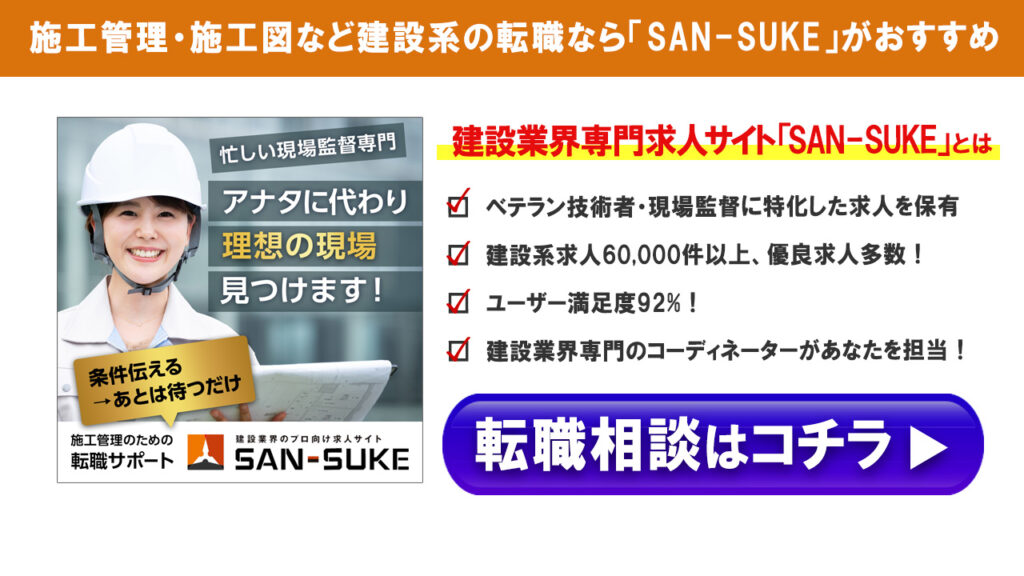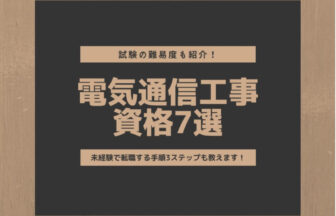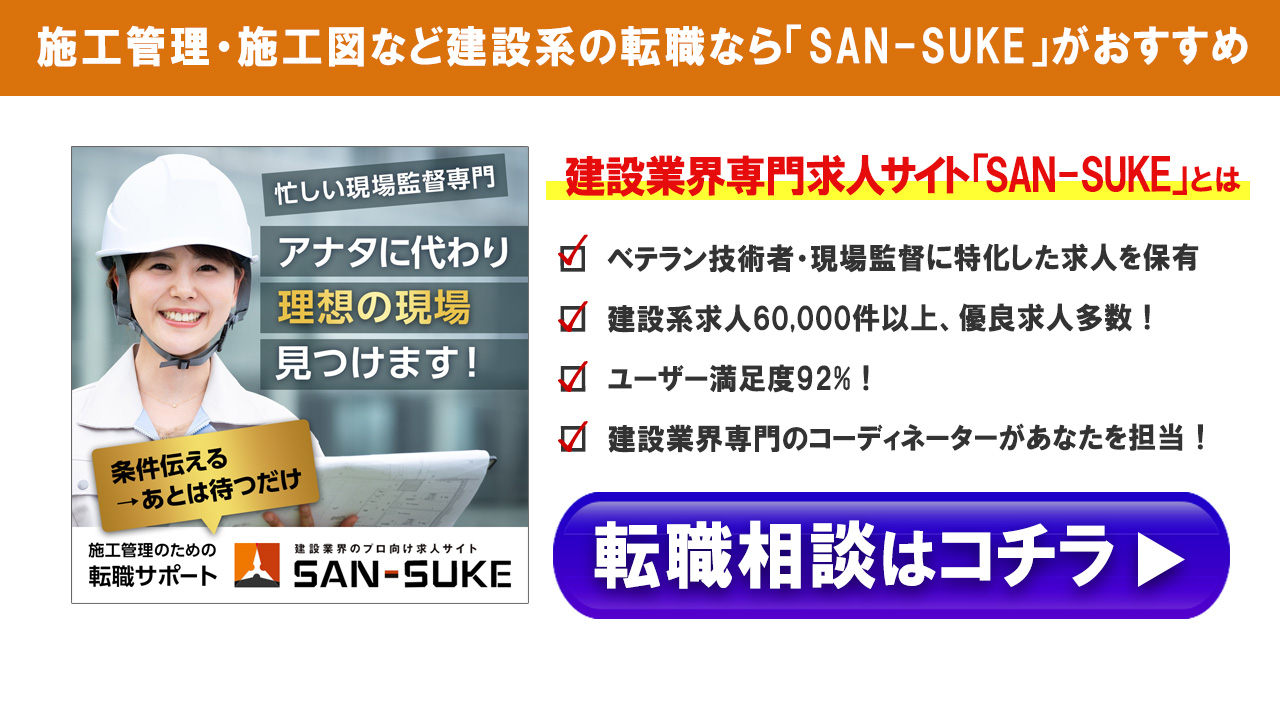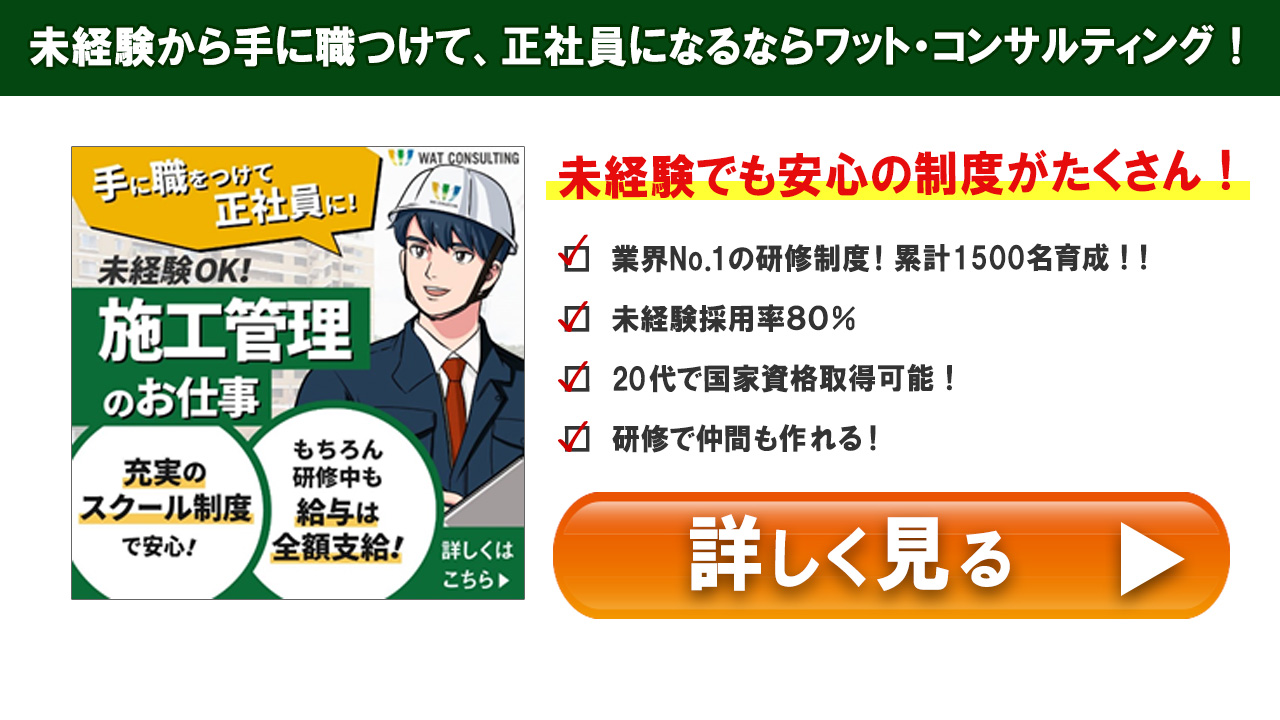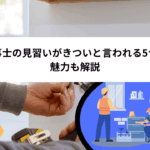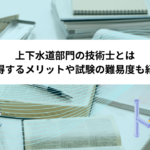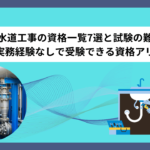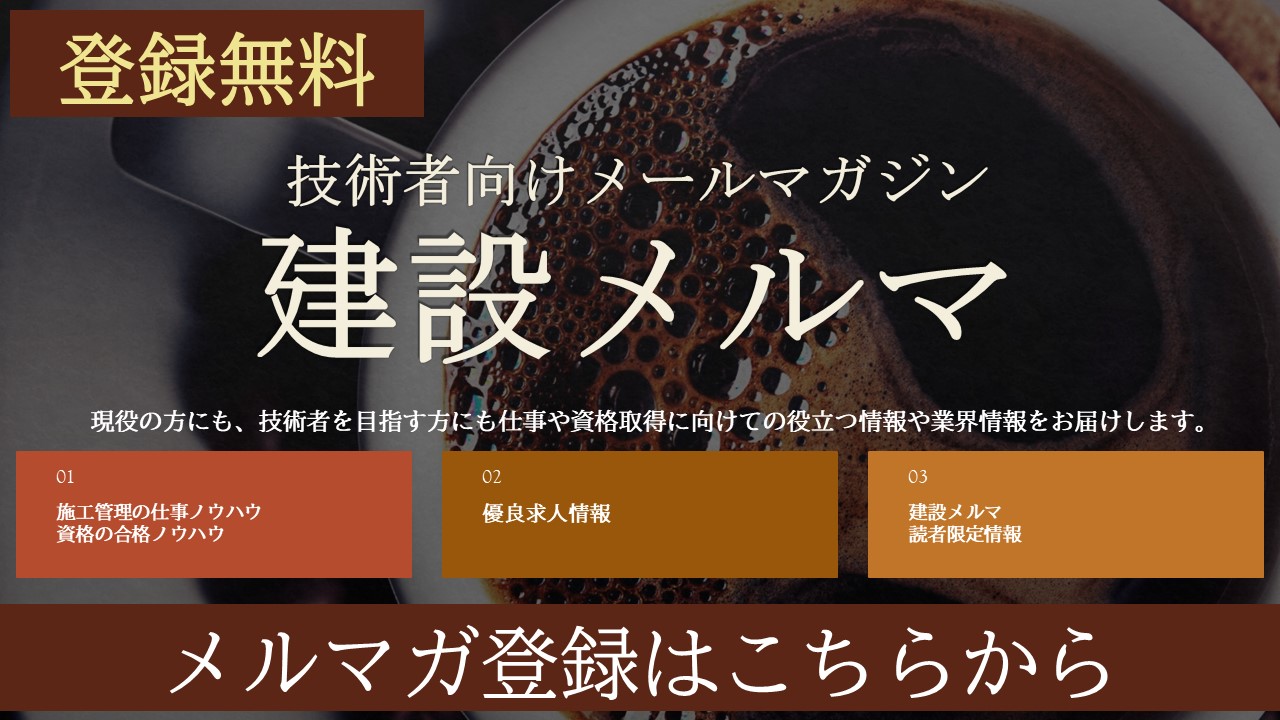簡単な試験みたいだけど、そんな簡単な試験で落ちたら恥ずかしい…
1回で合格したいから、合格するための勉強方法とかも知りたい。
資格をとってキャリアアップしたいな。
こういった疑問や不安に応える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- ガス消費機器設置工事監督者の合格率がわかる
- ガス消費機器設置工事監督者に合格するコツがわかる
- ガス消費機器設置工事監督者のキャリアプランがわかる
ガス消費機器設置工事監督者は、下記のガス設備の設置・変更の工事や監督をする国家資格です。
- ガス風呂釜
- ガス湯沸かし器
- ガス機器の排気筒・排気扇
独占業務の国家資格であるため、ガス業界でキャリアアップをするなら必ず取得しておきましょう。
試験はそんなに難しくないので、きちんと勉強すれば大丈夫です。
合格のコツも解説するので、1回で合格しましょう。
資格取得後のキャリアプランも解説しますね。
目次
ガス消費機器設置工事監督者の合格率
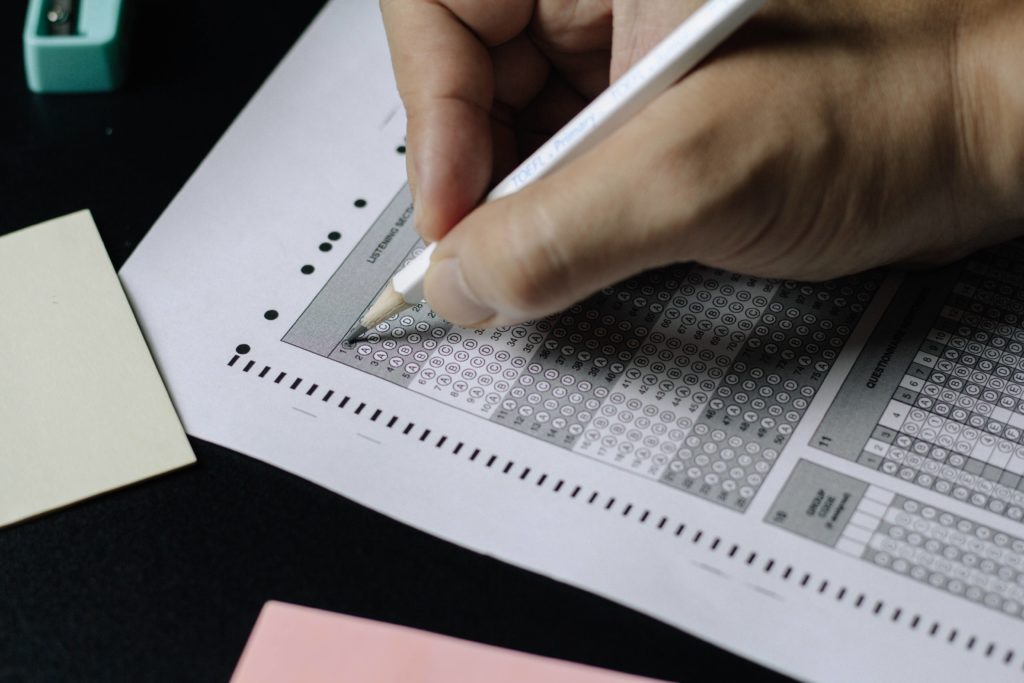
結論、ガス消費機器設置工事監督者のおおよそ合格率は85%前後です。
※年度や開催地によって変わります。
8割以上の人が合格する試験なので、難易度は低いですね。
ただし、決して合格率100%ではないので、落ちてる人がいるのも事実。
後述しますが、2日間の講習を受けて、最終日の修了試験で合格する流れです。
きちんと講習を聞いていれば合格できるレベルなので、2日間を集中して勉強しましょう。
ガス消費機器設置工事監督者とは
そもそも「ガス消費機器設置工事監督者」とは、下記のガス設備の設置・変更の工事や監督を行う国家資格です。
- ガス風呂釜
- ガス湯沸かし器
- ガス機器の排気筒・排気扇
これらのガス機器は一酸化炭素中毒などの事故が起きやすい「特定ガス消費機器」であり、危険を伴うためガス消費機器設置工事監督者の資格をもった人が工事・監督を行うことが義務づけられています。
※ガス湯沸かし器は暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器はガスの消費量が12kwを超えるもの、その他のものは7kWを超えるもの。
工事が終わったら事業者名か監督者名が記名されたラベルを現地に貼るため、責任のある資格といえますね。
受験資格について
ガス消費機器設置工事監督者の受験資格は、特にありません。
つまり、誰でも受験できます。
ガスに関する仕事をしたことがない人でも、合格する人もたくさんいます。
仕事でガス設備を扱ってる人には、かなり難易度の低い試験です。
ただし前述のとおり、落ちる人は落ちるので気を抜かずに講習に臨みましょう。
ガス消費機器設置工事監督者の講習
ガス消費機器設置工事監督者は、2日間の講習を受けないといけません。
これらを2日間で勉強し、講習最終日の最後に1時間の修了試験を受けます。
修了試験は1時間しかないのに50問も出題されるため、スピーディーに回答する必要あり。
1問2点で60点以上で合格です。※30問以上の正解が必要。
幸い4択問題なので、得点はとりやすくなっています。
試験結果は1ヶ月後くらいに郵送で送られてきます。
ガス消費機器設置工事監督者の試験に合格するための勉強方法


どうすれば合格できるかな?
結論、2日間の講習をしっかり聞くしかありません。
なぜならガス消費機器設置工事監督者は、テキストや過去問集が書店やAmazonで売ってないから。
事前学習をする方法がないので、講習をしっかり聞くのが合格する唯一の方法です。
1日目の夜に復習しておく
1日目の講習が終わったら、夜は復習に当ててください。
2日目の講習が終わったら、10分の休憩の後すぐに修了試験です。
じっくり復習できるのは1日目の夜だけなので、ここが勝負かなと。
講習では試験に出るところは強調されるので、ノートをとっておきましょう。
また、テキストの練習問題は修了試験の問題と似てるので、練習問題で慣れるのもコツですね。
前述のとおり、修了試験は1時間しかないのに50問も出題されるので、スピーディーな回答が必要です。
出題範囲も広いので、しっかり講習を聞いて、1日目の夜も復習しましょう。
ちなみに、試験前は特に準備は不要です。
何も勉強せず講習に臨んでも合格できるレベルなので、講習を本気で聞けるかが勝負です。
ガス消費機器設置工事監督者の資格取得後のキャリアプラン


結論、転職が有利になります。
なぜなら、ガス消費機器設置工事監督者は独占業務の国家資格だから。
- ガス会社
- ガス設備会社
などに転職が有利になります。
ガス機器設置スペシャリストと簡易内管施工士も取得しておく
今後のキャリアプランですが、できれば下記の2つの資格も取得しておきましょう。
- ガス機器設置スペシャリスト
- 簡易内管施工士
まだ取得してない人は、ガス機器設置スペシャリストと簡易内管施工士も取得していきましょう。
ちなみに、ガス機器設置スペシャリストと簡易内管施工士については下記の2記事にまとめてます。
まとめ【ガス消費機器設置工事監督者の合格率は約85%】

ということで、ガス消費機器設置工事監督者を取得したいなら、まずは講習日程を確認しましょう。
一般財団法人日本ガス機器検査協会のホームページから、最寄りの会場の日程を確認してみてください。
ホームページに申し込み方法も書いてあるので、それに従って申し込みすればOKです。
試験の合格率はけっこう高いですが、2日間の講習で寝てたりすると落ちますよ。
講習をしっかり聞くのが、合格の最大のコツです。
ちなみに、今後は下記の資格も取得を目指しましょう。
- ガス機器設置スペシャリスト
- 簡易内管施工士
また、さらなるキャリアアップを目指すなら、下記の資格も取得してみてください。
- 管工事施工管理技士:ガス配管の施工管理
- ガス主任技術者:ガス工作物の工事・維持・運用の保安監督
- 高圧ガス製造保安責任者:高圧ガスの製造・販売の保安監督
これら3つの資格の詳細は、下記の4記事にまとめてます。
あなたのキャリアアップの参考になればうれしいです。